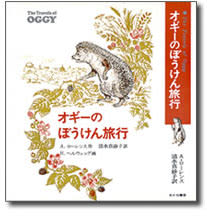あかね書房のあかね世界の児童文学、アン・ローレンス著、ハンス・ヘルウェッグ画、清水真砂子訳の児童向けの本です。
ハリネズミは、危険が迫ると、丸くなる、という強い本能があるそうです。実際、動きの鈍いこの小さな動物は、丸いとげの塊になることによって、外敵から身を守っています。
でも、やさしいイギリス人親子の一家が引っ越した先へ向けてぼうけん旅行をするオギーは、かあさんが何度も言っていた、本能に逆らう行動、「道路でくるまが迫ってきたら、けっしてまるまってはだめ、はしるの。」という教えに助けられ、無事にやさしい一家の元にたどり着き、寒くなる季節にたまらずに冬眠へと誘われ、満たされて眠ってしまいます。春になって、寝ぼけたオギーを起こしに来たやんちゃな仔猫のティギーとの出会いが続編となります。
何故か、今でも理由は不明なのですが、衝動的に買った本で、続編の「オギーのゆかいな友だち」も購入し、幾度となく読んだばかりか、主人公であるハリネズミのオギーのキャラクターはいつも私の中のどこかにあって、S.A.S(英軍の特殊部隊)の教練の中に、郊外でのサバイバル食としてハリネズミの丸焼きというのがあるのを知ったとき、「オギーならぷりぷり憤慨するだろうな・・」などと思ってしまったこともあるのです。
訳者の清水真砂子さんはル・グインのゲド戦記シリーズの訳も手がけておられ、この本を買う前から存じ上げていたのですが、2007年の学校図書館図書整備協会の会報にエッセイを載せておられ、そのなかで、オギーに触れています。
曰く、旅行先の北欧のとある街でふと前を横切るオギーに出会った、と。もちろん物語の中、ロンドン郊外で暮らすオギーではないのですが、生まれて初めて見たハリネズミの動くさまを見たとき、28年の年月をあっさりと越えて、氏のなかの一部となっていたオギーが呼び覚まされた、との逸話でした。二つのお話の翻訳中に、オギーに魅せられ、その存在がずっと残っていたことに、あらためて文学の持つ力に感嘆した様子を書いておられます。
作者のローレンスは1942年英国生まれ、自然保護関係の職を経て教職を務め、結婚後作家活動、1987年に病死されています。オギーのシリーズは未訳のOggy and the holiday、というのがありますが、おそらくは訳者の清水氏も訳したかったのでは無いかと思われるこの作品については、「休暇」を実体のあるものだと勘違いしているオギーが、「休暇」を見に行くお話ではないかと想像しています。原著は手に入るようですが、まずは、どこかに眠っている2冊のオギー、何かの折りに探してみようと思っているのです。
ハリネズミは、危険が迫ると、丸くなる、という強い本能があるそうです。実際、動きの鈍いこの小さな動物は、丸いとげの塊になることによって、外敵から身を守っています。
でも、やさしいイギリス人親子の一家が引っ越した先へ向けてぼうけん旅行をするオギーは、かあさんが何度も言っていた、本能に逆らう行動、「道路でくるまが迫ってきたら、けっしてまるまってはだめ、はしるの。」という教えに助けられ、無事にやさしい一家の元にたどり着き、寒くなる季節にたまらずに冬眠へと誘われ、満たされて眠ってしまいます。春になって、寝ぼけたオギーを起こしに来たやんちゃな仔猫のティギーとの出会いが続編となります。
何故か、今でも理由は不明なのですが、衝動的に買った本で、続編の「オギーのゆかいな友だち」も購入し、幾度となく読んだばかりか、主人公であるハリネズミのオギーのキャラクターはいつも私の中のどこかにあって、S.A.S(英軍の特殊部隊)の教練の中に、郊外でのサバイバル食としてハリネズミの丸焼きというのがあるのを知ったとき、「オギーならぷりぷり憤慨するだろうな・・」などと思ってしまったこともあるのです。
訳者の清水真砂子さんはル・グインのゲド戦記シリーズの訳も手がけておられ、この本を買う前から存じ上げていたのですが、2007年の学校図書館図書整備協会の会報にエッセイを載せておられ、そのなかで、オギーに触れています。
曰く、旅行先の北欧のとある街でふと前を横切るオギーに出会った、と。もちろん物語の中、ロンドン郊外で暮らすオギーではないのですが、生まれて初めて見たハリネズミの動くさまを見たとき、28年の年月をあっさりと越えて、氏のなかの一部となっていたオギーが呼び覚まされた、との逸話でした。二つのお話の翻訳中に、オギーに魅せられ、その存在がずっと残っていたことに、あらためて文学の持つ力に感嘆した様子を書いておられます。
作者のローレンスは1942年英国生まれ、自然保護関係の職を経て教職を務め、結婚後作家活動、1987年に病死されています。オギーのシリーズは未訳のOggy and the holiday、というのがありますが、おそらくは訳者の清水氏も訳したかったのでは無いかと思われるこの作品については、「休暇」を実体のあるものだと勘違いしているオギーが、「休暇」を見に行くお話ではないかと想像しています。原著は手に入るようですが、まずは、どこかに眠っている2冊のオギー、何かの折りに探してみようと思っているのです。