KINU洋画会で
人物画は描きたくない
というような話を聞いた
だのに大塚先生は描かせたいみたいな?
描きたくないといえばがっかりするみたいな話
要は 人物はデッサンが狂うと
話にならない部分があるので
無力感にさいなまれるということらしい
だから
楽しくない と
大塚先生は
みんなが 描く力をつけられるように
と人物を描かせ
彩友会でも鉛筆画を描かせるのだと思うが
なかなか真意が伝わらないようだ
それで↓の本を読んで思ったことに似ていると思った
究極のところ 中国語や古代の文字
古代の言葉
それらの知識がない素人には
分かりえないことがあるので
苛つく
それでも 梅原猛は なぜ この本を企画したか
そりゃあ 教育的意図があったのだなと思う
詩経についてなんの知識もない読者に
道案内のやらせ質疑応答を入れているもの
でも 学問というものは
素人に縁のないものだろうか?
学者がやっていることを覗いてみる楽しみ
これが 素人の楽しみだぞ と思う
この本に刺激されて
詩の分類
風 雅 頌
と
賦 比 興
この六つのことを 絵の市民グループのことで
応用して考えてみる
梅原猛はなんの学者かというと
哲学者なのだよね
で
美術についていろいろ教えてくれるのだが
文化歴史に関することに繋がっていく
これが面白い
詩の六義
絵で言えば
最初の風 雅 頌 はジャンル分けみたいなものだ
風は 民謡 民衆の歌という感じ
雅は貴族とか王朝文化みたいなの
頌は霊的なものとの交信みたいなものか?
こういう風に表現の世界を3つに分ける
私は勝手にジャンル分け
と考えたのだが
古代で言えば
絵画は 雅 頌この二つしかなかったような気もする
いいんだ ジャンル分けと考えることにした
風景画 人物画 とか描く対象で分けたり
抽象画 具象画 という風に表現方法を形式的に考えたり
で 賦 比 興
賦というのは一つ一つ あげて数え上げるように
という歌
と考えると
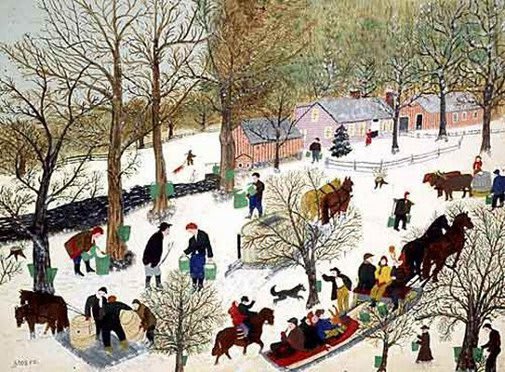
このグランマ・モーゼスのような描き方
がこれにあたると思う
比 というのは詩の場合なぞらえる歌
というか 比喩 暗喩 象徴 そういう歌
絵画にも象徴とか比喩とか
そういう風なものもあるけれど
私がイメージしたのは
絵画でとらえて表現するときに
関係をとらえるではないか
それを 点線面で考えることもあり
強弱
とか塊とか
比較しながら物事をとらえる
そこを 整理して考えることができるようにすれば
わけ和漢愛というときの道筋が見えて
面白くなると思うのだが
興 というのは
この本の中では
字の成り立ちがお酒を入れる器を両手で持って
地にそそぐと
地の神様が起き上がる
復興の興の字だからね
だから歌うことによって 内的な生命を呼び覚ます
という意味
それで 呪歌 となるわけだ
絵でも描くことで
内的なパワーを呼び覚ます
・・
そんな 呪術的なことではなく
一つ一つあげていく美しさでもなく
あれやこれや 確かめてただす日でもなく
ゥわット 湧いてくるもの
だいたい 絵ってそんなものだろう
何を描きたいのか そのつかみ 匂い 本性みたいなもの
そういうようなことを 考えた
ま でっち上げだが
この 頌とか 興とか
いわば霊的なものとのかかわりで文化を見るというのは
現代ではあまりないが
古代の文化を考えると欠かせない視点だ
実は 科学万能の時代で意識からすっぽ抜けているけれど
実際は人間の心に占める部分は大きいかもしれないとも思った
梅原猛は歴史観 唯物史観では読み取れないものについて
いろいろ言っているが
それはあるな
という気がしている
















