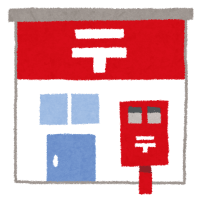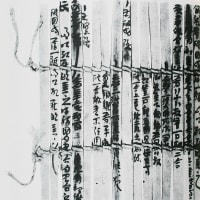ダウおよび日経平均株価の反発がもの凄いことになっており、日経では一時19000円代を割り込むなど、このまま株安が続くのかと感じながらチャートを眺めていると、そこから一気に買いが入り、結果900円余りの上げ幅で終了。ダウに関しては上げ幅が史上最大だとか。まさに大混乱の様相だ。
そんな中、多くの人が懸念することといえば、やはりこのまま景気は後退してしまうのだろうか、ということだろうが、株価そのもので景気云々を判断することはあり得ないのではないかと考える。
なぜなら、株価というのは本来、金融商品としての企業株の値が、実体に見合ったものかを検証しなければならないからだ。
今年10月には24000円の平均株価だったものが、2か月ほどで19000円ほどまで下がった。これは投資家自身の「今後景気が後退するかもしれない」という心理状態が働いたからだとする知識人もいるが、もちろんそれだけでこれほどの値が下がるとは思えない。
このことは日経平均株価が、24000円という値が付いたことと、実体経済の矛盾とを比較すれば容易に察しがつくことであるが、もちろん筆者は経済に関しては全くの素人であるから、憶測とでもいっておこうと思う。
24000円という破格ともいえる平均株価、それが現状(10月地点)、適切な株価だったのかといえば、決して適正とはいえない。では19000円(12月現在)が適正だったのかといえば、それも違う。おそらく現在の国内企業の適正株価というのは10000円から12000円ほどではないかと考える。したがって、現在はどう足掻いてみても下げ傾向であるということだ。
このことは国内企業の時価評価額が、年々落ちてきていることで証明ができる。空前のバブル期と比較してみても、その差は歴然であるから、やはりバブル期を抜きにこの話はできないのだ。
当時もおなじようにバブルがはじけると、国内企業の株価は適正株価へと値を下げ出した。しかもこの時期は、不良債権やら不景気やらとメディアや知識人たちが大騒ぎすることで、さらに株価は下落し、適正株価を下回ったことで、本当の意味での不景気が起こり、長引くデフレ社会へと続いていくことになってしまった。結果、民主党政権時代には平均株価が7000円代にまで下がってしまい、まさに景気のどん底となってしまったのだ。
こうした株価が下がり続ける中で、当然のこととして一般投資家たちは株に手をだすことはなく、しかし第二次安倍政権下におけるアベノミクスの第一の矢が的中し、空前の投資ブームが巻き起こり、株価がグングンと上がっていくことになった。
しかし、国内企業の時価評価額は下がる一方である。しかも新興国であるシナ中共がめざましい経済発展をつづけ、世界企業の時価評価額ランクでも上位を占めるようになってきたことでもわかるように、国内企業の平均株価が24000円だとか19000円の値がついていること自体が異様ともいえるのだ。
ちなみにバブル期の平均株価最高値は38000円くらいである。これはかなり色(一般投資家による投資)がついており、実体の適正株価とは言えない。おそらくこのころの適正株価は20000円ほどだったのではないだろうかと考える。そこから18000円以上もの値(色)がついているのだから、当然バブルと言っていいだろう。
で、現在はというと適正価格を10000円とした場合、プラス9500円くらいの値(色)がついているわけであるから、これもバブルと言っていいのかも知れない。もちろん感じ方は人それぞれであるから、これは筆者独自の考えである。
そんな中、仮にリーマンショック級の株価暴落が起こり、平均株価が下がりだしたとしても、10000円くらい下がったくらいが調度良いものと考える。このことは、GPIF(政府による年金の株式運用)の利率を適正に処置するなどの対策をすれば、それほど日本国内の経済弱体にはつながることもないわけであり、企業に関していえば、時代の流れの中で不要なものは倒産もしくは合併するなどして、生き残りを模索すればよいだけのことである。
このことは、日本国において、いわゆる大企業といわれる企業の比率が、少しばかり多すぎる気もするわけで、もっともっと中小企業が中心となった経済発展へと変貌していかなければならないのではないか、という筆者の想いでもある。
当然、今から30年くらい前のバブル期を絶対肯定するものではないが、本当の意味で、労働者が報われてこその経済発展が、この国の真の「力」にもなっていくと信じてやまない。
そう考えると、リーマンショック級の株価暴落も決して悪いことでもないと思うのだが・・・。
【 ご訪問、有難う御座いました。 】