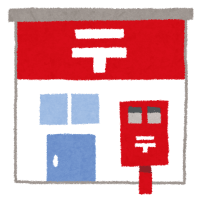2021年3月16日 Wedge REPORT 島澤 諭 (中部圏社会経済研究所研究部長)
【 所 感 】
『財政破綻論』ちょっと気になって記事を読ませて頂いたが、今回の学者さんも他の『財政破綻』論者と同様に、そもそもとして、貨幣そのものの理論をご存じないと見える。
この貨幣の仕組みをきちんと理解すれば、『〇%まで消費税を引き上げなければ…』という論調にはなるまいに…。したがって、もし仮にDSGEなどという統計学を用いて算出せねばならないとすれば、政府が日銀から赤字国債(=政府の赤字は国民の黒字)を発行し、それを市中へ流すことによって、様々な経済的効果が物価の上昇を押し上げる。この物価上昇率が、現在の政府と日銀とが目指す2%にまで達した場合において、GDPに占める個人所得の割合や、消費者指数などのあらゆる統計に基づき、過度な物価上昇にならないための、適切な税収を統計学などを用いて算出することが求められる。
そもそもインフレとは、経済が安定的に循環している状況をいい、例えば、制限速度が40キロのまっすぐな一本道を、時速40キロの車が何台も何台も走行し続けている状態を、 "安定的" と仮定した場合、仮に時速20キロの車が1台走行すれば、他の車も同じ速度で走行しなくてはならず、これによって交通状況が悪化したことになる。この、たかだか1台の車のお陰で、他の車すべてが悪影響を被ることになる。これが、デフレスパイラルといい、この迷惑極まりない車1台こそが、消費税そのものを指し、現在の日本政府が行っている景気対策でもある。
たしかに、時速20キロの速度でしか運転できない人(=敢えて例にはしない)からすれば、この時速20キロで走行する1台の車(=社会保障のための税金)は非常に有難い存在なのかもしれないが、安定的な速度は時速40キロと定められているのだから、否が応でも時速40キロで走行してもらわないといけない。
しかしながら、それも日本政府の大胆な財政出動さえあれば、社会保障すらも補うことが可能であり、これこそがMMTの経済的理論の真骨頂ともいえる。
また、制限速度が40キロの一本道を、全ての車が時速60キロで走行している状況が、スーパーインフレであり、速度超過がもらたす悪影響は計り知れない(=バブルの崩壊など)。だから、時速40キロで走行するように調整しなければならない。この調整こそが経済学者と呼ばれるような学者さんの一番の見せ所でもある。
かつて、本田技研工業(現HONDA)の創設者である本田宗一郎氏はこのような感じで述べられている。「自動車は、エンジンも大切だがブレーキが最も重要だ」と。つまりは、優れたブレーキがあってこそのエンジンということであり、優れたエンジンを開発するならば、まずは優れたブレーキを開発することがエンジニアとしての務め(=見せ所)だというわけである。
しかし、現在の多くの経済学者さんは、この一番の見せ所を無視し、なんの変哲もないデフレ下の中で胡坐をかき、財政破綻論だけを叫び続けながら私腹を肥やし、日本社会にとってなんら有益な情報をも流さないのだから、全くもって困ったものである。
しかも、経済に詳しい財政破綻論者はこのように指摘する。「MMT理論にはインフレ後の景気対策が盛り込まれておらず、無責任だ!」みたいなお馬鹿さんな事をいうのだから、本当に呆れてしまう。
確かに、MMTの経済的理論の中身には、こうした技術系のことにはほとんど触れられていない。というよりも、技術系に関していえば、日本と英国、日本と独国など、それぞれにそれぞれの特色や事情も異なってくるわけだから、明確な景気対策論を盛り込まないのは当然のことである。
よって、実際に景気が上昇し、物価上昇率が2%に達成した段階において、様々な統計をもとに景気対策を研究し論ずるのが、本来あるべき経済学者の姿ではないのか。
尚、現在のわが国の景気状況を考えた場合、デフレがさらに進んだことで、個人所得も消費者指数も落ち込みが激しいわけで、これら景気状況を改善するためには、何といっても日本政府による大幅な財政支出と大胆な減税を早急に実施することにある。また、インフレ傾向としては、そのことによって、あらゆる経済活動が活性化されていく。
無駄な議論や論調よりも、まずは何を為すべきなのか、財務省やその他の政府機関には、真剣に考えていただきものだ。
ちなみに、自国通貨が発行できる国家で、財政破綻した国家は過去に一度も存在していないことも合わせて述べておく。