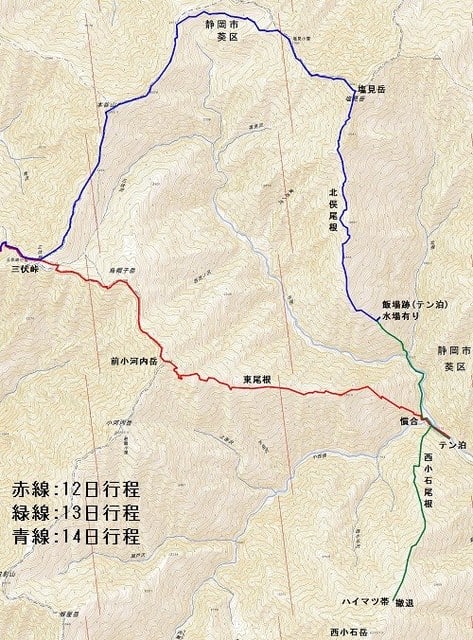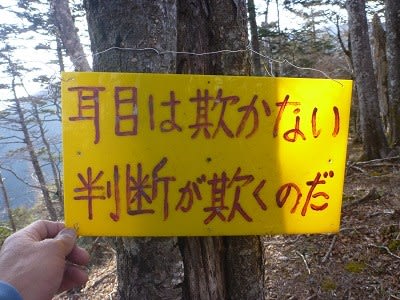山行日:2017年8月26日(土)~27日(日)
天気:26日雨のち晴れ 27日晴れ
山行者:単独です。
CT:
26日 飛越新道登山口6:13…1842分岐点7:45…寺地山8:38…北ノ俣岳11:03…赤木岳11:50…
黒部五郎岳13:48~14:11…黒部五郎小舎15:34…テント設営完了16:04
27日 黒部五郎小舎4:56…黒部五郎岳6:46…北ノ俣岳9:45…寺地山11:44…1842分岐点12:29…
飛越新道登山口13:59
2年前にも飛越新道登山口から黒部五郎岳へ登りに行っている。
その時は北ノ俣岳でまさかの呼び出しをくらって引き返した。
今回はそのリベンジ。
≪26日≫
登山口に着いた時はまだ雨。
予報では六時頃雨上がり回復するとのこと。
6時過ぎ、予報通り雨上がり晴れ間が見えてきたので出発する。
朝方まで余程降ったのだろう、登山道がまるで川のようになっている。
寺地山を過ぎ木道が出てくるまではヌタ場多し、
木道がある辺りは池糖が点在する感じのいいところ。
木道が終わると大きくえぐられた道、最後はまともな道が稜線へと続く、
稜線で太郎平からの道と合流し少しで北ノ俣岳。ここへは2年前に来ている、
ここから先は未踏の地、登ったり下ったりの道で奥には黒部五郎岳が待ち構えている。
晴れてはいるが稜線は風が強く寒い、カッパは朝から着込んだまま、
赤木岳を過ぎた辺りで日差しが多くなり風も弱まり暖かくなってきたのでカッパを脱いだ。
登山道から見える景色は絶景で時おり足を止めてしまう。
赤木平辺りはなだらかで池糖もありペポーニだ。
黒部五郎岳への登りはジグザクの急登、一旦肩に出て最後の一登りで山頂。
念願の黒部五郎岳は感無量、ここから見える景色は贅沢の極みだ。
今夜の幕営地黒部五郎小舎はまだ遥か遠く、
面倒くさいのでそこら辺でビバークしようかと思うが水がないので向かうことにする。
黒部五郎岳のカールの中を下っていく。
影にはまだたくさんの雪渓がありそこから川が流れている。
幾つも渡渉して下っていく、ゴーロ地形なので石が多く足に負担がかかる。
もうそこら辺でビバークしようかと思いつつも頑張り歩く。
ほうほうの体で小屋に到着、手続き済ませ、テントを張った。
小屋前で冷やされていたリンゴを買った。
適度に冷えて食べごたえがあった。
テントに戻り、笠ヶ岳を見ながらビールで乾杯。こ
の時間帯でもいい天気、大陸性高気圧に覆われているのだろうか、
空を見ると筋雲にウロコ雲、空はすっかり秋模様だ。
翌日朝方に東の空にオリオンが見えた。着実に夏から秋、そして冬へと向かっている。
≪27日≫
今日は昨日の逆の行程。
テント場を出発ししばらくしたところで日の出。
後ろからやってきた単独男性と飛越新道分岐まで御一緒するになった。
一人だと長い道のりも二人だと会話も弾み苦にならない。
楽しいひと時を過ごしあっという間に飛越新道分岐、またどこかでと言葉を交わし別れた。
避難小屋から少し進んだ右手の藪の中、大きな黒い生き物。
僕の存在に気付き藪の中をものすごい勢いで奥へと走り去って行った。
あれは…熊?
往路もヌタ場に悪戦苦闘しつつもなんとか登山口に到着。
温泉により汗を流し、途中で渋滞に巻き込まれつつも20時に自宅に到着。
ザックをガソゴソやったらヘッドライトが見つからない。
どうやら山にお供えしてしまったようだOTZ
2日間ともよく晴れてくれてサイコーの山旅でした。

(まずは北ノ俣岳グー)

(振り返ると薬師岳がこんにちは)

(水晶岳もこんにちは)

(遠くに白馬、唐松、五竜辺り)

(北ノ俣からの稜線と薬師岳)

(目の前黒部五郎岳)

(山頂直下でライチョウさんとこんにちは)

(リベンジ成功)

(山頂からの槍様)

(薬師岳と黒部五郎小舎)

(テント場からの笠ヶ岳)

(27日もいい天気に恵まれました)
天気:26日雨のち晴れ 27日晴れ
山行者:単独です。
CT:
26日 飛越新道登山口6:13…1842分岐点7:45…寺地山8:38…北ノ俣岳11:03…赤木岳11:50…
黒部五郎岳13:48~14:11…黒部五郎小舎15:34…テント設営完了16:04
27日 黒部五郎小舎4:56…黒部五郎岳6:46…北ノ俣岳9:45…寺地山11:44…1842分岐点12:29…
飛越新道登山口13:59
2年前にも飛越新道登山口から黒部五郎岳へ登りに行っている。
その時は北ノ俣岳でまさかの呼び出しをくらって引き返した。
今回はそのリベンジ。
≪26日≫
登山口に着いた時はまだ雨。
予報では六時頃雨上がり回復するとのこと。
6時過ぎ、予報通り雨上がり晴れ間が見えてきたので出発する。
朝方まで余程降ったのだろう、登山道がまるで川のようになっている。
寺地山を過ぎ木道が出てくるまではヌタ場多し、
木道がある辺りは池糖が点在する感じのいいところ。
木道が終わると大きくえぐられた道、最後はまともな道が稜線へと続く、
稜線で太郎平からの道と合流し少しで北ノ俣岳。ここへは2年前に来ている、
ここから先は未踏の地、登ったり下ったりの道で奥には黒部五郎岳が待ち構えている。
晴れてはいるが稜線は風が強く寒い、カッパは朝から着込んだまま、
赤木岳を過ぎた辺りで日差しが多くなり風も弱まり暖かくなってきたのでカッパを脱いだ。
登山道から見える景色は絶景で時おり足を止めてしまう。
赤木平辺りはなだらかで池糖もありペポーニだ。
黒部五郎岳への登りはジグザクの急登、一旦肩に出て最後の一登りで山頂。
念願の黒部五郎岳は感無量、ここから見える景色は贅沢の極みだ。
今夜の幕営地黒部五郎小舎はまだ遥か遠く、
面倒くさいのでそこら辺でビバークしようかと思うが水がないので向かうことにする。
黒部五郎岳のカールの中を下っていく。
影にはまだたくさんの雪渓がありそこから川が流れている。
幾つも渡渉して下っていく、ゴーロ地形なので石が多く足に負担がかかる。
もうそこら辺でビバークしようかと思いつつも頑張り歩く。
ほうほうの体で小屋に到着、手続き済ませ、テントを張った。
小屋前で冷やされていたリンゴを買った。
適度に冷えて食べごたえがあった。
テントに戻り、笠ヶ岳を見ながらビールで乾杯。こ
の時間帯でもいい天気、大陸性高気圧に覆われているのだろうか、
空を見ると筋雲にウロコ雲、空はすっかり秋模様だ。
翌日朝方に東の空にオリオンが見えた。着実に夏から秋、そして冬へと向かっている。
≪27日≫
今日は昨日の逆の行程。
テント場を出発ししばらくしたところで日の出。
後ろからやってきた単独男性と飛越新道分岐まで御一緒するになった。
一人だと長い道のりも二人だと会話も弾み苦にならない。
楽しいひと時を過ごしあっという間に飛越新道分岐、またどこかでと言葉を交わし別れた。
避難小屋から少し進んだ右手の藪の中、大きな黒い生き物。
僕の存在に気付き藪の中をものすごい勢いで奥へと走り去って行った。
あれは…熊?
往路もヌタ場に悪戦苦闘しつつもなんとか登山口に到着。
温泉により汗を流し、途中で渋滞に巻き込まれつつも20時に自宅に到着。
ザックをガソゴソやったらヘッドライトが見つからない。
どうやら山にお供えしてしまったようだOTZ
2日間ともよく晴れてくれてサイコーの山旅でした。

(まずは北ノ俣岳グー)

(振り返ると薬師岳がこんにちは)

(水晶岳もこんにちは)

(遠くに白馬、唐松、五竜辺り)

(北ノ俣からの稜線と薬師岳)

(目の前黒部五郎岳)

(山頂直下でライチョウさんとこんにちは)

(リベンジ成功)

(山頂からの槍様)

(薬師岳と黒部五郎小舎)

(テント場からの笠ヶ岳)

(27日もいい天気に恵まれました)