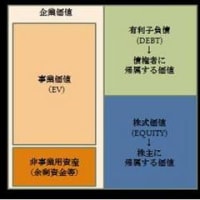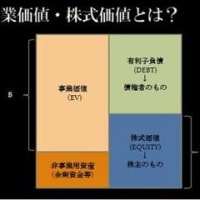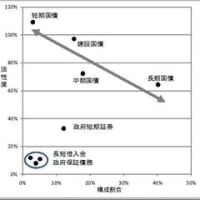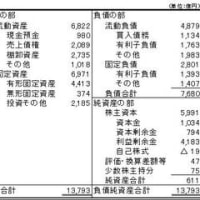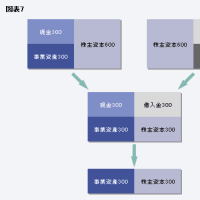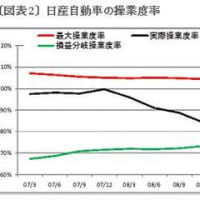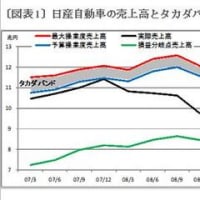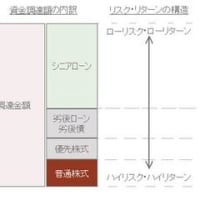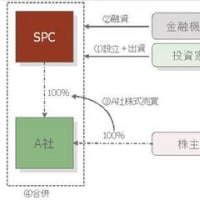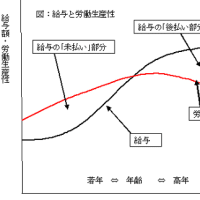[東京 19日 ロイター] トヨタファイナンシャルサービス・エグゼクティブバイスプレジデントで元日銀理事(国際担当)の平野英治氏は19日、ロイターのインタビューに応じ、日本経済は年後半以降、世界経済が回復テンポを強めるにつれ輸出中心に持ち直しの動きを強めると見通し、今後の金融政策について、追加緩和の必要性はないとの認識を示した。
日銀はデフレと闘う姿勢を明確にしているが、量的緩和政策に踏み込んだからといってデフレ脱却できるとも思っていないと指摘。重要なことは、今の金融緩和を断固継続することによって回復シナリオをより確かにし需給ギャップ圧力を解消させることだと語った。
インタビューの概要は以下の通り。
──国際金融の今年のテーマは。
「信用バブル崩壊後の後始末が十分終わったとは言えない。米欧のバランスシート調整問題がひとつ。第二が金融危機克服の過程でどの国も公的債務を累増させてしまった。財政赤字への対応を誤れば、潜在的な国際金融市場の火種ともなりかねない。クレディブルな財政再建の展望を、日本も含めできるかどうか。第三が人民元を含む世界的な不均衡問題と為替の問題。先進国の緩和効果が新興市場国の経済を大きく支える循環になった。そのなかで中国では景気過熱への懸念が出始め、引き締め気味の政策運営になり始めている。それと整合的な為替が新興国通貨の切り上げだがどうなるかだ」
──世界的な不均衡是正問題では人民元改革を求める声強まるか。
「中国当局は人民元問題を内政問題と位置づけている。彼ら自身がその気にならないと動かない。一方で、当局は経済の過熱のリスクを意識し始めている。人民元を弾力化して切り上げる(方向)が政策的には正しいと考えるが、世界経済がまだぜい弱ななか、中国といえども輸出セクターにはまだ心配がある。これをどう判断するかだ。今までの中国のやり方をみると、追い込まれた形での切り上げは好まない。独自の判断として、景気の過熱状況をどの程度シリアスにみるかだ。国内経済が過熱に懸念を示しており、大きな流れとしては弾力化の方向に向かっていることは間違いない」
──先進国の金融政策の変化が日本経済に及ぼす影響は。
「米国経済はバランスシート問題抱えまだ磐石とは言えないが、着実な回復の足取りを続けている。今年後半から来年にかけて持ち直しのテンポは若干強くなると思っている。今年の後半には、市場は米利上げのタイミングの意識を高めると予想されている。日米金利差と金利差の裏にある景気格差、それを反映して為替は円安方向に動く可能性が高い。これは日米の景気物価格差を素直に反映した展開といえる」
──日本経済にとっては好ましいことか。
「海外経済に比べ、日本経済の立ち直りは鈍い。内需の自立回復力はぜい弱で、海外経済頼みが日本の姿であるとすると、円安、円高の修正は日本経済にとってはプラスだ。ただ、中長期的には日本がかかえる最大の問題は財政赤字で、日本経済の大きな障害になる。対応を誤ると、いまのところ国債を増発しても長期金利は跳ね上がらず消化できているがそう長くは続かないだろう。どこかで長期金利は跳ね上がり、為替円安になり、株売られると、大きなトリプル安リスクを潜在的に抱えている。これとは違う景気格差・金利格差を素直に反映した円高の修正は、日本経済を支えるひとつのファクターになる」
──日本経済の展望は。
「世界経済は米国中心に年後半から回復を高める。中国初めとする新興国が高水準の成長を続ける。そのシナリオのなかで、日本経済は年央にかけて政策効果が財政の息切れリスクもあり中だるみが続くにしても、年後半以降、来年にかけて世界経済が回復テンポを強めるにつれ、日本経済も輸出中心に持ち直しのテンポを強めるだろう」
──追加緩和の必要はないか。
「そういうシナリオのなかでは(追加金融緩和の必要は)ない。デフレをどうするかという問題は常にある。日銀もデフレと闘うとの姿勢を明確にしている。ただ、金融政策で踏み込んで量的緩和をやったからといってデフレ脱却できるとも思っていない」
「デフレについては金融システムの安定性を確保する必要はある。その限りにおいて、今のデフレ自体を過度に恐れる必要はない。大事なことは日本銀行が緩和を断固継続することによって、海外経済にあわせた形での緩やかな回復シナリオをより確かにしていくこと。そのことによって需給ギャップ、デフレ圧力を解消していく。これが正しい対応ではないか」
──需給ギャップが大きいだけにデフレが長引くのではないか。
「デフレの前回ピークである2001年の需給ギャップは4%程度だった。今はマイナス7%程度で当時と比べて非常に大きく簡単には埋まらない。しかし、息の長い回復に向けて徐々に解消していくしかない。重要なのは、企業にしろ、家計にしろ、先行きに対する期待・自信が深まらなければ支出しない。政府の政策を含め成長期待を後押しする環境づくりが大事だが、まだ展望がみえない。今の政治の混乱は日本経済にっとっては痛い」
──日銀は今回はデフレと認定して政策対応した。前回との違いは。
「コミュニケーションを考えたということではないか。2000年、2001年と比べると、需給ギャップを起点とする物価の下落テンポは今のほうが大きい。しかも継続的に向こう何年も続くと考えざる得ない。(従来)デフレという言葉を避けたのは、定義が多岐にわたり曖昧だったからだ。当時、曖昧な言葉を使うのは政策運営を不透明にしかねないという議論があった」
「いまは、日本銀行が(デフレの定義が)不正確だといって(認定することを)避けることが、日本銀行が日銀の使命である『物価の安定』という目標から逃げているという印象を与えかねないというリスクを感じたからだろう」
──物価下落をより深刻に受け止めながら、緩和の維持でよいのか。
「認識が深刻というより、金融システムをめぐる環境が違う。今、物価のマイナスの程度は大きいが、総じて比べると金融システムの安定度は高い。根っこには、マネーを出せばどうにかなるというものでもない。経済の成長期待に働きかけることが本筋だ。緩和的な金融環境を断固維持するしかない。そして金融システムの安定を守る。これ以外にない」
──政策手段として、将来、日銀による国債引き受け増額の余地は。
「中期的な財政再建計画がきちんと出されることが重要で、そういうものがきちんとない形で国債を増発し続けると悪い金利上昇はあり得る。そういう状況になれば、苦し紛れに、日銀に国債買い入れ増額を求める声が強まるだろう。それはリスクだ」
「しかし、いま政府はオーソドックスに対応しようとしており、そのプレッシャーが高まるとは思わない。日銀が引き受けなくとも、家計の貯蓄率は下げ止まり感があり企業の貯蓄余剰も大きい。国債が少々増発されてもマクロ的には吸収できる。政府が中期的な財政再建計画を作る状況からみて、直ちに、日銀に国債買い増しプレッシャーがあるとはみない」
──政府が成長戦略の基本方針を出した。
「肉付けがまだなので評価は難しいが、成長戦略を出そうという方向にカジをきったことは評価できる」
──政治状況に危機感をもつ理由は。
「日本の抱える大きな問題として財政赤字と少子高齢化があるが、国民的コンセンサスを踏まえた息の長い政策を打っていかなければ簡単にこの問題を乗り越えることはできない。これまでは、日本経済は政治が何かあったとしても、民間の力で頑張ってきた。いま初めて、政治による方向づけや政策誘導が必要な局面になっている。海外では官と民が一体となって『大競争力時代』を勝ち抜こうという戦略を立てている。日本は、いまのところ民間の片肺みたいな状況。政府がビジョンを示し、政策誘導すべきところは誘導し、税の体系を考え、緩和すべきところは規制緩和する。今こそ、政府がビジョンと政策のフレイムワークを示すことによって企業が本来の力を発揮できる環境を作ることが求められている。しかし、今のところその期待に応えるものは出ていない」
──鳩山政権下での日米同盟のきしみが日米経済関係に与える影響はないか。
「まだ、普天間問題もペンタゴンにとどまっている。日米関係がさらに冷え込み、あるいは不信感が高まると、経済関係にも良いはずがない。そのマグマはたまってきている」
──G7の役割について。非公開色を強めており声明発出取りやめ観測もある。
「声明が出ようが出まいが、重要度は変わらない。G7のなかで国際金融の問題を話し合い対処してきた蓄積がある。問題はG7だけでは世界経済も十分カバーできない。中国はじめとする新興市場国を含めた国際的枠組みを考え問題への対応を考えていかなければいけないということは事実認識としてあるが、これまでの蓄積をベースに、G7がG20の議論をリードしていくかということが重要だ。G20といっても、G7で行われてきたような密度の高い議論が行えるかどうかについては疑問もある。いまが過渡期であるという状況では、G7が全体の議論を引っ張るのが自然な流れ」
「G7であれ、G20であれ、声明に意味があるなら出せばよい。会議があるから出さなければならないということでもないだろう。市場が荒れた場合には臨時に声明を出すこともあった。いわばメカニズムだ」
(ロイターニュース 吉川 裕子 木原 麗花)
日銀はデフレと闘う姿勢を明確にしているが、量的緩和政策に踏み込んだからといってデフレ脱却できるとも思っていないと指摘。重要なことは、今の金融緩和を断固継続することによって回復シナリオをより確かにし需給ギャップ圧力を解消させることだと語った。
インタビューの概要は以下の通り。
──国際金融の今年のテーマは。
「信用バブル崩壊後の後始末が十分終わったとは言えない。米欧のバランスシート調整問題がひとつ。第二が金融危機克服の過程でどの国も公的債務を累増させてしまった。財政赤字への対応を誤れば、潜在的な国際金融市場の火種ともなりかねない。クレディブルな財政再建の展望を、日本も含めできるかどうか。第三が人民元を含む世界的な不均衡問題と為替の問題。先進国の緩和効果が新興市場国の経済を大きく支える循環になった。そのなかで中国では景気過熱への懸念が出始め、引き締め気味の政策運営になり始めている。それと整合的な為替が新興国通貨の切り上げだがどうなるかだ」
──世界的な不均衡是正問題では人民元改革を求める声強まるか。
「中国当局は人民元問題を内政問題と位置づけている。彼ら自身がその気にならないと動かない。一方で、当局は経済の過熱のリスクを意識し始めている。人民元を弾力化して切り上げる(方向)が政策的には正しいと考えるが、世界経済がまだぜい弱ななか、中国といえども輸出セクターにはまだ心配がある。これをどう判断するかだ。今までの中国のやり方をみると、追い込まれた形での切り上げは好まない。独自の判断として、景気の過熱状況をどの程度シリアスにみるかだ。国内経済が過熱に懸念を示しており、大きな流れとしては弾力化の方向に向かっていることは間違いない」
──先進国の金融政策の変化が日本経済に及ぼす影響は。
「米国経済はバランスシート問題抱えまだ磐石とは言えないが、着実な回復の足取りを続けている。今年後半から来年にかけて持ち直しのテンポは若干強くなると思っている。今年の後半には、市場は米利上げのタイミングの意識を高めると予想されている。日米金利差と金利差の裏にある景気格差、それを反映して為替は円安方向に動く可能性が高い。これは日米の景気物価格差を素直に反映した展開といえる」
──日本経済にとっては好ましいことか。
「海外経済に比べ、日本経済の立ち直りは鈍い。内需の自立回復力はぜい弱で、海外経済頼みが日本の姿であるとすると、円安、円高の修正は日本経済にとってはプラスだ。ただ、中長期的には日本がかかえる最大の問題は財政赤字で、日本経済の大きな障害になる。対応を誤ると、いまのところ国債を増発しても長期金利は跳ね上がらず消化できているがそう長くは続かないだろう。どこかで長期金利は跳ね上がり、為替円安になり、株売られると、大きなトリプル安リスクを潜在的に抱えている。これとは違う景気格差・金利格差を素直に反映した円高の修正は、日本経済を支えるひとつのファクターになる」
──日本経済の展望は。
「世界経済は米国中心に年後半から回復を高める。中国初めとする新興国が高水準の成長を続ける。そのシナリオのなかで、日本経済は年央にかけて政策効果が財政の息切れリスクもあり中だるみが続くにしても、年後半以降、来年にかけて世界経済が回復テンポを強めるにつれ、日本経済も輸出中心に持ち直しのテンポを強めるだろう」
──追加緩和の必要はないか。
「そういうシナリオのなかでは(追加金融緩和の必要は)ない。デフレをどうするかという問題は常にある。日銀もデフレと闘うとの姿勢を明確にしている。ただ、金融政策で踏み込んで量的緩和をやったからといってデフレ脱却できるとも思っていない」
「デフレについては金融システムの安定性を確保する必要はある。その限りにおいて、今のデフレ自体を過度に恐れる必要はない。大事なことは日本銀行が緩和を断固継続することによって、海外経済にあわせた形での緩やかな回復シナリオをより確かにしていくこと。そのことによって需給ギャップ、デフレ圧力を解消していく。これが正しい対応ではないか」
──需給ギャップが大きいだけにデフレが長引くのではないか。
「デフレの前回ピークである2001年の需給ギャップは4%程度だった。今はマイナス7%程度で当時と比べて非常に大きく簡単には埋まらない。しかし、息の長い回復に向けて徐々に解消していくしかない。重要なのは、企業にしろ、家計にしろ、先行きに対する期待・自信が深まらなければ支出しない。政府の政策を含め成長期待を後押しする環境づくりが大事だが、まだ展望がみえない。今の政治の混乱は日本経済にっとっては痛い」
──日銀は今回はデフレと認定して政策対応した。前回との違いは。
「コミュニケーションを考えたということではないか。2000年、2001年と比べると、需給ギャップを起点とする物価の下落テンポは今のほうが大きい。しかも継続的に向こう何年も続くと考えざる得ない。(従来)デフレという言葉を避けたのは、定義が多岐にわたり曖昧だったからだ。当時、曖昧な言葉を使うのは政策運営を不透明にしかねないという議論があった」
「いまは、日本銀行が(デフレの定義が)不正確だといって(認定することを)避けることが、日本銀行が日銀の使命である『物価の安定』という目標から逃げているという印象を与えかねないというリスクを感じたからだろう」
──物価下落をより深刻に受け止めながら、緩和の維持でよいのか。
「認識が深刻というより、金融システムをめぐる環境が違う。今、物価のマイナスの程度は大きいが、総じて比べると金融システムの安定度は高い。根っこには、マネーを出せばどうにかなるというものでもない。経済の成長期待に働きかけることが本筋だ。緩和的な金融環境を断固維持するしかない。そして金融システムの安定を守る。これ以外にない」
──政策手段として、将来、日銀による国債引き受け増額の余地は。
「中期的な財政再建計画がきちんと出されることが重要で、そういうものがきちんとない形で国債を増発し続けると悪い金利上昇はあり得る。そういう状況になれば、苦し紛れに、日銀に国債買い入れ増額を求める声が強まるだろう。それはリスクだ」
「しかし、いま政府はオーソドックスに対応しようとしており、そのプレッシャーが高まるとは思わない。日銀が引き受けなくとも、家計の貯蓄率は下げ止まり感があり企業の貯蓄余剰も大きい。国債が少々増発されてもマクロ的には吸収できる。政府が中期的な財政再建計画を作る状況からみて、直ちに、日銀に国債買い増しプレッシャーがあるとはみない」
──政府が成長戦略の基本方針を出した。
「肉付けがまだなので評価は難しいが、成長戦略を出そうという方向にカジをきったことは評価できる」
──政治状況に危機感をもつ理由は。
「日本の抱える大きな問題として財政赤字と少子高齢化があるが、国民的コンセンサスを踏まえた息の長い政策を打っていかなければ簡単にこの問題を乗り越えることはできない。これまでは、日本経済は政治が何かあったとしても、民間の力で頑張ってきた。いま初めて、政治による方向づけや政策誘導が必要な局面になっている。海外では官と民が一体となって『大競争力時代』を勝ち抜こうという戦略を立てている。日本は、いまのところ民間の片肺みたいな状況。政府がビジョンを示し、政策誘導すべきところは誘導し、税の体系を考え、緩和すべきところは規制緩和する。今こそ、政府がビジョンと政策のフレイムワークを示すことによって企業が本来の力を発揮できる環境を作ることが求められている。しかし、今のところその期待に応えるものは出ていない」
──鳩山政権下での日米同盟のきしみが日米経済関係に与える影響はないか。
「まだ、普天間問題もペンタゴンにとどまっている。日米関係がさらに冷え込み、あるいは不信感が高まると、経済関係にも良いはずがない。そのマグマはたまってきている」
──G7の役割について。非公開色を強めており声明発出取りやめ観測もある。
「声明が出ようが出まいが、重要度は変わらない。G7のなかで国際金融の問題を話し合い対処してきた蓄積がある。問題はG7だけでは世界経済も十分カバーできない。中国はじめとする新興市場国を含めた国際的枠組みを考え問題への対応を考えていかなければいけないということは事実認識としてあるが、これまでの蓄積をベースに、G7がG20の議論をリードしていくかということが重要だ。G20といっても、G7で行われてきたような密度の高い議論が行えるかどうかについては疑問もある。いまが過渡期であるという状況では、G7が全体の議論を引っ張るのが自然な流れ」
「G7であれ、G20であれ、声明に意味があるなら出せばよい。会議があるから出さなければならないということでもないだろう。市場が荒れた場合には臨時に声明を出すこともあった。いわばメカニズムだ」
(ロイターニュース 吉川 裕子 木原 麗花)