

櫛ケ浜駅は複線平面交差の駅、岩徳線の分岐駅で広い構内を持ちます。岩徳線のホームがあり、既に駅構内からカーブして、駅を出る頃には完全に別れています。場所は山口県周南市大字久米字院内にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅です。駅を出るとすぐ国道、駅前には競艇場があります。徳山駅方面を見ますと、石油化学コンビナートが見えます。

徳山地域鉄道部が管理し、ジェイアール西日本広島メンテックが駅業務を受託する業務委託駅である。窓口ではPOS端末による発券を行うが、土休日は無人になる。

利用可能な鉄道路線 は 西日本旅客鉄道 山陽本線 - 櫛ケ浜駅の所属線。
岩徳線 - 線路名称上では櫛ケ浜駅が終着駅であるが、運転系統上、列車は全て徳山駅まで乗り入れる。そのため、当駅止まりの列車は設定されていません。

駅は単式1面・島式2面の合計3面4線(5線に見えるが、山陽本線上りプラットホームの待避線に見える線路は上り方で行き止まりになる保守用)のホームを持つ地上駅。駅舎はコンクリートの平屋駅舎です。

山陽本線の列車は駅舎側の単式ホーム(1番のりば)と島式1面(2番のりば、その反対側の1線は上述のとおり保守用のため番線カウントにも含まれない)を、岩徳線の列車は島式1面(3・4番のりば)を使用する。なお、岩徳線は単線であるため、当駅が交換駅としての役割も担っている。各ホームは跨線橋で連絡している。

跨線橋に書かれた駅名

のりばは駅舎側から以下の通り。
1■山陽本線下り 徳山・防府方面 単式
2■山陽本線上り 柳井・岩国方面 島式
3■岩徳線 下り 徳山行き 島式
4■岩徳線 上り 周防高森・玖珂方面島式
なお、列車運転取り扱い上では、2番のりばの反対側の使われていない線路を「3番線」とするため、岩徳線の3・4番のりばが「4番線」「5番線」とされている。

1928年(昭和3年)2月11日 - 国有鉄道山陽本線の下松駅 - 徳山駅間に新設開業。旅客・貨物の取扱を開始。
1932年(昭和7年)5月29日 - 岩徳西線(現在の岩徳線)が周防花岡駅まで開業し分岐駅となる。
1934年(昭和9年)12月1日 - 山陽本線の麻里布駅(現在の岩国駅) - 櫛ケ浜駅間が、それまでの岩徳西線を含む周防花岡駅経由のルートに変更され、以前の柳井駅経由のルートは柳井線に改称される。
1944年(昭和19年)10月11日 - 線路名称改定。山陽本線の麻里布駅(現在の岩国駅) - 櫛ケ浜駅間はそれまでの柳井駅経由に戻され、周防花岡駅経由のルートは岩徳線に改称。
1962年(昭和37年)9月1日 - 貨物の取扱を廃止。
1968年(昭和43年)3月7日 - 当駅を通過する上り特急「つばめ」が構内ポイント切替ミスより岩徳線へ進入。救援機関車により山陽本線に引き戻す。
1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅となる。
電報略号 クシ
駅構造 地上駅
ホーム 3面5線
乗車人員 -統計年度-877人/日(降車客含まず) -2009年-
開業年月日 1928年(昭和3年)2月11日
備考 業務委託駅 POS端末設置
* 全列車が徳山駅まで乗り入れ










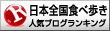


















午後に入ってから撮影したのでしょうか。
画像を見ると、4両編成の列車の先頭部分が映っていましたが、
車内は座席が埋まっていなかったのでしょうかね。
山口県内の山陽線では、
真っ昼間でも、4両編成の列車が結構走っていますが、
山口県の岩国~下関間では、
4両編成にするほどの輸送需要が、
朝を除けば、どうも全般に引き合っていないのではとでも思うのですが・・・
下関に配置されて山口県内の運用に就いている117系に加えて、
現在、岡山に配置されている117系を下関に配置替えして、
大阪寄りのクハ117の運転台部分を切断してモハに接合してクモハ化するやり方で3両編成にするというアイディアも考えられるのですが・・・・
広島県内~山口県の柳井、徳山、山口、下関間を直通する列車が、
現在のダイヤでは、下り20本、上り16本ありますが、
広島と下関の2つの車両基地に配属されている115系4両編成の入り組んだ広域運用の見直しや、
岩国駅を素通りする乗客があまり多くない?実情などを踏まえ、
1~2年先のダイヤ改正で、そうした列車が、
岩国で終日完全分離されるのではないのかと、私は思っているのですが…
この画像を見ると、櫛ヶ浜駅の階段に、
「広島往復格安きっぷ」のPR看板が付いているのを確認しましたが、
これは、山口県内向けの広島への新幹線利用が前提らしくて、
在来線の山陽線で、新山口や徳山~広島駅まで直通する利用客は、今でもそう多くないというのが実情なのでしょうね???