
ワム80000形は、日本国有鉄道(国鉄)が1960年(昭和35年)から製造、使用した、15t積み二軸有蓋貨車である。国鉄貨車の標準型として、1981年(昭和56年)までの21年間で、実に26,605両が量産された。製造所は、日本車輌製造、川崎車輛/川崎重工業、汽車製造東京支店、日立製作所、輸送機工業、富士車輌、ナニワ工機、三菱重工業、協三工業、舞鶴重工業、鉄道車輛工業、若松車輛である。かつては全国各地で見ることのできた貨車で、ワムハチの愛称で知られる。

1959年(昭和34年)、汐留駅 - 梅田駅間においてコンテナ輸送が始まった。一方でそれまで主流であった車扱貨物、特に有蓋車の荷役作業の近代化をはかる必要がでてきた。このためパレットを使用し、フォークリフトで荷役をすることによる効率化が検討され、初代ワム80000形(後の初代ワム89000形)が誕生した。本形式はその改良量産型である。車体色はとび色2号(明るい茶色)。

最大積載荷重は15tであるが、これはパレットの重量を含んだものである。本形式の試作車にあたる初代ワム80000形は、容積が過小で15トンを積載することができなかったため、本形式では容積を大きくして、同荷重の他形式と比べ車体長が増加している。また、初代ワム80000形同様、荷役の利便を図るため側面は総開き式として4枚の引戸とされ、どの場所でも開口させて荷役を行うことができる。積載可能なパレット数は、初代ワム80000形より2枚多い14枚である。
走り装置は二段リンク式で、最高運転速度は75km/h、車軸は12t長軸で、軸受は平軸受である。
標記トン数15tのパレット荷役用有蓋車であることから車番標記の前に「パ」(後年「ハ」に変更)の小文字が入れられたため「パワム(ハワム)」と区別される。パレット輸送の利点を生かし主に大口輸送に使用されたため、1984年(昭和59年)2月のダイヤ改正で、ヤード集結形輸送が廃止された後も、製紙業者による紙の輸送用に生き残った。1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道(JR貨物)のほか、九州旅客鉄道(JR九州)を除く旅客鉄道会社にも少数が事業用として引き継がれた。
JR貨物に引き継がれたものの一部は、軸受をコロ軸受にする改造(380000番台)や製紙原料用の木材チップバラ積み用(480000番台)へと改造されたが、輸送自体の廃止やコンテナ車への切り替えにより消滅した。
廃車体の駅舎への転用例(JR北海道 函館本線尾白内駅)
廃車となった車両の一部は、使い勝手の良さから数多くが一般に払い下げられた上で倉庫や店舗などに再利用された。今でも全国各地でその姿を見ることができる(淡路島など鉄道がない地域にもある)。また、廃車体が駅舎として転用された例もあるが、既に建て替えられたところもある(香取駅、伊勢柏崎駅など)。

走行安定対策車(ワム280000 - ワム288499・280000番台)
1975年(昭和50年)より製造された改良型で、1981年までに8,500両が製造された。走行性能の改善のため軸距を260mm延長して5,300mmとし、床鋼板の厚みが4.5mmから6mmに変更となったほか、台枠構造が変更されている。軽量化のための引戸のアルミ化などが行われている。外観上では雨樋縦管が車端部に露出しており、屋根は耐候性高張力鋼1.6mm厚となり、耐食性ポリエステル樹脂を塗布したため、塗色が薄茶色になった。側扉がアルミ製となったことにより強度が小さくなり、注意喚起の意味で「●」印が扉に標記されたものの破損事故が多発したため、さらにその下部に縦書きで「アルミドア」の表示が追加された。
1978年第1次債務負担で新製されたワム284990 - 284999の10両は、木製床を試用しており、日本車輌製造製の5両(ワム284990 - 284994)は合板を、三菱重工業製の5両(ワム284995 - 284999)は単板を使用している。また、1978年本予算以降の新製車の一部は、輪軸や軸ばね、制動弁、自動連結器に中古品を使用したものがある。
2006年(平成18年)現在、使用されている本形式は、全て本番台または本番台の改造車である。
国鉄分割民営化後
26,000両以上が製造された本形式であるが、1984年2月のダイヤ改正でヤード集結輸送が原則廃止されたため大量の余剰車が発生した。余剰車は他の不要車両とともに操車場跡地に留置され、うち相当数が車軸を撤去して民間に売却され、各地で倉庫等に利用されることとなった。
1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化時には、日本貨物鉄道(JR貨物)および旅客5社に6,632両が承継された。これは本形式総製作数の4分の1弱である。内訳は、北海道旅客鉄道(JR北海道)6両、東日本旅客鉄道(JR東日本)13両、東海旅客鉄道(JR東海)8両、西日本旅客鉄道(JR西日本)19両、四国旅客鉄道(JR四国)1両、JR貨物6,588両である。走行安定性対策車(280000番台)が承継車の多数を占め、ごく少数の2次量産車およびビール輸送用物資別適合車が含まれていた。旅客鉄道会社のものは配給車や救援車代用等の事業用、JR貨物のものは営業用であるが、一部は車両所の配給用である。配給車代用のものは、国鉄時代から車体に白帯を巻いて区別されているが、広島車両所のものは緑色一色に「SUPPLY LINE」のロゴを標記した塗装に変更された。また、民営化初期のJR貨物所有車では、JR貨物のコーポレートカラーであるコンテナブルーに、「パワー全開JR貨物」等のキャッチコピーを書いた車両も存在した。JR貨物での用途は、ロール紙を主体とする紙製品を輸送する専用貨物列車が主体であった。各地の製紙工場から大都市近傍の消費地に向けた多数の列車が設定されていたが、最高速度の制約ならびに本形式の老朽化にともなうコンテナ輸送への置換や、輸送需要自体の消滅によって運用は漸次減少し、2012年3月17日のダイヤ改正で全車運用を終了した。2010年4月1日現在の在籍数は、JR北海道1両(ワム281395)、JR東日本1両(ワム287336)、JR貨物401両で、JR発足時の10分の1以下となっている。

国鉄ワム80000形貨車
基本情報
車種 有蓋車
運用者 日本国有鉄道
日本貨物鉄道
北海道旅客鉄道
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
四国旅客鉄道
製造所 日本車輌製造、川崎車輛/川崎重工業、汽車製造東京支店、日立製作所、輸送機工業、富士車輌、ナニワ工機、三菱重工業、協三工業、舞鶴重工業、鉄道車輛工業、若松車輛
製造年 1960年 - 1981年
製造数 26,605両
運用終了 2012年3月17日
主要諸元
車体色 とび色2号、貨物ブルー、赤紫色(JRFレッド)他
軌間 1,067 mm
全長 9,650 mm
全幅 2,882 mm
全高 3,703 mm
荷重 15 t
実容積 52.8 m3
自重 11.3 t
換算両数 積車 2.2
換算両数 空車 1.0
走り装置 二段リンク式
軸距 5,300 mm
最高速度 75 km/h
*寸法関係は280000番台を示す










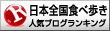


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます