
クハ381形 は国鉄381系電車、日本国有鉄道(国鉄)が1973年から1982年の間に設計・製造した振子式の直流特急形車両です。
最大4両給電の110kVA電動発電機 (MG) を搭載する制御車。定員60名。本形式は引通しが両渡りとなっており、奇数・偶数いずれの方向でも使用が可能。「しなの」用として製造された貫通扉付きの0番台が18両、「くろしお」「やくも」用として製造された非貫通形の100番台が44両あるとのこと。
0番台全車と100番台2両の20両がJR東海に、他の車両がJR西日本に承継された。0番台は2001年までに全て廃車され、現在1が「リニア・鉄道館」で保存・展示されています。

JR東海には「しなの」用として神領電車区に配置されていた88両が承継された。同区の車両は新造当初は長野運転所(長ナノ)に配置されたが、1982年11月15日のダイヤ改正で移管されました。民営化前後の1987年から1989年にかけてサロ381形は全て先頭車に改造された他、不足分はクハ381から改造され、長野向き先頭車は全てクロ381型に統一されました。

特急「しなの」車体は(1983年 / 東海道本線山崎付近)振子車両に必要とされる軽量化と低重心化を図った車体構造となっています。
車体は軽量化と振子作用を容易にするため、アルミニウム合金製構体となっています。前面形状は183系0番台車や485系200番台車などと同様、「電気釜」と呼ばれる形状です。また、貫通形と非貫通形があります。側面はグリーン車の窓や普通車の客用扉の数を除き183系に似ているが、振子作用による車両限界への抵触を防ぐため183系に比べて車体下部の裾絞りが大きい。台枠上面幅は2,600mmとなっています。また重心を下げるため、重量物である冷房装置は床下に設置しており、屋根上はパンタグラフなどの必要最小限の設置物がある程度で非常にすっきりしています。客室床面高さは181系とほぼ同じ1,105mm。屋根高さは3,385mmだが、天井は冷房ダクトを通した平天井構造のため、床面からの高さは2,050mmで181系よりも低い。また、国鉄の電車では初めて全長を新基準の21,300mmとしています。アルミ製車体だが外観は183系など他の昼行特急形電車と同様にクリーム4号地に赤2号帯が塗装されています。
本系列では振子装置を装備しており、これにより半径400mの曲線における通過速度は本則+20km/h(機関車牽引の高速貨物列車の制限速度より20km/h高い速度)で走行した場合の、乗客にかかる遠心力を軽減することができ、急カーブが続く路線のスピードアップに貢献しています。
本系列で使用されている振子装置はコロ軸支持式の自然振子装置です。これはカーブで生じる遠心力をコロにより伝達して車体を傾けるものです。しかしこの方式では、カーブでの遠心力がコロに伝わり車体を傾けるまでの間に時間差が生じてしまい、不自然な揺れを生じることに加え、カーブを走行中に一般の乗客には不慣れな縦方向の荷重が加わるという振り子式車両の特性もあり、乗り物酔いを起こす乗客が多発し、乗心地の面で問題が残ってしまいました。車掌が酔客のために酔い止め薬を常備していた逸話が残っています。
「くろしお」用の車両では制御振子の実験が行われました。また1985年11月26日に湖西線で行われた高速試験では179.5km/hを達成。これは現在に至るまで、日本における在来線の最高速度記録です。
JR移行後は自然振子式に比べて乗心地が良い制御付き自然振子式を使用する車両の導入が進められており、自然振子式は古い方式となっています。営業用電車で自然振子式の車両はこの381系のみです。
接客設備 は座席が、普通車が 910 mm 間隔の簡易リクライニングシート、グリーン車が 1,160 mm 間隔のリクライニングシートです。これは183系電車(基本番台)と同一の仕様である。最終製造の車両の普通車は、座席の背もたれにロックがかかるように改良されています。座席の端部には取手を設け、曲線通過時の立ち席客の安全に配慮しています。客室と出入口との仕切り扉は新幹線0系電車と同一のマットスイッチ式自動ドアを用いました。運転開始直後に乗物酔いが多発したことから、当初はエチケット袋が各座席に用意されました。これは本系列特有の装備品。しかし今でもエチケット袋は、「くろしお」の洗面台に用意されています。

窓の日除けはベネシャンブラインドを採用。これは591系の装備を踏襲したもので、開閉方式は591系の電動式から手動式に変更されています。これはJR西日本では後年の各種改装で一般的な横引きカーテンに換装され、最後まで維持していたJR東海も運用から退いたため、現存する装備ではない様子。
冷房装置はAU33形ユニットクーラーを床下に各車1台搭載し、冷風はダクトにより天井の吹出口から吹出す床下集中方式です。ダクトは各車両中央、左右二箇所の窓柱部の床から立ち上がっています。










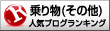



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます