
鉄道におけるパンタグラフとは、コイルばねの力や空気圧などによって架線に集電舟を押し付け、関節構造または伸縮構造を設けることで、架線高さの変化に追従させる形態の集電装置。近年架空電車線方式における集電装置としては最も一般的に使われている。略してパンタ、またはパンと呼ばれることが多い。

パンタグラフの構造は、大きく分けて4つの部分で構成されており、架線に直接に接触して摺動しながら架線の電力を取込むための集電舟、集電舟が自由に動きながら架線の追従性を良くするための集電舟支え装置、鋼板・アルミ合金・ステンレスパイプのリンクで構成された枠組、パンタグラフ全体を支えて車体に固定するための枠からなっており、集電舟の架線との摺動部分は摺板と呼ばれており、導電性の良く架線に損耗を与えにくいカーボンや銅合金などが使用され、摩耗による定期的な交換を必要とするため、それが容易にできるように、いくつかに分割された構造となっている。

その発明者が誰であったかについては、現在に至るまで明らかとはなっていないが、ボルチモア・アンド・オハイオ鉄道(Baltimore and Ohio Railroad)で1895年(明治25年)、電気機関車に先端に集電用台車を取り付けたひし形の集電装置を使用している[注釈 20]。アメリカ・サンフランシスコの対岸、オークランド周辺に路線網を形成していたキー・システム (en:Key System)[注釈 21] が1903年(明治36年)の開業時に既に菱枠形パンタグラフを装備した電車を就役させていたことが開業当日に撮影された写真で判明している。
「パンタグラフ」の語源は、製図やフライス加工などで、複製のために用いられる、リンク機構を持つ菱形をつなげた形の道具である、パンタグラフ (Pantograph) に動作が似ていたため採られた名称である。現在では必ずしも菱形のもののみを指すのではなく、他の形状のものも含め、関節構造を備えた屋根上に装備する集電装置の総称となっている。

菱形
菱形の最も古典的かつ一般的な構造のもので、その形状と動作が絵を拡大または縮小して描くことのできるパンタグラフ(写図器)に似ていたことから、このタイプの集電装置がパンタグラフと呼ばれるようになった。厳密には菱形(四角形)ではなく、五角形である。一般的には鋼管をトラス構造に組立てたものであるが、一部にラーメン構造のものも見られた。

特に低・中速での追従性能がよく、下枠交差型が普及してもなお、国鉄の在来線電車の大半に採用されるなど架空電車線方式の集電装置の主流を占めていた。しかし、可動部の質量が大きい、高速時の空気抵抗が大きい、といった欠点があり、1990年代以降はシングルアーム型に取って代わられつつある。現在、新造車に装備されるケースはほとんどなくなってきている。










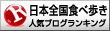




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます