
姫路駅は、姫路市の中心駅として、在来線3路線と新幹線が乗り入れるターミナルとなっています。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として姫路市内に所在する山陽本線のひめじ別所駅 - 網干駅間の各駅を管轄しています。
山陽新幹線と、在来線である山陽本線・播但線・姫新線の合計4線が乗り入れています。このうち山陽本線は在来線における当駅の所属線で、当姫路駅より神戸駅方面・東海道本線大阪方面には「JR神戸線」の愛称路線名が設定されています。 播但線と姫新線は姫路駅を起点としています。かつては、日本国有鉄道(国鉄)の播但線支線(飾磨港線)と山陽本線貨物支線、姫路市交通局の姫路市営モノレールが乗り入れていました。兵庫県姫路市駅前町にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅。駅の北側は城下町時代からの市街地で、南側は戦後発達した市街地である。東側では姫路操車場跡地の再開発が中途のままの状態となっています。姫路市役所へは手柄駅(山陽電気鉄道本線)が最寄り駅。駅前北ロータリーには淀井敏夫作の「希望」と題された銅像が1985年6月に設置されている。駅周辺の整備に伴い銅像は姫路港の姫路ポートセンター広場に移設されます。

1989年より姫路駅とその前後区間において在来線の連続立体交差化工事が行われ、2008年12月22日をもって全てのホームが高架化された。在来線は島式ホーム3面8線(内2線行き止まり)および下り通過線1線、新幹線は島式・相対式ホーム2面3線および上下通過本線の構成となっている。※在来線の上り通過線は無いので、上り通過列車(貨物列車等)は5番のりばを通過しています。

姫路駅プラットホーム
ホーム 路線 方向 行先 備考
在来線ホーム
1・2 ■播但線(普通) 寺前・和田山方面
□特急「はまかぜ」 大阪方面 2番のりばのみ
3・4 ■姫新線 播磨新宮・佐用方面
5・6 ■JR神戸線(新快速・普通) 加古川・三ノ宮・大阪方面
□特急「スーパーはくと」 大阪方面 5番のりばのみ
7・8 ■山陽本線(新快速・普通) 相生・播州赤穂・上郡・岡山方面
□特急「スーパーはくと」 鳥取方面(智頭急行線経由)
□特急「はまかぜ」 城崎温泉方面(播但線経由) 7番のりばのみ
新幹線:16両編成対応の11 - 13番のりば(山陽新幹線)は島式・相対式2面3線の高架ホームで、11番のりばと12番のりばの間に2線の通過線がある。また、11番のりばと在来線の高架の間に、線路をもう1線増設して2面4線とすることが可能なスペースがあります。基本的に新大阪・東京方面の列車は11番のりばを、岡山・鹿児島中央方面の列車は12番のりばを使用する。ただし、当駅始発の東京行「のぞみ」は12番のりばから(前日終着となった東京発「のぞみ」の折り返し運用のため)、7時台の当駅始発の岡山行き「こだま」と23時台の列車は13番のりばから発車します。また、事故や気象に起因するダイヤ乱れなど緊急時の列車待避に13番のりばを使用する場合があります。
新幹線ホーム
11 山陽新幹線 上り 新大阪・東京方面 当駅始発は12番のりば
12・13 山陽新幹線 下り 岡山・鹿児島中央方面
コンコースののりば案内標では上記のように案内されている。この他、寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」が、下りは8番のりば、上りは5番のりばに停車します。
在来線
島式ホーム1面4線(1 - 4番のりば)と14両編成対応の島式ホーム2面4線(5 - 8番のりば)、合計3面8線のホームを持つ。1 - 4番のりばは一つのホーム上にあり、2番のりばは大阪側・南側の切り欠きホーム、3番のりばは岡山側・北側の切り欠きホームです。1・4番線はスルー式になっており、姫新線と播但線を相互に直通することが可能。このため1番線の西側は播但線車両の留置線としても利用されています。2番のりばの岡山方には4番のりばへ進入するための渡り線がある。また山陽本線上り線岡山側から4番のりばへの進入が可能であり、夜間に貨物列車1本が4番のりばを通過している。なお1 - 4番線は全て電化されているが、架線は西側で終端となっています。大阪側の上り線と下り線の間に留置線が4線敷設されており、相生方面からの列車の折り返しや、播但線・姫新線の列車留置に使われている。大阪方面からの終着列車は、6番のりばへ進入して直接折り返す列車や、一時留置線で留置後上り新快速になる列車もあり網干総合車両所まで回送の列車もある(当駅で播但線に使用される221系が2番線で夜間滞泊を行っている)。岡山方面からの折り返し列車は直接7番のりばに入る事もある。2・4 - 8番のりばのいずれからも留置線への入出場は可能であるが、2・4番のりばからは一番北側の1番留置線にしか入線できないような配線となっています。

ホームには1面に1か所ずつ計2か所の待合室が設けられている。内部の座席は全て南向きで、冷暖房完備。ただし他駅と異なり、車椅子スペースの折りたたみ座席は設けられず、空きスペースとされている。山陽本線部は青春18きっぷシーズン中には、岡山方面への乗り継ぎを行う旅行者で混雑いたします。
5・6番のりば、7・8番のりばのそれぞれ中程には駅そば屋が設けられています。かつての地上駅時代には旧3・4のりば、旧6・7のりばの中程や旧31 - 33のりばの西端でも駅そば屋が営業していたが、新ホーム移行に伴い営業終了・撤去されました。また、旧1のりばの東端にはカレー屋もあったが、こちらも営業を終了しました。
5 - 8番のりばでは、駅員が赤旗を振る事によって客扱い終了合図を送っています。

姫路駅が山陽鉄道によって設置されたのは1888年暮れと、全国的に見ても初期の部類に入ります。このころの駅は市街地を避けて設置されることが多かったが、当駅の場合市街地のすぐ南隣、外堀の南側の田畑の上に作られました。この当時姫路城内には陸軍歩兵第10連隊が設置されており、このことによる必要性もあって市街地に隣接して設置されたと思われる。これは姫路市街の発展に大きく寄与することとなりました。なお翌年、姫路駅で日本で初めての本格的な駅弁が発売されました。
1894年から播但鉄道(後に山陽鉄道に合併され、現在は播但線)が当姫路駅に乗り入れるようになる。同線は陰陽連絡線であると同時に、生野銀山の銀を運ぶ役割もありました。姫新線の接続は遅れて1930年である。1958年に明石駅から当姫路駅までが電化され、東京方面からの列車はここで電気機関車から蒸気機関車への付け替えをおこなっていました。その名残か、高架化前の当駅の跨線橋下には多数の洗面台があり旅人が顔を洗う光景が数多く見られていた。さらに1972年には山陽新幹線の岡山駅までの開業で新幹線の駅が設けられ、東京方面と日帰りできるようになった。近距離輸送では、1923年8月19日には飾磨駅・高砂駅経由の本格的都市間高速電気鉄道(インターアーバン)である神戸姫路電気鉄道(現在の山陽電気鉄道)が明石駅 - 当駅間で開業。以後長らく神戸までの輸送は神姫電鉄→宇治川電気→山陽電鉄、大阪などへ向かう長距離客は国鉄という棲み分けがなされていた。 第二次世界大戦後、山陽電鉄が1948年に日本における戦後初のロマンスカーとして記録される820形を投入、快適な接客設備によりシェアを拡大した。これに対抗して国鉄はC62形などの牽引機を例外的に東灘で転向するという無理をして神戸駅 - 当駅間で列車増発を実施、従来の棲み分けが徐々に崩れ始めました。1958年の山陽本線西明石駅 - 姫路駅間電化で40分間隔になり、1968年の神戸高速鉄道開業と同時に国鉄線も毎時2本に増発された。1972年の山陽新幹線の岡山駅までの開業に伴って新快速への153・165系の転用が実施され、さらに1973年のダイヤ改正で当駅発着新快速の増発(毎時2本へ)が実施されるまで、急行券を必要とするにもかかわらず大阪駅 - 当駅間で国鉄急行の利用実績が高かったことが示すように、神戸以東への直通客、特に対大阪方面の輸送実績については常に国鉄が圧倒的優位に立っていました。この状況は料金・所要時間の問題もあって、山陽電鉄の阪急六甲駅・阪神大石駅への直通乗り入れと高速神戸での大阪方面への同一ホーム乗り換えを実現した神戸高速鉄道の開業をもってしても覆ることはなく、オイルショック後は沿線の工業地帯が大きなダメージを受けたこともあり、山陽電鉄の輸送実績は1970年代前半から後半にかけて大きく低下しました。さらに、1980年から国鉄側は老朽化した153・165系の代替用として117系を新快速に投入、本格的に神姫間のシェア拡大を図るようになり、1986年11月1日に新快速はすべて当駅発着になった。221系投入後はさらに利用客が増加しました。

1995年の阪神・淡路大震災は姫路駅にも重大な影響をもたらしました。駅に地震の直接的影響があったわけではないが、震災によって分断され当駅止まりとなった山陽新幹線や神戸市内で断絶したJR神戸線を迂回するためのルートとして播但線が用いられ、姫路駅は同線あるいはJR神戸線の開通区間に乗り換える博多方面との間の乗客で大変に混雑した。姫路市とその周辺地域はモータリゼーションの進展が激しく、当駅の乗客数は昭和40年代頃をピークに一度大きく減少している。昭和50年代半ばに底を打ち、以降は上記のような積極攻勢もあってピーク時の水準以上にまで戻している。しかし山陽姫路駅側はピーク時の半分以下と大きく落ち込んでしまった。また、みゆき通りを始めとする姫路駅前の商店街は郊外型店舗に客を奪われ苦しい状況です。かつては当駅にも貨物設備が存在していた。北上する播但線の東側に、コンテナホームや有蓋車用車扱貨物ホームがあり、鉄道貨物輸送の拠点となっていたが、設備の老朽化や市街地に位置することにより設備が小規模であることから、郊外に新設した姫路貨物駅へ機能を譲渡し廃止された。また付属設備として姫路操車場およびターンテーブルと扇形庫を擁する姫路機関区や姫路客貨車区が設置され、鉄道病院も駅南側に設置されていました。連続立体化工事の際に高架ホーム予定地や地平ホーム跡の発掘調査を行ったところ、奈良時代の遺跡(「豆腐町遺跡」と命名された)が発見され、和同開珎や漆紙文書など多数の遺物が出土しています。











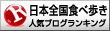


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます