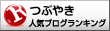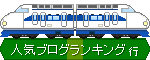今朝の信州は、気温は18度、信州の空一面厚い雲が覆
っていて、いよいよ入梅かな~と感じさせられます。
今日は、夏至です。そして明日は6月の満月ストロベリームーン
です。明日の満月は昼間の10時08分なので早朝観察か
明日の夜の観察がいいはずですが・・お空が、ね~
今日は、夏至(げし、英: summer solstice)は、二十
四節気の第10。北半球ではこの日が1年のうちで最も
昼(日の出から日没まで)の時間が長い日。南半球で
は、北半球の夏至の日に最も昼の時間が短くなります。
今日を境に、だんだんと日が短くなっていきます。
ついこの頃迄朝が明るくて、朝walkingには最適の季節
今日から朝の時間は1分ずつ遅くなっているようです
この朝の明るさがず~と続けばいいのですが・・
「昼の時間が長い」というのは北半球での話で、南半
球では同じ日が、もっとも昼の時間が短い日になります。
同じ日本でも、緯度によって微妙に変わるんですね。
例えば東京(緯度35度)だと、夏至の日の昼は14時間
例えば東京(緯度35度)だと、夏至の日の昼は14時間
34分。札幌(緯度43度)では15時間23分。北へ行く程
長くなるんですね。北極圏(緯度66.6度以北)では24
時間、太陽が沈みません。いわゆる白夜ですね。
逆にもっとも夜が長い日が冬至。これも二十四節気の
ひとつで今年の冬至は、12月21日(土)となります。
同じ日に、南半球では昼がもっとも長くなります。
同じ日に、南半球では昼がもっとも長くなります。
二十四節気は太陽の動きをもとにした暦で、季節を表
すのに便利だったため、月の動きをもとにした太陰暦
が普通だった時代からよく使われてきました。
1年を24等分して、夏至・冬至の中間の日(昼と夜の
1年を24等分して、夏至・冬至の中間の日(昼と夜の
長さが同じ日)を春分・秋分とさだめています。
夏至、冬至、春分、秋分という4日間の、さらに中間が
立春、立夏、立秋、立冬と呼んでいますよね。
この8つの日はニュースなどでもよく耳にする言葉ですね。
この8つの日はニュースなどでもよく耳にする言葉ですね。
二十四節気は中国で生まれた暦のため、ネーミングの
季節感が日本とは微妙に違う部分があります。
例えば、立秋が8月7日ごろだったり、夏至は梅雨のない
例えば、立秋が8月7日ごろだったり、夏至は梅雨のない
北海道を除いて、ほぼ日本全域で梅雨だったりします。
そのため、雑節という日本独自の暦を表す言葉も生ま
れました。八十八夜(5月1日or2日)、入梅(6月10日
or11日)、半夏生(はんげしょう:7月1日or2日)、土用
(7月19日or20日)といったものです。
そして冬至はカボチャや小豆などを食する習慣があり
ますが、この夏至には、そんな美味しいものを頂く慣習
は見当たりませんね~食に飢えてる私には残念です。
季節感をこのように表すのも、また風流ですよね~
今年のようにまだ梅雨入りもしないのに、夏至とか
今日からの雨が梅雨入りとなるのでしょうか、それと
も、遅い梅雨入りの新記録となるのでしょうか
昨夜は大分の息子が来て今日は愛知の娘が来るようで
す。もう暫く軟禁状態が続きますのでブログのコメント
はお休みさせて頂きます。
写真は1カ月ほど前の朝walkingから