まめに更新できる間に、ジャッキー・チェン話のつづきをしたくてムズムズしているのだが、今回もおあずけ。
久々にマスコミ試写で見た映画のことを。
『バット・オンリー・ラヴ』
2015 同作・製作運動体
監督・脚本・主演佐野和宏
4月2日よりK‘scinemaほか全国順次公開
http://www.but-only-love.com/
佐野和宏の監督復帰作。「誰?」と思う人は、まあ、よそを検索してみてください。
「あの〈ピンク四天王〉のひとりである伝説的な映画人の、がんで声帯を失ったあとの、18年振りの復活作なのだ」と劇的なトーンで紹介する文章は、あちこちで見つかると思う。
試写室に入ったのは約3ヶ月振り。改めて、実感した。マスコミ試写はくたびれる。
「タダ見をする」後ろめたさがドンヨリ付きまとうからだ。感想を求められたら何か必ず、他の書き手と違う視点を言わないことには乞食と同じだ、位のプレッシャーがある。「媒体をお持ち」ではないので、なおさら。
本作も、配給の東風・渡辺さんに、いつものように感想を聞かれたものの、いつものようにはペラペラと口から出てこなかった。「あとでメールかなにかに書きます」と答えて帰った。実際に書こうとしたらとりとめもなく長くなりそうだったので、こうしてブログに。
昔、デニス・ホッパーの小規模の未公開監督作だったかを、やたら「伝説の復活!」と大きく喧伝するのに対して、居心地悪く思うことがあった。
別にデニス・ホッパーだけでなく、フラーでもアルドリッチでも森東でも石井輝男でも、「手に取るなやはり野に置け蓮華草」という態度が、僕には一番しっくりくる。まあ、ホドロフスキーや長谷川和彦みたいに、必要以上に伝説扱いしてもらったほうが精が出そうなタイプもいつつ。
とにかく、『イージー・ライダー』(69)も見ていない人が、いきなりカルトにさえ昇格してないものに接したら、かなりの確率で置いてけぼり感を味わう。その時に、誰も責任を取れないだろう……と、クソマジメに余計な心配をしたわけだ。でも、大体の人は「伝説の復活!」にさえ立ち合えて、「デニス・ホッパー、シブいッすよね」と飲み屋で感度の高い友人や先輩相手に数回話ができたなら、それで満足なのだった。その映画は確か、けっこうお客さんが入った。
その時、ああそうか、これが〈エスクァイア・マガジン式宣伝商法とその需要〉か、と妙に納得した。
「伝説の復活!」ならなんでも大好きな、シネマバーの常連みたいなタイプは個人としては苦手だけど、今、立ち合うこと自体が大事だって点は、肯定的に捉えるようになった。
昔の代表作を見ていないと、新作を見たところで分からないのでは……と、敬遠したら、かえって勿体ない、ということだ。
いずれにせよサブカルチャーが元気だった頃の話なので、本作、『バット・オンリー・ラヴ』の〈ピンク四天王、18年振りの監督復帰!〉という押し出しポイントが、〈エスクァイア・マガジン式〉の延長として有効かどうかは、蓋を開けてみないと分からない。
今はもう、「ピンク映画とアダルトビデオは違うんですよ。それはイコール、ソフトコアとハードコアの違いでありまして……」と、ひとくさり説明が必要になるから。
ただ、物事には、それだけ古い話になると逆に有難味が出てくる、神話的光彩を帯びてくる場合がある。
佐野和宏の初老のビジュアルに、実はあの『追悼のざわめき』(88)の主演者と同一人だ、という認識がハマれば、かつての、デニス・ホッパーはとにかく渋いんだから渋い!のふしぎな人気に近い現象は起こり得る。
……さて、中身の話になかなか、ならないようですが。もう、中身の話を始めてはいるんです。
『バット・オンリー・ラヴ』は、佐野和宏が声を失った自分自身を映画に出して、己が赤心を表出する、がメインテーマだ。中身とパッケージがあらかじめ接着されていて、分けては話せない。
「久し振りに作ったオレの映画は受け入れられるか?」と、「オレの人生はまだ続くし、忘れられるつもりもないが、それでいいか?」が不可分になっている、とも言える。近来では稀少なほど、見事に“自分の映画”であることに徹した映画だ。かつて佐野が〈ピンク四天王のひとり〉と形容されたことを抜きにしては語れないようになっている。
といって、現実には、過去のピンク映画の監督作をよく見ていて、今も新作映画情報をチェックする人となると、いきおい数は限られるだろう。そこは、『イージー・ライダー』がビデオでいつでも見られるデニス・ホッパーとは違う。
なので僕も、自主製作の処女作『ミミズのうた』(83)はどこかの上映会で見ている、代表作『変態テレフォンONANIE』(93)なんかもリアルタイムで……なんて同時代ばなしを書きたい気持ちは、それほど湧かない。書いたところで、上記程度しか見ていないし。
ただ、2016年に試写室で見ているのに、僕は途中で、新宿国際名画座や新宿昭和館地下に座っているような錯覚を起こした。一瞬だけ、本当にタイムスリップしたようで、自分自身でゾクッとした。
濡れ場だけでなく、ロケセットでのカメラの置き場所、カット割り、アフレコの音感、がいちいちピンク映画なのである。若い人が本作を見て、なんか映画の文体が、あんまり見たことのないものだ……と感じたなら、まさにその部分が、往年のピンク映画らしさなんですよ、と教えてあげて丁度良い感じ。
制作が国映だといっても、成人映画の興行チェーン用ではなく、単館ロードショーの一般映画として作られている。にもかかわらず、ここまで濃密にピンク映画らしい点には、気持ちが留まった。
90年代当時、〈ピンク四天王〉の映画は、評論家、批評家、映画マニア(今で言うシネフィル)にはウケが良いが、エロが足りないので商品(今で言うコンテンツ)としては二流、と言われていた。僕がバイトしていた昭和館地下(本作のフラッグシアターになるK‘scinemaの前にあったところです)は、エロに特化したエクセス系の新作が主だったので、違いはよく覚えている。
つまり僕は、佐野和宏は(四天王の他の3人も)、ジャンル映画のフォーマットに則りながらの面従腹背で作家のフィルムを作りたい人であって、例えばカサイ雅裕や深町章のようには、ピンクに殉じているわけではないのだ、と認識していた。
ところが『バット・オンリー・ラヴ』には、ローターの遠隔操作オナニーや、バイブレーターを人妻の口に無理やり銜え込ませて……という、ピンク映画では無くてはならない場面(アダルトビデオが普及する前の時代、という認識が一般的だと思うが、家の無い、日雇いで得た金を払ってレストハウスに泊まるおじさんは、ビデオデッキなんて持ってない)が、ちゃんと?出てくるのだった。もう、一般劇場公開作品なんだから、わざわざ描き込む必要も無いのに。
ここが、ジャンル映画で培われてきた監督の個性、というものなのだろう。
深作欣二、佐藤純弥らとともに東映やくざ映画をバリバリ撮っていた中島貞夫が、ATGで映画を作ったのに、まんま東映やくざ映画になった『鉄砲玉の美学』(73)とよく似た事態が、本作でも起きている。
手術を経て、声が出ない。
心情を具体的に描くための方法論は、ソフトコアのピンク映画。
二重の制限を、逆手にとったり利用したりしながら、生れた映画なのだろうという気がする。
そうでなければ、とても描けない自身の屈託、ナイーヴな本音が「妻の不貞への疑惑に苦しみ、妻を罰しようとした男」というストーリーの中に、託し込まれている気がする。
それが具体的にどういうものかは、僕には見つけられなかった。
ピンク映画らしさ、と散々書いてはきたが、主人公は妻との寝室以外では、カラミは果たしていない。よその人妻、若い娘との行為はそれぞれ未遂に終わる。別れた不倫相手の女性と再会しても、会話だけ。ピンク映画らしいフォルムで出来上がっているのに禁欲的という、実はかなり、ストレンジな映画なのだ。ヒントはこのあたりにある、とは思うのだが。
もしかしたらその本音は、深夜の、主人公が寝ている妻に向かっての、声にならない声の独白場面にあるのかもしれない。劇中の、声にならない声は大体、磁石ボードの筆談の字を撮ったカットで示されるが、あそこだけは、本人しか何を言ったか分からないようになっている。
なんとか聞き取れたのは、「……アノコロ、タノシカッタ……」「……オマエノセイダ!……オマエノセイダ!……」。
ネタバレ注意ってやつにならないよう、ぼかして書くが、妻が電話で、主人公に向かって長いセリフを言う場面もある。主人公は相槌も打てないわけだから、やはり長い独白めく。
本作のベース(参照のタネ)のひとつはおそらく、『パリ、テキサス』(84)だろうと僕は見立てている。
かの有名な、トラヴィス(ハリー・ディーン・スタントン)が妻に向かって長くしゃべり続ける場面を、夫婦の対の独白は容易に連想させるし、ストーリーそのものは違うが〈妻を探し求める〉構造にベクトルが向かっていくところも似ている。何より本作と『パリ、テキサス』は、〈愛情があるのに離れる〉ことへのモチーフ―或いはディスコミュニケーションの問題と直面した時の深い溜息と言ってもいい―が、共通している。
『パリ、テキサス』の場合は、サム・シェパードが、家族と漂泊という相容れぬもの(しかしどちらもアメリカ文学の基本テーマ)の間に引き裂かれる思いをヒリヒリと描き込んだシナリオを、ドイツのヴィム・ヴェンダースが批評的な目でこさえたわけだが。(それによって現代アメリカ論のように映画のスケールは大きくなったし、いささか難渋な、演出の独りよがりな部分も生まれた)
本作、『バット・オンリー・ラヴ』は、脚本も佐野だ。深夜に主人公が、寝ている妻に何を言ったのかと、佐野自身が(愛する人や、愛した人に)何を訴え、乞いたかったのかは、ほぼ重なると思っていいんじゃないだろうか。
だけど、その声は、観客には聞こえない。
佐野が描きたいのはあくまで、赤心が己を苛んだ渦中の再現だった、と考えることもできる。
妻の不貞を疑わざるを得ない情報がもたらされた時、主人公は、割とすぐに苦しみ出す。平和な温かい夫婦関係を築いたと信じてきた男なら、もうちょい、半信半疑の時間が長くあってもいいものだが、主人公はホント、すぐに(どんな男に抱かれたんだ)という妄執に囚われる。苦しむ時間のほうが生きている実感を味わえる。そういう質の人間が、待っていたように、そうなる。
大体、主人公は単著も出している国語の教師。美しい妻と美しい娘。清潔で広い家。でもって、昔は才女と長らく不倫していて、今も激しく憎まれたことが彼女の胸に残っている。
主人公=佐野、とあんまり重ね合わせてしまうと、いい気なもんだ……と呆れる一歩手前の設定なのだ。
「都合が悪くなると黙り込む」のを常套手段にしてきたインテリ男性は、基本、社会的には如才なくやれるようになっているものだ。そういう男が今は声を失っている設定には、吟味すると、もうひとまわりのユーモアが仕込まれているのかもしれない。(主人公が絵を描く―筆談とは別の表現方法を手にしている―ことは、冒頭で示されるだけに、後半でも活かされたほうがいいとは思った)
つまり。
徹底して“自分の映画”でありつつ、佐野はやはり、フィクションを作ったのだ。声の出ない自分自身を登場させたといっても、さらけ出すイコール自己表白、ではない。僕はそこに、引きずられかけていたかな。
目に見えない愛情(それはあったのか、まだあるのか、もう消えたのか、もともと無かったのか)を探して苦しんだ思いそのものを、オレは映画にしたんだ。カンタンに目に見えるかたちで描けるものかよ。佐野が言いたいことは、こっちかもしれない。
タイトルは、これはほぼ間違いなく、ニール・ヤングのソロ・キャリアでの初めてのヒット曲「オンリー・ラヴ」(70)からとったものだろう。佐野と年齢が近い人の多くが、この曲の収録アルバム『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』を愛聴している。僕もこのアルバム、初めてCD化された学生時代から、大好き。
but only love can break your heart
でも恋だけがきみの心を引き裂く(中川五郎訳)
ウニョウニョと書いたが、せんじ詰めれば、ほとんど、この一節の映画化。おじさん純情篇なのだ。
きみたちこの痛み、みんな覚えがあるだろ。今、血を流してる真っ最中かもしれないね。だけど、おじさんも、おばさんも、そうなんだぜ。幾つになっても痛いんだ。
それがメッセージとして、〈ピンク四天王〉の時代を知らない観客に伝われば、佐野和宏って誰?という興味は、自然と後から付いてくるだろう。
長くなったついでに、自分の話を。
本作を僕は、かなり落ち着かない、胸苦しいような、まぶしいような気持ちで見た。
日本映画学校を卒業した時、よくつるんでいた演出ゼミの数人が、一斉にピンク映画の現場に出て、瀬々敬久、佐藤寿保、そして佐野和宏の助監督になった。〈ピンク四天王〉の呼称が生まれる、ほんの少し前。
脚本ゼミの僕は、ある脚本家の助手をずっとつとめて、これから一本立ちする、ホンペンの執筆が控えている、という男のアシスタントになったのだが、これが失敗だった。
助手としては優秀なのにピンになると途端に書けなくなる。そういうタイプの典型だった。
シノプシスの案も出てこないので、ホンペンの話は流れた。片手間だと軽んじていたテレビの仕事も、いつの間にか来なくなった。精神的に追い詰められたのだと思う、ささいなことで顔を真っ赤にして「お前は絶対にものにならない」と怒鳴るようになった。苦しかったのだろうと理解はしているが、そんなセンセイのもとに通う毎日は……。
一方、助監督になった奴らは、オルタネイティブな日本映画の第一線で仕事を覚える高揚で、活き活きしていた。顔を合わせるのもつらくなった。あの頃の、どんどん置いていかれる、差を付けられていくのが肌で分かる痛み、〈映画は俺を拾わなかった〉という思いは、今も僕を縛っている。
そんな時、助監督になったひとり、Yが僕のバイト先に顔を出して「今夜これから、今、俺が付いてる監督と女優の○○さんと近くで呑む。お前も来いよ」と誘った。
その時、佐野和宏―佐野さんと、一度だけ一緒に呑んだのだ。もう四半世紀も前のことなので、佐野さんは覚えていないはずだ。
ゼロ、といっていいほどその席で、僕は存在感が無かった。あの頃、佐野さんは「いずれ日本のロバート・デ・ニーロになるのでは」位の噂をされる人だったし、精悍で、尖った雰囲気を発散させていた。緊張と気おくれでガチガチになり、ほぼ全く会話することができなかった。
(この、重度の対映画人コンプレックスで、目の前にすると口が聞けなくなる症状は後年、荒井晴彦さんの時も出てしまうのだが、その話はまたいずれ)
スタインベックの『二十日鼠と人間』みたいなストーリーを映画にしたい、と佐野さんがYに構想のひとつを話していたのだけは、覚えている。
全く口も聞けなかった夜のことは、僕の中では蹉跌経験のひとつになっていて、その後も、佐野さんが助演で映画に出てくるのを見るたび、ドキッとしていた。
「体調が悪いらしい」「がんになってしまった」「手術をして声帯を取った」といった話は、断続的に誰かしらから聞かされていた。
現在のところは、なんとか構成作家の仕事で糊口はしのげるようになった。とうとうここまでホンペンに近づけず仕舞だったが、俺は俺でやってる、俺は俺が思うほどには無能じゃない、と言い聞かせたい気持ちはある。
佐野さんの新作、という情報を知って、本当にすごいことだし、おめでたい話だと素直に思った。
でも、端役や内トラで、緒方明監督から『追悼のざわめき』の制作だった山本希平さんまで、〈知ってはいるがふだんのお付き合いの無い人〉がどんどん出てきたのには、心臓がチクッと疼いてしまった。ここにいる人たちと、胸が焦げるほど、同じ土俵に上がりたかった。
しばらく眠っていたのに、まだ、対映画人コンプレックスがある。これがガソリンになって、なんとかテレビの仕事をやってこられた面もあるので、仕方ない、一生付いて回るのだと思っている。
















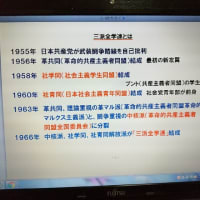
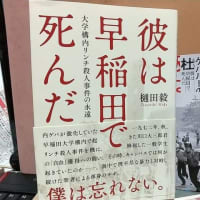

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます