しばらく前からSNSでは映画だけでなく、聴いたレコード、読んだ本なども短い感想を書いている。僕はちょっと古いものに今さらのように触れるペースでやっているので、それが情報としてはいいのではないかと思って。ミニコミ誌の埋草スペースを担当しているような気持ち。
で、LP2枚組の『五木ひろし ラスベガス・オン・ステージ』(1976 ミノルフォン)を聴いたこともササッと出そうとしたのだが、どうしても長くなりそうなので、ブログで書いておきます。

若い頃の松山数夫(本名)は1965年、松山まさるの名でレコードデビューした。その後、一条英一、三谷謙と改名しては再デビューしたもののなかなか芽が出なかった。
最期のチャンスのつもりで出たオーディション番組で平尾昌晃と山口洋子に見出され、1971年に五木ひろしの名で改めてデビュー。「よこはま・たそがれ」が大ヒットして一躍スターとなった。その後は常に第一線。1973年の「ふるさと」「夜空」あたりからは子どもでも知っている存在になった。
ここまではもう常識に近い話だと思う。
1976年、上昇期を迎えていた五木は、ラスベガス・ヒルトンホテルのショールームで公演した。日本人歌手のラスベガスでの単独公演は初めて。それを収録したのがこのレコードだ。公演は成功して、ひろしinヒルトンは1978年まで3年続いた。(1979年からは、山口洋子のプロデュースから独立して「おまえとふたり」を大ヒットさせるなど、ドメスティックを極める別路線に入る)
なぜ、ラスベガスだったのか。実は、ハッキリした理由はオフィシャルなかたちで広く知られているわけではない。雑誌やサイトで読める五木本人のインタビューでも「大きな挑戦だった」など、概念的なことが語られるのみだ。
ただ、複合的な理由がからまっての必然だっただろうことは理解できる。
当時、五木をマネージメントしていた野口修は、戦前のウェルター級チャンピオンである野口進の息子で、ボクシングの試合のプロモートからこの世界に入り、キックボクシングのブームを作った、格闘技の世界では伝説的な人物だ。五木は歌手でマネージメント契約した第一号にあたる。
ここらへんの経緯を知るには、近年評判のノンフィクションである細田昌志の『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修 評伝』(2020 新潮社)を読んでおかねばだが、少なくとも五木サイドには、音楽専門の業界人よりも視野の広い、世界と戦う/世界の舞台に立つ自分達をいきなりイメージできるだけの蓄積があった。
それに1966年にヒルトンホテルの二代目社長に就任したバーロン・ヒルトンは、もともとベンチャーでいろいろと経験を積んでいた実業家で、父が創業したヒルトンを大きなブランドにするため、カジノ事業の拡大などに辣腕をふるった。
音楽界にカムバックしたエルヴィス・プレスリーの公演もその一環で、ショーの充実は、新しい高級ホテルの売りのひとつだった。そんなやり手のバーロン・ヒルトンが、経済大国になった日本のお客をたくさん連れてきてくれることを当て込める歌手に注目するのは当然だろう。(ちなみにバーロンは、パリスとニッキー姉妹のおじいちゃまにあたる)
つまり、どっちもいい仕事、より大きな先につながる仕事がしたかった。それで決まった公演なのだから、そんなに難しい話ではないとも言える。
五木ひろしとラスベガス。確かにパッと受け取った時のミスマッチのインパクトは大きいので、このレコードは演歌ジャンルの割には音楽ファンの間で話題になることが多い。
ただ、演歌嫌いの方々の半ば揶揄を込めた珍盤扱いや、和モノDJの方々の逆張り的な高評価のどちらかに分かれがちな印象がある。
僕が聴くぶんには、実は奇をてらったところのないレコードで、まっとうな歌と演奏を楽しめる実況録音盤だ。それが言いたいばかりに少し長めの前段を書いた。
本当にオーソドックスで、全体になめらか。むしろ初期の藤本卓也作曲路線である「待っている女」「夜汽車の女」に関しては、オリジナルシングルのほうがずっと攻撃的だ。
五木は自身のヒット曲ばかりでなく、ポール・アンカやアダモに「赤とんぼ」「ソーラン節」まで歌い、自己紹介のMCのあたりでは琴まで鳴るのだが、当時の日本人歌手の海外公演では当然の構成だろう。日米親善の姿勢を示すのと、歌手としての幅の広さを伝えるのと、両方が噛み合っている。
大事なのは、ショービジネスの本場で歌う経験を積む、ということ。それを日本の業界に還元すること。一番伝わってくるのは、そんな五木ひろしの真面目さだ。ラスベガスであろうと、史上初であろうと、日本でと同じようにていねいに、まっとうに歌う。それがアメリカで通用するのかどうかを、まず自分で試す。
こうしたトップの責任感は、NHK『歌う!SHOW学校』(2016~2018)の先生役などで見せていた後輩歌手への面倒見の良さにもつながっている。
それにもうひとつ、書いておきたいポイントがある。
演奏はヒルトン・オーケストラで、指揮は服部克久。そして編曲のクレジットには、服部と前田憲男、宮川泰と、戦後のポピュラー音楽を牽引してきた3人が名を連ねている。
彼らが現地のオーケストラを束ねたものが、奇をてらわない、まっとうな演奏に聴こえる。しっくりきている。これは実はなかなか劇的なことだと思うのだ。
3人とも1930年代生まれ。少年時代は敵国だったアメリカで、青春時代は胸が焦げるほど憧れたアメリカで、自分のアレンジを鳴らす。
すでに坂本九や小澤征爾、秋吉敏子らが開拓してきた後なので、もうそんなに大仕事のつもりで臨んでいなかったかもしれないが、自分のアレンジがふつうに現地のオーケストラの演奏になじむのには、それなりの感慨はあったはずだと思う。
五木がエルヴィスよろしく荘重に歌い出す「リパブリック讃歌」が、途中から明るいディキシーランド調に崩れる(さらに曲の歴史的な原点に戻る)瞬間は、どうだ、俺達はあなた達の音楽をここまでよく知り解釈できているのだぞ、という宣言に聴こえる。
そういうツッパリに、ジンとくるものがある。
















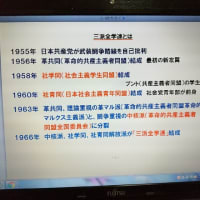
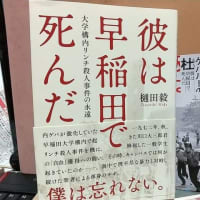

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます