僕はこのブログで「プログラミングを学ぶべき理由」をずっと説明してきました.要約すると,プログラミングはこれから重要なスキルであると言われているけれども,それ以前に,「コンピュータとはなにか」ということを知るためにプログラミングを学ぶべきなんですよ,ということです.
「コンピュータとはなにか」というのが説明が難しい.だいたいコンピュータの専門家でもここはうまく言語化できていないんじゃないでしょうか.僕もかなり手探りな状態です.
それで,最近つかっている例が田んぼです.多くの小学校に小さな田んぼや畑があって,担当の学年が決まっているのだと思いますが,お米や野菜を育てています.秋には収穫されて,それが給食に出されたりします.なんのために,これを小学生にやらせているのでしょうか.普通にスーパーに行けばお米や野菜は簡単に手に入ることができます.大人になっても趣味で農園をやっている人はいますけれど,大半の人は購入で済ませてます.まして,これからは農業の時代だからすべての子どもたちに農業体験は必須である,ということでもありませんよね.
逆に私たち大人が気持ち悪いと思うことは,子供達が,お米や野菜がどうやって育つのかを知らない,ということですよね.都会に育つ子供達だと,どうやって育つのかをまったく知らないまま大人になってしまう可能性があります.魚の切り身の話もありましたね.子どもは売られている切り身しか見たことがないから,切り身の状態で海に泳いでいると思っているとか.
教育を効率とか将来の効果とかそういう視点だけでみてしまうと,田んぼはたぶんやらないです.ところが,大半の大人たちは,それを知らない子どもを気持ち悪いと思う.なので,小学校で田んぼをやることは,なんとなくいいことだという合意は取れているわけです.
たんぼをやるというのは,分解すると,水とお日様が大事だとか,雑草をとらないと栄養が奪われるとか,小さい種から少しずつ大きくなるとか,毎日見てても成長の変化には気がつかないけど,長い期間で見ると確かに成長しているとか,そういう,わざわざ言葉にしなくてもいいくらい常識的なことをなんとなく知るということですね.
コンピュータとはなにかというのも,そんな難しい話をしているのではないのです.水やお日様や種や成長といったことに相当するコンピュータの中身のことを知るということなんです.
野菜の成長のことなんか何にも知らなくても,スーパーで買ってくるぶんには困らないように,コンピュータの中身を知らなくてもコンピュータは使えます.でも,野菜の成長のことを知らない子どもが気持ち悪いと同じような感じで,コンピュータの中身をしらない人が大勢いるのは気持ち悪いと思うわけです.
「コンピュータとはなにか」というのが説明が難しい.だいたいコンピュータの専門家でもここはうまく言語化できていないんじゃないでしょうか.僕もかなり手探りな状態です.
それで,最近つかっている例が田んぼです.多くの小学校に小さな田んぼや畑があって,担当の学年が決まっているのだと思いますが,お米や野菜を育てています.秋には収穫されて,それが給食に出されたりします.なんのために,これを小学生にやらせているのでしょうか.普通にスーパーに行けばお米や野菜は簡単に手に入ることができます.大人になっても趣味で農園をやっている人はいますけれど,大半の人は購入で済ませてます.まして,これからは農業の時代だからすべての子どもたちに農業体験は必須である,ということでもありませんよね.
逆に私たち大人が気持ち悪いと思うことは,子供達が,お米や野菜がどうやって育つのかを知らない,ということですよね.都会に育つ子供達だと,どうやって育つのかをまったく知らないまま大人になってしまう可能性があります.魚の切り身の話もありましたね.子どもは売られている切り身しか見たことがないから,切り身の状態で海に泳いでいると思っているとか.
教育を効率とか将来の効果とかそういう視点だけでみてしまうと,田んぼはたぶんやらないです.ところが,大半の大人たちは,それを知らない子どもを気持ち悪いと思う.なので,小学校で田んぼをやることは,なんとなくいいことだという合意は取れているわけです.
たんぼをやるというのは,分解すると,水とお日様が大事だとか,雑草をとらないと栄養が奪われるとか,小さい種から少しずつ大きくなるとか,毎日見てても成長の変化には気がつかないけど,長い期間で見ると確かに成長しているとか,そういう,わざわざ言葉にしなくてもいいくらい常識的なことをなんとなく知るということですね.
コンピュータとはなにかというのも,そんな難しい話をしているのではないのです.水やお日様や種や成長といったことに相当するコンピュータの中身のことを知るということなんです.
野菜の成長のことなんか何にも知らなくても,スーパーで買ってくるぶんには困らないように,コンピュータの中身を知らなくてもコンピュータは使えます.でも,野菜の成長のことを知らない子どもが気持ち悪いと同じような感じで,コンピュータの中身をしらない人が大勢いるのは気持ち悪いと思うわけです.










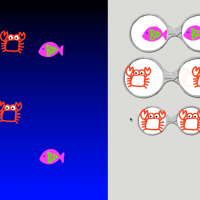
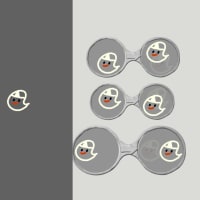
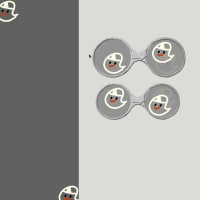
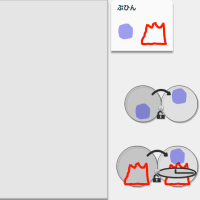
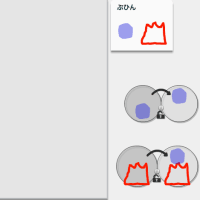
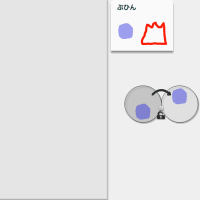

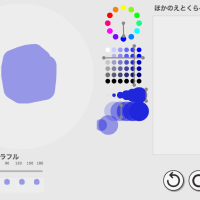
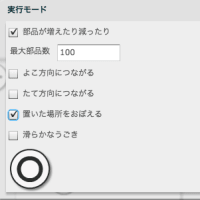
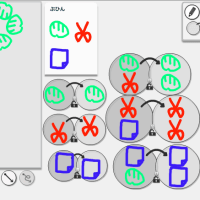
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます