この番組タイトルは地味ですね。
せめて梅若玄祥の名前くらいは出したらどうなのか。
それでもわたしの目にとまったくらいだから、結果的にこのタイトルで問題ないということか。
前に梅若玄祥×葉加瀬太郎のコラボの番組を見た。
ここで初めて梅若玄祥の名前を知り。印象に残っていた。今回は外国人とのコラボですか。
ギリシア悲劇と能は相性がいいように感じていた。非常に大雑把だが、
……古代ギリシアも日本も自然神信仰の多神教でしょ。
蜷川演出の日本人によるギリシャ悲劇をテレビで見たことがある。
もちろん音吐朗々の台詞回しは全く能にはないものだけど、
演劇に聖性が必要とされることは大きな一致点。
大道具がシンプルだったのもまた一致点。
しかし横のものを縦にしようというんだから数々の衝突はね。
テレビ番組ではこの衝突の部分を全然深く描いてくれなくて不満だった。
ここをしっかり描いてくれたら、より一層「能とは・ギリシャ劇とは」という部分がよくわかったと思うのに。
でも衝突のさわりだけでも多少はわかった部分がある。
世界的古典でも、大きな読み違えをすることもあるということ。
ちなみにわたしは、通して読んだという意味では世界こども名作全集かなんかの
オデュッセイアしか読んだことがない。
でもあれはそれなりに分量があったし(大判辞書1冊分くらいの大きさ。寝転がって読むには相当重い)
多分大人も読めるくらいしっかりと書いてあった記憶がある。
いい本だった気がしますよ。その後のわたしの数十年、これでオデュッセイアをまかなってきたんだから。
今回の演目は「ネキア」。オデュッセイアの冥府行の部分をいうらしい。初耳。
いやあ、初耳。冥府行自体は「ああ、そんなのもあったな」程度の記憶はあるけど、
オデュッセイアを全体としてみるならば、脇筋で、もっといえばオデュッセウスの中でわざわざこれを
能にするかね、という地味な部分。――と、一般的にいっていいのかどうか知らないが、わたしはそう思った。
能といえば死者。死者を出したくてわざわざコレなのかなあという感想。
能の脚本にする人も、まあわたし程度の読み込みではないだろうが、やはりだいぶ読み違えていたらしい。
能って多分登場人物が2人か3人がベストだよね。しかしネキアではオデュッセウスがテイレシアスに
予言をしてもらうという主目的に加え、その時点で死んでいる、母やアイアス、色々な人に出会う。
話としてはキルケーも出るのかな?
これを、多分最初の脚本では登場人物を数人に削ったんだろう。
梅若さんがテイレシアス。これがシテでオデュッセウスがワキなのは、多分能としては基本的な割り振りだろう。
日本人としてはこれだけでいいように思えるが、――ギリシア人としてはそれだけじゃだめなんだって。
死者のなかにはアイアスがいる。アイアスはアキレウスの死後、その鎧をオデュッセウスと争い、
それが原因で狂い死にした猛将。深い因縁の相手。
それが出てこない「ネキア」は「ネキア」じゃないと。
――これをわたしは日本古来の物語で例えてみようとしているんだけど、なかなか思いつかない。
オデュッセイアに対応するには古事記あたりからもってきたいところだが……
アメノウズメが登場しない天の岩戸?
タケミナカタのエピソードがない国譲り?
うーん。これ!というぴったり感に欠けるなあ。そもそも古事記って、シーンごとの登場人物少ないもんなあ。
群像劇になるわけがないのだ。
が、ネキアのシーンは有名無名の死者がわさわさといる――というイメージだが、何しろ読んだのは
世界こども全集の頃なのでさだかではない――ので、多分そのわさわさ感も必要なんだろう。
ちょっとね。ネキアの内容がね。全然わからないからね。皆目見当がつかない状態で書いてるんだけどね。
そもそも日本語Wikiに、11歌の内容としてアイアスのことが全く触れられていない時点で、
日本人の読みとしてはアイアスの扱いが軽いんだなあ、というのを実感。
ならばギリシャ語Wikiや英語Wikiはどうかというと、英語Wikiは意外なほど記事全体が短く、
章ごとのあらすじなんて記載されてないし、ギリシャ語Wikiは――ギリシャ語読めないのでわからん。
やっぱりギリシア古典の脚本を作ろうというなら、ギリシャ人との密なる相談は必要だよねー。
テレビでは、最初は全く日本側で作り、稽古もしてほとんど出来上がってから(つまり相当時間的に切羽詰まってから)
ギリシャ側から全面改稿の申し入れがあったように描いてあった。
作り手側は能は日本のもんだし、脚本は能の作法で書くもんだし、いくら演出家がギリシャ人だからといって
自分たちでやるつもりで作ってたんだろうけど、話の根幹が違うと言われたらなあ。
足元をすくわれた思いだろう。もっと最初からお互いで細かく意見を交換しておくべきだよね。
せめて電気的に会えるくらいは出来る限り会って喋っていた方がいい。今どきスカイプとかあるんだからさあ。
花道が超長いのも、柱の代わりに池?があるのも、演者は大変だろうと思った。
それをもう達観したように“なんでもやる”感じの梅若さんもお疲れさま。と思った。
で、舞台としては……
やっぱり人が多すぎてわさわさ感が強くて、まあそんなにいいもんとは思わなかったね。
わたしは、能はその演者の「存在」が「動く」際に美しさを感じるものだと思うが、
大勢舞台にあがったお弟子さんたちは、さささっと動いて、それでは単に移動であろう。
なんていうかね。存在の重み――だと思うんだよね。能の真骨頂は。
そこがあまり出てなかった。
ただ、新しい試みはなんでもやってみなきゃ始まらないし、今回のチャレンジも努力賞だと思う。
しかし梅若さんほどの人でも、今回の条件ではおいそれとは名作を生み出せない。
力量が充分にあってもこれだから、よくよく難しいことなんだろうなあ。
せめて梅若玄祥の名前くらいは出したらどうなのか。
それでもわたしの目にとまったくらいだから、結果的にこのタイトルで問題ないということか。
前に梅若玄祥×葉加瀬太郎のコラボの番組を見た。
ここで初めて梅若玄祥の名前を知り。印象に残っていた。今回は外国人とのコラボですか。
ギリシア悲劇と能は相性がいいように感じていた。非常に大雑把だが、
……古代ギリシアも日本も自然神信仰の多神教でしょ。
蜷川演出の日本人によるギリシャ悲劇をテレビで見たことがある。
もちろん音吐朗々の台詞回しは全く能にはないものだけど、
演劇に聖性が必要とされることは大きな一致点。
大道具がシンプルだったのもまた一致点。
しかし横のものを縦にしようというんだから数々の衝突はね。
テレビ番組ではこの衝突の部分を全然深く描いてくれなくて不満だった。
ここをしっかり描いてくれたら、より一層「能とは・ギリシャ劇とは」という部分がよくわかったと思うのに。
でも衝突のさわりだけでも多少はわかった部分がある。
世界的古典でも、大きな読み違えをすることもあるということ。
ちなみにわたしは、通して読んだという意味では世界こども名作全集かなんかの
オデュッセイアしか読んだことがない。
でもあれはそれなりに分量があったし(大判辞書1冊分くらいの大きさ。寝転がって読むには相当重い)
多分大人も読めるくらいしっかりと書いてあった記憶がある。
いい本だった気がしますよ。その後のわたしの数十年、これでオデュッセイアをまかなってきたんだから。
今回の演目は「ネキア」。オデュッセイアの冥府行の部分をいうらしい。初耳。
いやあ、初耳。冥府行自体は「ああ、そんなのもあったな」程度の記憶はあるけど、
オデュッセイアを全体としてみるならば、脇筋で、もっといえばオデュッセウスの中でわざわざこれを
能にするかね、という地味な部分。――と、一般的にいっていいのかどうか知らないが、わたしはそう思った。
能といえば死者。死者を出したくてわざわざコレなのかなあという感想。
能の脚本にする人も、まあわたし程度の読み込みではないだろうが、やはりだいぶ読み違えていたらしい。
能って多分登場人物が2人か3人がベストだよね。しかしネキアではオデュッセウスがテイレシアスに
予言をしてもらうという主目的に加え、その時点で死んでいる、母やアイアス、色々な人に出会う。
話としてはキルケーも出るのかな?
これを、多分最初の脚本では登場人物を数人に削ったんだろう。
梅若さんがテイレシアス。これがシテでオデュッセウスがワキなのは、多分能としては基本的な割り振りだろう。
日本人としてはこれだけでいいように思えるが、――ギリシア人としてはそれだけじゃだめなんだって。
死者のなかにはアイアスがいる。アイアスはアキレウスの死後、その鎧をオデュッセウスと争い、
それが原因で狂い死にした猛将。深い因縁の相手。
それが出てこない「ネキア」は「ネキア」じゃないと。
――これをわたしは日本古来の物語で例えてみようとしているんだけど、なかなか思いつかない。
オデュッセイアに対応するには古事記あたりからもってきたいところだが……
アメノウズメが登場しない天の岩戸?
タケミナカタのエピソードがない国譲り?
うーん。これ!というぴったり感に欠けるなあ。そもそも古事記って、シーンごとの登場人物少ないもんなあ。
群像劇になるわけがないのだ。
が、ネキアのシーンは有名無名の死者がわさわさといる――というイメージだが、何しろ読んだのは
世界こども全集の頃なのでさだかではない――ので、多分そのわさわさ感も必要なんだろう。
ちょっとね。ネキアの内容がね。全然わからないからね。皆目見当がつかない状態で書いてるんだけどね。
そもそも日本語Wikiに、11歌の内容としてアイアスのことが全く触れられていない時点で、
日本人の読みとしてはアイアスの扱いが軽いんだなあ、というのを実感。
ならばギリシャ語Wikiや英語Wikiはどうかというと、英語Wikiは意外なほど記事全体が短く、
章ごとのあらすじなんて記載されてないし、ギリシャ語Wikiは――ギリシャ語読めないのでわからん。
やっぱりギリシア古典の脚本を作ろうというなら、ギリシャ人との密なる相談は必要だよねー。
テレビでは、最初は全く日本側で作り、稽古もしてほとんど出来上がってから(つまり相当時間的に切羽詰まってから)
ギリシャ側から全面改稿の申し入れがあったように描いてあった。
作り手側は能は日本のもんだし、脚本は能の作法で書くもんだし、いくら演出家がギリシャ人だからといって
自分たちでやるつもりで作ってたんだろうけど、話の根幹が違うと言われたらなあ。
足元をすくわれた思いだろう。もっと最初からお互いで細かく意見を交換しておくべきだよね。
せめて電気的に会えるくらいは出来る限り会って喋っていた方がいい。今どきスカイプとかあるんだからさあ。
花道が超長いのも、柱の代わりに池?があるのも、演者は大変だろうと思った。
それをもう達観したように“なんでもやる”感じの梅若さんもお疲れさま。と思った。
で、舞台としては……
やっぱり人が多すぎてわさわさ感が強くて、まあそんなにいいもんとは思わなかったね。
わたしは、能はその演者の「存在」が「動く」際に美しさを感じるものだと思うが、
大勢舞台にあがったお弟子さんたちは、さささっと動いて、それでは単に移動であろう。
なんていうかね。存在の重み――だと思うんだよね。能の真骨頂は。
そこがあまり出てなかった。
ただ、新しい試みはなんでもやってみなきゃ始まらないし、今回のチャレンジも努力賞だと思う。
しかし梅若さんほどの人でも、今回の条件ではおいそれとは名作を生み出せない。
力量が充分にあってもこれだから、よくよく難しいことなんだろうなあ。










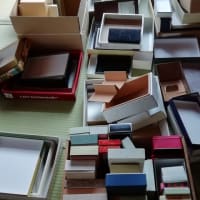













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます