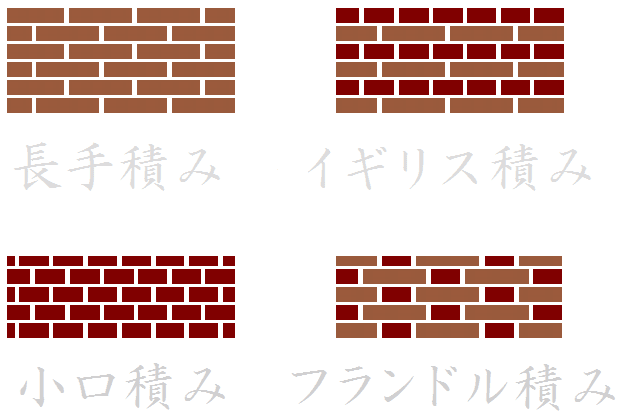その4では実用化に至るまでに開発されたスラブ軌道の試験線を紹介します。
まずコンクリート路盤向けのM型、A型、L型の3種類が検討され、それぞれ試作・試験を実施しました。
現存する最も古いスラブ軌道は紀勢本線の有田川橋梁下り線に敷設されているM-131/141形です。
このスラブ軌道は1967年(昭和42年)7月に敷設されました。

高架橋で良く見かけるA型と比べるとかなり複雑なつくりをしているように見られます。
M型はレールを締結した軌道スラブをビームとして受台で支持した構造です。(開床式)

軌道スラブの間にはレール方向の移動を抑制する突起が設けられ、突起の側面と下部の受台の間には緩衝用マットが敷かれています。このためマット調節形などとも呼ばれます。

またレールの締結方式は直21型(座面式)のためスラブには溝が掘られています。
M-131形は軌道スラブ長が3mで締結装置は片側6ヵ所、M-141形は4mで片側8ヵ所です。
元々省力化が開発コンセプトのスラブ軌道は新規開業区間に採用することで大きな費用対効果を得られますが、東海道新幹線の建設当時はまだ開発途上であったため本格的な採用は見送られました。

しかし東海道新幹線にも試験線として敷設されたスラブ軌道が僅かながら存在します。
名古屋駅14番線の新大阪方にはM-31形スラブ軌道が1967年(昭和42年)7月に敷設されています。

意外と知られていませんが新幹線の営業線の中では最も古いスラブ軌道になります。
M-131/141形とは異なり4つの突起を立てた受台で軌道スラブの前後左右移動を抑制しています。
M型の隣はコンクリート短マクラギ形の直結軌道となり、その先にまた違う軌道が現れました。

この一見するとラダー状の枠型スラブ軌道に見える軌道はA-50形です。(全面支持)
A形は軌道スラブと路盤の間にCAモルタル(セメントアスファルトモルタル)を挟むことで弾性を有しています。A-50形は軌道スラブの枠内に流し込んだCAモルタルの凸部によってレール方向の力を受けるため、突起コンクリートはありません。また、軌道スラブの両脇にある四角錘の存在も気になるところです。

岐阜羽島駅の下り通過線にも試験線があります。こちらは4ヵ月遅れの1967年11月に敷設。
このスラブ軌道では200km/h 以上の高速走行に対する安全性と耐久性が検証されました。

こちらもM-31形と称されていますが、名古屋とは支持構造が異なり、1つの突起で保持しています。どちらかというと有田川橋梁のM-131/141形をベースにした形状ですね。
突起の両脇にある竹とんぼみたいな金具は軌道スラブを上下方向に拘束する板バネです。

M型を筆頭とする初期のスラブ軌道は締結装置をスラブの溝に収めたレール座面式が特徴的です。
米原方にはA-50形スラブ軌道も敷設されていました。それぞれ25mずつ敷設されています。

名古屋のように直結軌道を挟んでいないのでM型とA型の接続部を観察できます。M型の軌道スラブは梁としての強度を持たせるため厚みがあります。M型は軌道構造としての性能は十分あるものの、受け台の支承構造が複雑で経費が高くつくことや使用箇所の制限があるといった欠点がありました。

2番線から名古屋方面を望む

この前下り列車で岐阜羽島を通過する際、一瞬だけ走行音が大きくなることに気が付きました。
気になる方は耳を傾けてみてください。
→岐阜羽島のスラブ軌道は脱線防止ガード設置に伴い2020年頃に撤去されました。
総武快速線の中川放水路橋梁にはL型スラブ軌道の試験線があります。

敷設されているのは写真右側の上り線で、左の下り線はA-151型が敷設されています。
L型スラブ軌道はレール直下を帯状のCAモルタルで支持するロングチューブ式(※後述のロングチューブ施工法とは違います)で、後に登場する枠型スラブ軌道のベースとなった施工方式です。試験線は昭和44年敷設とのことですが、橋梁自体は昭和32年に竣工しているので後天的な改造と思われます。

軌道スラブ自体はラダー状で名古屋や岐阜羽島のA-50形とよく似ていますが、レール直下のCAモルタルだけでは摩擦力が足りないため矩形の突起が設置されています。
下の拡大写真を見ると、軌道スラブはレール直下を除いて浮いていることが分かります。

このL型は敷設の際に下部構造に線状の支持台を設ける必要があり、この支持台を精度よく生産することが難しいと考えられました。その後、CAモルタルの開発が進み価格も下がったことから、軌道スラブ全面をCAモルタルで支えるA型が標準構造として採用されていきます。
また、帯状のてん充方法についても型枠による施工ではなく不織布にCAモルタルをてん充するロングチューブ施工法が確立されたことから、枠型スラブ軌道で本格的に採用されていきました。
クリックお願いします
↓ ↓ ↓
2018/5/28 加筆修正
2017/8/8 加筆修正
2022/11/23 加筆修正