帳簿を作成するために、帳簿に関することを調べていると、必ず「簿記」という言葉に出くわします。簿記(ぼき)は、英語で「bookkeeping」といいます。「帳簿を作成する=記帳する」という程度の理解でよいです。
簿記の方式には複式簿記と単式簿記があります。帳簿には様々な取引(入出金など貨幣価値で測定できる出来事)を記録しますが、複式簿記と単式簿記とでは取引の把握の仕方が異なります。
複式簿記では取引の両面を記録します。「売上が生じて現金が増えた」、「仕入をして現金が減った」といった具合です。一方、単式簿記では、「売上があった」、「仕入があった」といった具合に記録をします。
わが国に限らず世界中のほとんどの会社は複式簿記で帳簿を作成しています。市販されている会計ソフトも複式簿記の原理で帳簿を作成するためのものです。複式簿記で帳簿を作成するのが世界標準なのです。「複式、単式」という言葉にこだわる必要はありません。簿記といえば複式簿記なのです。
★仕訳とは?取引とは?
簿記を習得するに当たっては、「仕訳」に対する理解を避けて通ることができません。仕訳とは、取引を記録することです。「取引」とは、入出金など貨幣価値で測定できる出来事で、「1万円で売った」、「5千円で仕入れた」、「電車賃3千円を払った」、「現金10万円を盗まれた」、「倉庫が放火され全焼した」などのことです。「会議で有意義な議論をした」、「優秀な人材を採用することができた」、「お客さんに商品をほめてもらえた」などは簿記での取引ではありません。
仕訳は帳簿を作成し決算書を作成するという一連のプロセスの最初の作業です。帳簿や決算書は仕訳の集計結果です。
★勘定科目とは?
勘定科目とは取引を仕訳する際に、取引を分類し集計する単位です。「売った→売上」、「仕入れた→仕入」、「電車賃→交通費」、「現金で支払った→現金」、「資金を借りた→借入金」といった具合に、取引を分類します。その後に、この分類ごとに集計するのです。
★借方と貸方(試算表の集計場所のこと)
仕訳は左右同額で、左右それぞれに勘定科目を割り当てます(仕訳は左右しかありません)。勘定科目が左右のどちらになるかは、勘定科目ごとに決まっています。仕訳の左側を借方(英語ではdebit)、右側を貸方(英語ではcredit)といいます。この「借方と貸方」という言葉の意味に深入りしてはいけません。
大切なことは、仕訳を集計する試算表を理解することです。試算表には個々の仕訳で生じた左側(借方)の勘定科目は左に、右側(貸方)の勘定科目は右に集計します(試算表は左右しかありません)。仕訳は左右の金額が一致しますので、試算表の左右の合計金額も一致します。勘定科目によっては左右両方に金額が集計される場合がありますが、その場合は左右を差引したものが試算表での集計金額です。
この説明は簿記の教科書では必ずされていますので、この部分は必ず読んでください。会計ソフトでは、このプロセスはブラックボックスになっています。会計ソフトにも試算表と称する帳票がありますが、それは実質的には決算書(貸借対照表と損益計算書)と呼ぶべきものです。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
簿記の方式には複式簿記と単式簿記があります。帳簿には様々な取引(入出金など貨幣価値で測定できる出来事)を記録しますが、複式簿記と単式簿記とでは取引の把握の仕方が異なります。
複式簿記では取引の両面を記録します。「売上が生じて現金が増えた」、「仕入をして現金が減った」といった具合です。一方、単式簿記では、「売上があった」、「仕入があった」といった具合に記録をします。
わが国に限らず世界中のほとんどの会社は複式簿記で帳簿を作成しています。市販されている会計ソフトも複式簿記の原理で帳簿を作成するためのものです。複式簿記で帳簿を作成するのが世界標準なのです。「複式、単式」という言葉にこだわる必要はありません。簿記といえば複式簿記なのです。
★仕訳とは?取引とは?
簿記を習得するに当たっては、「仕訳」に対する理解を避けて通ることができません。仕訳とは、取引を記録することです。「取引」とは、入出金など貨幣価値で測定できる出来事で、「1万円で売った」、「5千円で仕入れた」、「電車賃3千円を払った」、「現金10万円を盗まれた」、「倉庫が放火され全焼した」などのことです。「会議で有意義な議論をした」、「優秀な人材を採用することができた」、「お客さんに商品をほめてもらえた」などは簿記での取引ではありません。
仕訳は帳簿を作成し決算書を作成するという一連のプロセスの最初の作業です。帳簿や決算書は仕訳の集計結果です。
★勘定科目とは?
勘定科目とは取引を仕訳する際に、取引を分類し集計する単位です。「売った→売上」、「仕入れた→仕入」、「電車賃→交通費」、「現金で支払った→現金」、「資金を借りた→借入金」といった具合に、取引を分類します。その後に、この分類ごとに集計するのです。
★借方と貸方(試算表の集計場所のこと)
仕訳は左右同額で、左右それぞれに勘定科目を割り当てます(仕訳は左右しかありません)。勘定科目が左右のどちらになるかは、勘定科目ごとに決まっています。仕訳の左側を借方(英語ではdebit)、右側を貸方(英語ではcredit)といいます。この「借方と貸方」という言葉の意味に深入りしてはいけません。
大切なことは、仕訳を集計する試算表を理解することです。試算表には個々の仕訳で生じた左側(借方)の勘定科目は左に、右側(貸方)の勘定科目は右に集計します(試算表は左右しかありません)。仕訳は左右の金額が一致しますので、試算表の左右の合計金額も一致します。勘定科目によっては左右両方に金額が集計される場合がありますが、その場合は左右を差引したものが試算表での集計金額です。
この説明は簿記の教科書では必ずされていますので、この部分は必ず読んでください。会計ソフトでは、このプロセスはブラックボックスになっています。会計ソフトにも試算表と称する帳票がありますが、それは実質的には決算書(貸借対照表と損益計算書)と呼ぶべきものです。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
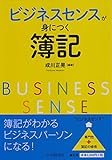 | ビジネスセンスが身につく簿記 |
| クリエーター情報なし | |
| 中央経済社 |













