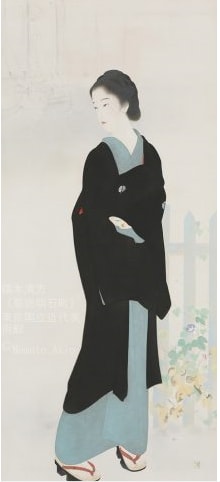
今年6月、長く所在不明だった鏑木清方画伯の「築地明石町」の絵が、
「新富町」「浜町河岸」とともに発見され、東京国立近代美術館に収蔵されました。
まぁ私など、しょっちゅう見に行けるわけでもなし、どこにあってもおなじなんですが、
私がまだ結婚前から行方不明になり、目にできるのは、それまでに撮られた写真などのプリントもの。
印刷技術がいまほどよくはない時代ですから、はてさて「本物に近い色」なのかどうなのか…。
3枚見れば3枚とも微妙に色がちがったりして…それがはっきりわかるわけですから、
やっぱりうれしい~!いつか本物に会える機会があるかもしれないと思うと心踊ります。
さて、この「築地明石町」、絵のモデルが誰だとか、描かれた経緯だとかは今日はパス。
話題にしたいのは「着方」です。
先日、「美の巨人たち」と言う番組だったと思うのですが、女優の酒井美紀さんリポート番組で、
あのスタイルをまねた姿で川べりにたちました。それがどうのと言うのではなく、
着付けのときに「じゅばんを着ないんですね」というお話しになりました。
「素袷(すあわせ)」という着方です。
明治の終わりから大正初期に流行ったといわれる着方で、文字通り「袷をじゅばんなしで着ること」。
確かにじゅばん、着ていません。

この「素袷」は「素合わせ」ではなく「素袷」と、わざわざ「袷」と言う文字を入れているのですから、
「袷の着物」だったと思うのですが、肝心の築地明石町では「単衣」のように見えます。
実際「素袷とは単衣の着物をじかに着ること」と言う記述もあります。
なぜ流行ったのかは、調べてみてもよくわからないのですが、いわゆる「粋な着方」として、
粋筋の女性に好まれたとか。あわせて黒繻子の掛け衿に素足、と言うのも流行ったのだとか。
こちらが足元。畳表の千両(のめりともいいます)ゲタに素足、です。

同時に見つかった「新富町」も「浜町河岸」も、黒繻子の掛け衿です。
黒い掛け衿は、江戸時代からありますが、当時の庶民は絹は着られませんから、
この場合は「絹の着物に黒い掛け衿」なのでしょうね。
さて、この「素袷」ですが、時期は初夏から夏、築地明石町の絵には、女性の足元に朝顔があります。
そして羽織を着ていても、足は素足です。
つまりは決して暖かくていい気候…ではなく、暑さにかかる時期、ですね。
ちなみに江戸時代の俳句の「歳時記」には「素袷」は「夏の季語」として載っているそうです。
ご承知のように今の時代、着物は厳格に守るならば、袷は5月の31日まで。6月からは単衣になります。
でも、時期も、また生活習慣や暮らしぶりなども、今と比べると違うところがたくさんありますから、
一概に夏に袷っておかしいよねぇ、それに羽織も絽じゃないよねぇ…と言う素朴な疑問を呈するのは、難しいんですね。
鏑木画伯は、明治11年生まれ、明治の半ばごろから絵を始めたそうですから、
実際に「素袷」をみているのでしょう。そうなると「単衣」か…。
ややこしいことですが、単衣の着物を普通にじゅばんの上に着ればいいものを、
わざわざ袷の着物を肌襦袢の上に直接着る、ということになるわけで、はてさて涼しいのかどうなのか。
そこがおしゃれというもので、袷だからいいのよ、なのかもしれませんし、
袷でも単衣でもいいけど、とにかくじゅばんナシがいいのよ、なのかもしれません。
たぶん、袷も単衣もいたのではないかと思います。
こういうことって「~でなければならない」よりも「こうしたらステキ」で使われるものだったのではないかと思っています。
そんなこんなをツラツラ考えておりましたが、今、この着方をしたら「あらちょっと」といわれてしまう。
それもまた残念なことです。ずっと言っていますが、着物に限らずいろいろなものが「かわっていく」こと、
コレは避けられないことです。また避けずに変わっていくことが「進化」であり「改善」であり、
それが定着していくことが、文化であるわけです。
着物も100年前、200年前、300年前と遡っていけば、今とは違うところがたくさんあります。
それぞれの時代に、それぞれの状況に合わせて、いろいろなことが変わってきて今に至るわけです。
ただ、残念なことに、一度着物は廃れかけましたから、順当な変化ではなく、
基本的なことがあれこれすっぽ抜けたまま、さらには商売上の都合で、売り手作り手の都合のいいことが、
「これが着物です」と、言われてしまったり、はたまた、自分の時代のことが「正しいこと」と、
それを教えるのではなく押し付ける状況があったり…。
結局、ある日着物を着てみようかと思ったら、どれが正しいのか、どれが普通なのか、
よくわからなくなってしまっていたわけです。
新しい着方、と言うものがよく出てきたりします。
若い方が、半衿にレースをつけたり、着物に靴や帽子だったり…。
それのすべてを否定するつもりはありません。それもひとつの「変化」だと思うからです。
ただ、変わるには基本がなければなりません。
伝統工芸といわれるものの数々も、たとえば漆工芸にしても、陶芸にしても、
もともとの基本的な、伝統的なものは大切にして、そこから上に積み重ねるようにして、
今の時代にあったものを作り始めています。
着物は積み重ねようとしたら「なかった」…の状態に近いです。
だから「基本」「伝統」という視点で守るべきものをきちんと残していかねば、
ただの奇をてらった思い付きだったり、奇抜なはやりものだったりになってしまう恐れがあるわけです。
実はこの「素袷」が今に残らなかったことは、それなりに「残らなかった理由」があるはずです。
今となってはその理由はわかりませんが、こういう着方があったということは記録や写真があったわけで、
もっと前の時代では、廃れてしまった「何か」が、もっとたくさんあるのだと思います。
残る残らないではなく、基本があるからそこからいろんなものが出てくる…という
当たり前のことを、していかなければならないと思うのです。
「浴衣にレースの半衿」は、「素袷」とは違う「ハヤリもの」だということ、それをどうしたら理解していただけるか。
それを考えていくのが、私がやりたいこと…なのだと思っています。






























初めて知りました。
なるほど、よーくみると襦袢を着ていない。羽織物まで来ているのに軽く見えますね~
着物の世界は奥が深いとつくづく感じ入りました。
耳で聞いても「アワセ」と言う言葉が「袷」だとは、
最近知ったので、へぇぇと思っています。
自由にいろんな着方もあるのが着物、
なにやら余分に固まっている今の着物の世界が、
ちょっと勿体無いと思っています。
ほんとに奥が深いですー。
「素袷せ」とは、粋な風情が満載ですね、意味深でもあるし。
袷に黒羽織で出かけたけど、お泊りすることになりちょっと、涼しいので襦袢は着ずに散歩に出た。。とか?
先ほど「着物好き」で投稿したものですが、すでに「着物好き」さんがいらっしゃるようなので、「です」を追加させていただきました。
今日は、もう少しだけ、前の記事を読ませていただきます。
コメントありがとうございます。
知らないことが出てくると、いろいろ想像をかきたてられますね。
ブログは長いのですが、半分からあとは、諸事情で、
すつかり着物話題から離れていまして…。
過去記事でお楽しみいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。