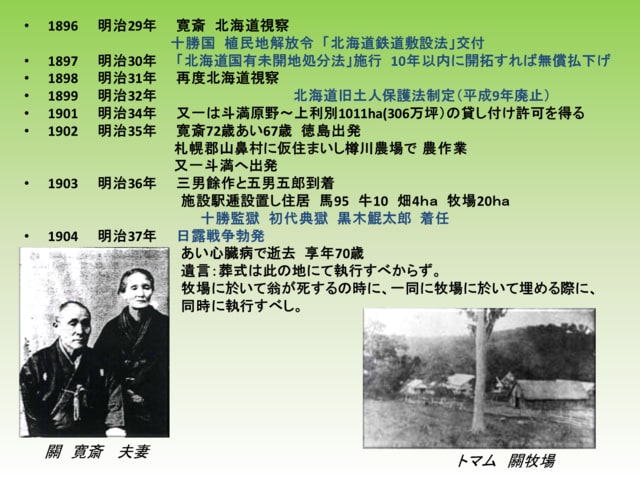

世の中を渡りくらべて今ぞ知る
阿波の鳴門は浪風ぞなき
寛斎は、感傷に浸る性癖は薄いほうだが、穏やかな鳴門の海を進む船縁に立って、苦節の皺が目立ちはじめたアイの横顔と、遠ざかり行く阿波の山々を眺めると、しばし感慨を覚えるのであった。
途次、東京をはじめ再度の上総の訪問などを経て、一ヵ月後の五月十八日、札幌に到着した。
寛斎は斗満開拓の前進基地として、又一に「樽川農場」を経営させていたが、さらに慎重を期し家族の便を考え、札幌に居を構えて連絡の足場にした。そこは、屯田兵の本拠地である郊外の山鼻(現・札幌南区四条西十二丁目)住宅である。
因みに樽川は札幌から北に五里(約二十キロ)石狩湾に注ぐ石狩川の河口付近に位置していることから、此処は、格好の足場であると云える。
寛斎は聴診器を鍬に替え、妻・アイは機織りの筬の代わりに鎌を手に、葉もの野菜、根菜、豆類、粟黍稗の雑穀など、自給自足に励んだものの腰は突っ張り、萎えた手は上がらず、節々がポキポキと鳴るように痛み、全身が疲労の塊である。
寛斎は「幸いにして儂は健康なり」と、自負していたが、意識と肉体とは必ずしも一致せず「筋必合和」(きんひつあいわする)には至らなかった。
一方、妻・アイは、大家族の主婦としての多年の苦労、とくに辛苦と心労のためか、心臓がかなり弱っていた。気丈のゆえ、苦痛などを訴えなかったが、医師の寛斎には、彼女の心の臓の衰えがはっきりと診み取れた。
寛斎が札幌に着くと、入れ替わるように、片山八重蔵・ウタ夫妻が先達として、斗満に向った。
この片山なる人物は、徳島時代からの旧知で、明治二十五年、又一の札幌農学校入学に同行して徳島より札幌に移住。又一が貸付許可の樽川農場を、彼とともに開拓開墾し実務を担当し、さらに斗満関農場の開設にあたっては、調査・申請を行い関農場管理の責任者として働いた得がたい仲間であり、同志である。(「関農場の考察」より)
八月五日、寛斎の一行は札幌を発して牧場へ向った。この先遣隊が、現地で受け入れ準備が整った頃合を見計らっての出発である。妻アイは一同を送り出し札幌に残ることになった。いかに「偕老同穴」(かいろうどうけつ)とはいえ、この心の臓の衰弱では、当初の開拓は無理である。厳しい気候に対処できる住居が整い、そこで、くつろいだ生活ができるまでは、別居も止むを得ない。寛斎にとっては、別れて暮らしても「夫婦は輪廻の絆」の思いである。
札幌から落合までは、開通間もない鉄道に乗りそれからは徒歩。現在は新狩勝トンネルを快適に通過出来るが、一行は国境の峠を歩行し、清水に降り一泊。翌日は帯広に出、又一に合流して一泊。さらに高島、利別に宿泊、五泊目は足寄に宿。
翌日の早朝、アイヌ一名を道案内として雇い、乗馬を調達して出発。ほどなく十伏川を渡ると、おりから鉄道建設工事のための、測量の天幕があるのみで、人跡未踏の密林。川沿いに山間の道を行くのだが、寛斎の眼には何処が道だか皆目見当がつかぬ所を進んでいる。
数回、川を渡り峻坂を登り、密樹の繁茂する間をくぐるときには、鞍にかじり付いてもなお危く、木の枝に帽子が引っ掛かったり、或は袖が枝にからまり危うく馬から転げ落ちそうになった事が、一度ならず二度三度、数回にもおよんだのである。
そのうえ、原生の大樹のために昼なお暗く、案内人アイヌの後を追うのがすこぶる困難で、何度も見失いそうになり、後に続くのに必死の思いである。
無事に川を渡り平坦の原野に出、やれやれと思いきや、再び密林に入ると、到るところ倒れた大樹が横たわり、その上を飛び越え、或は曲がり、或は迂回するなど、さすがの寛斎も、「筆舌を以って尽くすべからずあり」と、彼にしては珍しく弱音を吐いている。
いやいやまだ続く。
斧が入らぬまま風化して朽ち果てた大樹の上に丸くなった蝮が五六匹、行く先々で、固まってとぐろを巻き、赤い舌をチョロチョロさせているので、ゾクとして全身が粟起したのである。

平坦地を通り過ぎると、密林あり、湿地あり、小川あり、その傍らに蕗の繁茂した所がある。
この蕗は直径六七尺(約ニメートル)高さは一丈余(約三メートル)、驚くことに、跨がった馬の上からでも手が届かない高さで、寛斎が携えた傘で比べると、倍以上の大きさなので思わず感嘆。
それから十丁行くと湿地である。進むうちに馬脚が水没し、深さが馬の腹に達し、寛斎の足も膝まで水に浸ったままの前進である。ふと川岸を見ると、近傍の葦は、彼の身の丈以上の高さである
やっとの思いで川を渡り、また、平坦地に出で再び湿地に入ったが、今回は馬脚は膝を没するも馬腹までには至らず、八月十日に出発以来、目指す陸別に五日がかり、やっとの思いで到着した
寛斎は、この間の苦闘の行程について、「此処(陸別)に至りては、予は実にうれしくて、一種言ふべからざるの感にうたれて、知らず識らず震慄して且つ一身萎えるるが如きを覚えたり。
此時たるや精神上に言うべからざるの感を為すは、これ終身忘るる事能はわざるべきなり。
故に今日に於ても時存思い出す事あり。ああ此現状に遇するに、於ては大満足たるや、如何なる憂苦困難を重ねたるも、此れにて満難を打消すべきを感じたり。
ああ世人は斯くの如きの実境を得る事を知らず、只空しく、一身一家を固守するの人にては、自ら誇るのみ其人をあはれに思うなり。
夜、アイヌが鱒二匹捕りたるを調理して晩飯を食して眠につけり。此夜は恰も慈母の懐に抱かれたる心地して大安堵せり」と述べている。
渡辺 勲 「関寛斎伝」陸別町関寛斎翁顕彰会編

「十勝の活性化を考える会」会員 K





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます