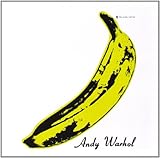エクアドル産のバナナが美味しいという話を熱めに語っていたら、ユニクロの「アンディ・ウォーホールのバナナの絵」Tシャツをプレゼントして頂いた。
翌日、エクアドル産の一本もの高級バナナを持参する。と言っても一本150円(高級とは言えバナナ価格)なので、一緒にGODIVAの粒粒チョコをつけて、ついでに高級チョコバナナもお楽しみ頂けるようにしてみる。「ではこの粒粒チョコを、バナナに埋め込んで食べてみます」と先方は言っていたけれど、本当にそうしただろうか。
八百屋などで見ていると、バナナにも結構色々な種類があるように思える。けれど、店頭で見る名前は、「バナナ」、「高原バナナ」、「台湾バナナ」、「モンキーバナナ」の4種類くらい。あと赤い「レッドバナナ」。「バナナ」はそのままだし(当たり前だけど)、「高原」と「台湾」は産地の特徴と国名をつけただけ、「モンキーバナナ」は唯一名前らしいと言えるかもしれないが、なにかその小ささを侮っているような気がして今一つ気が乗らない。ラカタンバナナ。東京マラソンで配られるというスポーツ・バナナだ。スポーツ・バナナとは何ぞやと思えば、クエン酸が多く含まれているのでエネルギー代謝がよく、スポーツマン向けということらしい。
現在日本国内の市場で出回っているバナナの約90パーセントは、フィリピン産のジャイアント・キャベンディッシュ種ということ。大きくて、食べごたえもあるし、皮も厚い(皮が厚いのが何の役に立っているのかはよく分からないが)。とにかくきれいなレモン色なのである。キリンのようになったら食べ頃、という言い方も、このバナナの為のように思える。
バナナについての記事を見ていたら、今をときめくジャイアント・キャベンディッシュの前には、世界の覇者、その名をグロス・ミッシェルというバナナがあったそうだ。ところが1900年代半ばにバナナの大敵パナマ病が蔓延し、グロス・ミッシェル種は壊滅。その後に改良され出てきたのが、ジャイアント・キャベンディッシュ種らしい。ウィキペディアによれば、1960年代には完全にキャベンディッシュがグロスミッシェルに取って代わったという。
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの1stアルバムは、1967年発売だ。
言わずもがな、アンディ・ウォーホールのバナナの絵は、このアルバムのジャケットに使われた。
このバナナの絵の商標権をめぐり、アンディ・ウォーホール・ヴィジュアル・アーツ基金なるものと、バンド側が争っていたらしい。2013年5月29日に示談により和解が成立したという記事があった。http://ro69.jp/news/detail/83068
そう思うと、ユニクロのTシャツの絵にも感慨深いものがある気がする。そういやユニクロはMoMAニューヨーク近代美術館のスポンサーにもなっていて(MoMAのサイトのトップ・ページに堂々とロゴが出ている)、何故かニューヨークが好きなんですね。
アンディ・ウォーホールのバナナの絵は、別に悲しくはない。ただのバナナだから。
ただ気になるのは、このバナナがグロス・ミッシェル種なのか、キャベンディッシュ種なのかということだ。
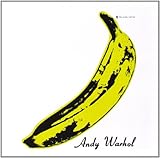
翌日、エクアドル産の一本もの高級バナナを持参する。と言っても一本150円(高級とは言えバナナ価格)なので、一緒にGODIVAの粒粒チョコをつけて、ついでに高級チョコバナナもお楽しみ頂けるようにしてみる。「ではこの粒粒チョコを、バナナに埋め込んで食べてみます」と先方は言っていたけれど、本当にそうしただろうか。
八百屋などで見ていると、バナナにも結構色々な種類があるように思える。けれど、店頭で見る名前は、「バナナ」、「高原バナナ」、「台湾バナナ」、「モンキーバナナ」の4種類くらい。あと赤い「レッドバナナ」。「バナナ」はそのままだし(当たり前だけど)、「高原」と「台湾」は産地の特徴と国名をつけただけ、「モンキーバナナ」は唯一名前らしいと言えるかもしれないが、なにかその小ささを侮っているような気がして今一つ気が乗らない。ラカタンバナナ。東京マラソンで配られるというスポーツ・バナナだ。スポーツ・バナナとは何ぞやと思えば、クエン酸が多く含まれているのでエネルギー代謝がよく、スポーツマン向けということらしい。
現在日本国内の市場で出回っているバナナの約90パーセントは、フィリピン産のジャイアント・キャベンディッシュ種ということ。大きくて、食べごたえもあるし、皮も厚い(皮が厚いのが何の役に立っているのかはよく分からないが)。とにかくきれいなレモン色なのである。キリンのようになったら食べ頃、という言い方も、このバナナの為のように思える。
バナナについての記事を見ていたら、今をときめくジャイアント・キャベンディッシュの前には、世界の覇者、その名をグロス・ミッシェルというバナナがあったそうだ。ところが1900年代半ばにバナナの大敵パナマ病が蔓延し、グロス・ミッシェル種は壊滅。その後に改良され出てきたのが、ジャイアント・キャベンディッシュ種らしい。ウィキペディアによれば、1960年代には完全にキャベンディッシュがグロスミッシェルに取って代わったという。
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの1stアルバムは、1967年発売だ。
言わずもがな、アンディ・ウォーホールのバナナの絵は、このアルバムのジャケットに使われた。
このバナナの絵の商標権をめぐり、アンディ・ウォーホール・ヴィジュアル・アーツ基金なるものと、バンド側が争っていたらしい。2013年5月29日に示談により和解が成立したという記事があった。http://ro69.jp/news/detail/83068
そう思うと、ユニクロのTシャツの絵にも感慨深いものがある気がする。そういやユニクロはMoMAニューヨーク近代美術館のスポンサーにもなっていて(MoMAのサイトのトップ・ページに堂々とロゴが出ている)、何故かニューヨークが好きなんですね。
アンディ・ウォーホールのバナナの絵は、別に悲しくはない。ただのバナナだから。
ただ気になるのは、このバナナがグロス・ミッシェル種なのか、キャベンディッシュ種なのかということだ。