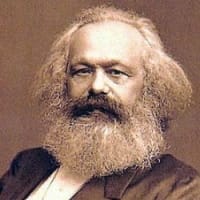第2章 古典派経済学の公準
よみがえる一般理論と現代正統派理論の空疎さ
助走がすんだところで、いよいよケインズの論理展開を追ってみよう。
古典派の公準とは、雇用理論を考える上での前提であった。その雇用理論は、第一公準は雇用の需要関数を与え、第二公準は雇用の供給関数を与える。賃金は労働力商品の価格だから需要と供給の二つの関数の交点が雇用の均衡点となる、というものである。
古典派の雇用理論とは

図では
実質賃金が均衡点より高いと需要が供給を下回り失業が発生し
逆に
実質賃金が均衡点より低いと需要が供給を上回り実質賃金が上昇する ことを示している。
古典派にしろ、現代正統派にしろ、実ははっきりとした理論はない。が、図のようなものを見せられると「そうかな」と思ってしまう。
一時的に失業者が増えることがあっても、価格による調整で失業はなくなる。というのが概ね古典派の話であろう。図では実質賃金が二つの曲線の交点まで下がれば失業はなくなる、と主張している。これは「贅沢言わなきゃ仕事はある」という「世間知」と結びついて強固な影響力を持ちイデオロギー化していくが、労働市場に価格調整を持ち込むと理論的に何が待っているのか考えようともしないし、考えるための理論もないのである。
強固なイデオロギーにとらわれた人には現実が見えない。消費増税とコロナの二重苦で経済が惨憺たる現状を示していても「財政再建」は進んでいくのだ。脱線した。
リカードのために付言しておく
エンゲル係数が非常に高く、穀物生産の弾力性が低い、つまり追加需要1単位に対する穀物の生産増が低い状態では、古典派の第1公準が該当するケースがある。リカード理論が穀物法廃止の理論的主柱となった理由である。同時に貿易における比較優位理論を確立し自由貿易の提唱者であったことも知られている。
しかし、第1公準の裏返しとして第2公準=労働供給を考えることの是非はさておき、農業生産技術の発達と貿易によって穀物価格が低廉に抑えられ、エンゲル係数も低くなり、賃金財(賃金で購入される財)そのものが工業生産品になった時、つまり「差額地代」が消滅したとき、なお古典派理論の第1公準も通用するのだろうか。この辺りのリカードの理論展開は「04:第2章 今も生きる第1公準 リカードの論理 」を参照されたい。
ところが、ケインズの時代になっても古典派はその理論がよって立つ前提を顧みることなく、「労働を含めたすべての商品の需給は価格によって調整される」という理論を変えようとはしなかった。
穀物生産の弾力性が生産(ケインズは総産出量と呼んでいる)の限界を画することがなくなった時、何が総産出量の限界を画するのだろうか?
総産出量の限界を迎えたとき雇用量の増大は止まる。そのとき完全雇用は達成されているだろうか?
現代正統派は総産出量の限界を画するのは「規制」だと言っているのだが、当時は何と言われていたのだろうか?
「一般理論」の叙述に戻る
古典派は、労働需給は価格(賃金)によって調整されるので、失業者は高すぎる賃金を求めて「自発的に」失業している、と考える。そうすると失業問題の解決は4つの方法しかなくなる、とケインズは言う。
実質賃金が均衡点より高いと需要が供給を下回り失業が発生し
逆に
実質賃金が均衡点より低いと需要が供給を上回り実質賃金が上昇する ことを示している。
古典派にしろ、現代正統派にしろ、実ははっきりとした理論はない。が、図のようなものを見せられると「そうかな」と思ってしまう。
一時的に失業者が増えることがあっても、価格による調整で失業はなくなる。というのが概ね古典派の話であろう。図では実質賃金が二つの曲線の交点まで下がれば失業はなくなる、と主張している。これは「贅沢言わなきゃ仕事はある」という「世間知」と結びついて強固な影響力を持ちイデオロギー化していくが、労働市場に価格調整を持ち込むと理論的に何が待っているのか考えようともしないし、考えるための理論もないのである。
強固なイデオロギーにとらわれた人には現実が見えない。消費増税とコロナの二重苦で経済が惨憺たる現状を示していても「財政再建」は進んでいくのだ。脱線した。
リカードのために付言しておく
エンゲル係数が非常に高く、穀物生産の弾力性が低い、つまり追加需要1単位に対する穀物の生産増が低い状態では、古典派の第1公準が該当するケースがある。リカード理論が穀物法廃止の理論的主柱となった理由である。同時に貿易における比較優位理論を確立し自由貿易の提唱者であったことも知られている。
しかし、第1公準の裏返しとして第2公準=労働供給を考えることの是非はさておき、農業生産技術の発達と貿易によって穀物価格が低廉に抑えられ、エンゲル係数も低くなり、賃金財(賃金で購入される財)そのものが工業生産品になった時、つまり「差額地代」が消滅したとき、なお古典派理論の第1公準も通用するのだろうか。この辺りのリカードの理論展開は「04:第2章 今も生きる第1公準 リカードの論理 」を参照されたい。
ところが、ケインズの時代になっても古典派はその理論がよって立つ前提を顧みることなく、「労働を含めたすべての商品の需給は価格によって調整される」という理論を変えようとはしなかった。
穀物生産の弾力性が生産(ケインズは総産出量と呼んでいる)の限界を画することがなくなった時、何が総産出量の限界を画するのだろうか?
総産出量の限界を迎えたとき雇用量の増大は止まる。そのとき完全雇用は達成されているだろうか?
現代正統派は総産出量の限界を画するのは「規制」だと言っているのだが、当時は何と言われていたのだろうか?
「一般理論」の叙述に戻る
古典派は、労働需給は価格(賃金)によって調整されるので、失業者は高すぎる賃金を求めて「自発的に」失業している、と考える。そうすると失業問題の解決は4つの方法しかなくなる、とケインズは言う。
- 「衰退産業」から「成長産業」への労働力移動を円滑にする。(摩擦的失業対策)
- 名目に対する実質賃金を引き下げること(物価の上昇も理論的にありうるが難しい)
- そのために、賃金財産業の生産性を上げること(または安い消費財を輸入すること。一時はやった「価格破壊」)
- 非賃金財価格を賃金財に比べて割高にすること(贅沢品への課税等の手段で賃金財を割安にする)
さらに言うと
- 貨幣賃金(名目賃金)の引き下げに反対する労働者の抵抗を排除すること
非常に既視感のある方法である。
新古典派の主張は現代まで連綿と続き、何の進歩もないことがわかるが、これに対するケインズの反論はこうである。
- 実質賃金の切り下げが賃金財価格の上昇によるものだとしたら、労働の引き上げを招くだろうか?
- 労働者は名目賃金の引き下げには抵抗するが、実質賃金の引き下げには抵抗する術がないのではないか?
- 実質賃金が下がれば労働者は労働を引き上げるなんてことがあったろうか?
- 実質所得維持のためむしろ労働供給量を増やそうとするのではないか?
等々の疑問を呈している。一般理論の全面展開まで全面的な反論はできないので、古典派の理論を徹底すればこんなことになってしまう、と反論しているのである。
雇用量の決定要因は、労働の価格とは別にある。ケインズは古典派の第1公準について次のような指摘を行っている。「第1公準が意味するのは、組織、装備、そして技術を所与とすれば、実質賃金と産出量(したがって雇用量)とは一意の関係をもち、それゆえ雇用の増大が起こりうるのは、一般には、実質賃金率の低下に付随する場合に限る、ということである。」
総産出量が変わらなければ、雇用量×一人当たりの実質賃金は変わらず、したがって実質賃金が減少しなければ、雇用量は増えない、ということになる。
雇用量×一人当たりの実質賃金=定数なら、どちらかが減らないとどちらかが増えない。しかし総産出量不変という前提は正しいのだろうか?そんなことはあるのだろうか。ケインズは短期ならありうる、と言っている。不況に突入する局面ではありうるだろう。
現代日本でも古典派の公準は生きている。ワークシェアとか言う筆者が一番嫌いな、そして人口に膾炙した概念である。しかし実際にワークシェアなんかやったら不況は永続化する。実際にしたし低賃金労働者を増大させた。不況の原因は別のところにある。
当たり前のことだが、雇用量を決めるのは産出量であってその逆ではない。*
では、なぜ総産出量が変わらなかったり、増加したり、減少したりするのだろうか?総産出量の決定要因はなんなのだろうか?この問いに答えたのがケインズの一般理論である。
要は、GDPはどのように決まっているかという話なのだ。まさに、よみがえるケインズである。
雇用量の決定要因は、労働の価格とは別にある。ケインズは古典派の第1公準について次のような指摘を行っている。「第1公準が意味するのは、組織、装備、そして技術を所与とすれば、実質賃金と産出量(したがって雇用量)とは一意の関係をもち、それゆえ雇用の増大が起こりうるのは、一般には、実質賃金率の低下に付随する場合に限る、ということである。」
総産出量が変わらなければ、雇用量×一人当たりの実質賃金は変わらず、したがって実質賃金が減少しなければ、雇用量は増えない、ということになる。
雇用量×一人当たりの実質賃金=定数なら、どちらかが減らないとどちらかが増えない。しかし総産出量不変という前提は正しいのだろうか?そんなことはあるのだろうか。ケインズは短期ならありうる、と言っている。不況に突入する局面ではありうるだろう。
現代日本でも古典派の公準は生きている。ワークシェアとか言う筆者が一番嫌いな、そして人口に膾炙した概念である。しかし実際にワークシェアなんかやったら不況は永続化する。実際にしたし低賃金労働者を増大させた。不況の原因は別のところにある。
当たり前のことだが、雇用量を決めるのは産出量であってその逆ではない。*
では、なぜ総産出量が変わらなかったり、増加したり、減少したりするのだろうか?総産出量の決定要因はなんなのだろうか?この問いに答えたのがケインズの一般理論である。
要は、GDPはどのように決まっているかという話なのだ。まさに、よみがえるケインズである。
*先走りだが、単純な産出量ではなく期待産出量である。