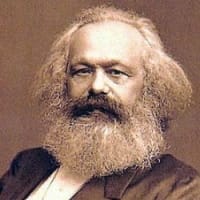この付論は全巻で最も難解だと思う。使用費用について厳密な検討を行っている。次は「第13章 利子率の一般理論」かな。
先ほどは、概略的に触れただけだがここでは精緻な議論が展開される。
「企業者の使用費用は、定義により、A1+(G′―B′)―G に等しい。ただし、 A1はその企業者の他の企業者からの購入領、 Gは期末において彼の資本装備がもつ現実の価値、G′は装備を使用せず、装備の維持・改善のためにB′という最適額の支出があったとしたならば、彼の資本装備が期末において有するはずの価値である。」
ここでケインズは使用費用に「価値のうち前期から引き継いだ装備が(なんらかの意味で)寄与した部分」と「G′は装備を使用せず、装備の維持・改善のためにB′という最適額の支出があったとしたならば、彼の資本装備が期末において有するはずの価値である。」と二つの意味を持たせている。のちほど統合的に検討する。
第6章においては費用は、雇用の費用である要素費用と使用費用①:他の企業者からの購入額、使用費用②:当期売り上げのうち過去の資本装備から移転した額の三つであった。
A1(外部購入費用)についてケインズは下記のように定義しなおす。「他の企業者に支払った額の一部は装備への当期の投資と見合い、残りは販売した生産物のために費やさたければならなかった犠牲のうち、生産要素への支払総額以外のものを表している。」すなわち、A1の一部は当期の投資と見合い、一部は完成品へ価値が移転されるということになる。
さらに
「ところで、G―(G′―B′)、すなわち前期より引き継いだ純価値を上回る企業者の資本装備の増加分は、装備に対する企業者の当期の投資を表し、これをIと書くことができる。こうして、A1を他の企業者からの購入額、Iを装備に対する当期の投資額とすれば、売上高 A の使用費用Uは、A1 - I に等しくなる。」
すぐにはわからない。ここでケインズの論述を離れて使用費用を解釈してみる。
総所得ではなく個々の企業者の所得を対象とする。
価値のうち前期から引き継いだ装備が(なんらかの意味で)寄与した部分をXとしておく。Xは実現された価値への資本装備からの移転額であるから、期首資本装備は期末までにX分減価すると考える。
わかりやすくなったとは思えないが、定義は厳密にしたつもりである。
ある企業者について
A:期中販売高
A1:外部購入費用
とし、
この企業者の
G0 :期首資本装備額
G:期末資本装備額
G′:当該資本装備を期中に使用せず、維持・改善費用B′を支出した場合の期末資本装備額
をとしておく。
このときB′を支出せず、かつ当該資本装備を期中に使用しなければ資本装備額はG0のままとする。つまり経年劣化はここでは考慮しない。資本の増加額Rは維持・改善費用Bを上回っているから、このとき必ずG′―B′>G0である。
期末資本装備額=当初資本装備額―減価償却累計ではない
G>G0としたとき、資本装備の増価には四つの回路が考えられる。G0をG01、G02、G03、G04に分解し、期首(末)資本装備額もそれに応じて①②③④とする。
- 資本装備を使用し、維持改善をしなかった場合はG<G0となり、ここでの検討から外れる。
①資本装備を使用し、維持改善の費用をかけた場合
期首資本装備額①―X+β(費用Bによる増価額)=期末資本装備額①
G01―X+β=G1
②資本装備を使用せず維持改善の費用をかけた場合
期首資本装備額②+β1(費用B′による増価額)=期末資本装備額②
G02+β1=G2
③新規設備投資I′をした場合
期首資本装備額③+I′=期末資本装備額③
G03+I′=G3
④資本装備を使用せず維持・改善もしなかった場合
期首資本装備額④=期首資本装備額④
G04=G04
①から④を連立方程式とすると
①G01―X+β=G1 資本装備を使用し、維持改善の費用をかけた場合
②G02+β1=G2 資本装備を使用せず維持改善の費用をかけた場合
③G03+I′=G3 新規設備投資I′をした場合
④G04=G04 資本装備を使用せず維持・改善もしなかった場合
G01+G02+G03+G04=G0 G1+G2+G3+G04=G だから
G0―X+β+β1+I′=G となる。
このときI′が期中に稼働を始めた場合I′からX′という価値移転があるとすると
G0―X+β+β1+I′―X′=G
G0―G+β+β1+I′=X+X′
G0―Gは負の値をとりβ+β1+I′は正の値を取る。
また次のように書き換えると
G0―(G―β―β1―I′)=X+X′
G―β―β1―I′は企業者の投資の決意にかかっている。ということになり一般的な減価償却の概念とは異なっている。
G0―(G―β―β1―I′)=X+X′は資本の増価・減価を表しており、貸借対照表上の概念である。所得を定義しようとすると費用面で考えなければならない。
費用面で考えると、βとBは一意の関係を持つであろうから
G0―(G―B―I′)=X+X′
G0―(G―A1)=X+X′
これは、第6章 1所得 のケインズの式と同じである。しかし結局期首資本装備価値と期末資本装備価値が決まらないと使用費用は決まらない。XはXのままである。期首と期末の資本装備価値はどのように決まるのだろうか?投資額次第であり、投資額はそれぞれの時点の資本の限界効率との関係で決まるのだが、論考のこの時点では結局Xのままである。
XはXのままである。ということがケインズの言いたかったことなのだ。
以前に筆者は使用費用を次のように定義した。
使用費用=資本装備の増減価額+投資額
投資額は企業者の期待に基づく決意に依存しており確定しない。そういうことである。