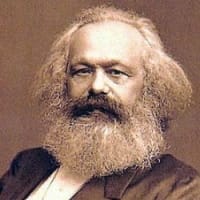人は、なぜ価格によって資金の需給すら均衡すると考えてしまうのか
前項で見た古典派の利子率理論はまさに新古典派・現代正統派の基本的考え方・異次元の金融緩和の理論的根拠そのものである。市中銀行の日銀預金を増やせば利子率が低下し投資に用いられる、と想定する。
ここで「一般理論」唯一のグラフが登場する、ので触れない訳にはいかない。古典派の利子率理論を視覚化したものだ。ケインズがなぜグラフを嫌うのか?グラフが意味を持つのは均衡点が見つかる、という前提があるからだが、一般理論には均衡点が存在しない場合がある。だから恐慌の分析に役に立つのだ。
誤解のないように強調しておくが、ケインズは、このようなグラフは成り立たないということを主張するためにこのグラフを掲載している。

曲線Xは投資の需要曲線。Yは投資の供給曲線である。rは利子率。Iは投資額である。利子率の上昇とともに投資の需要は減り(右下がり)、資金の供給は増える(右上がり)。両者は交点をもち、そこが均衡利子率である。なるほど、と思ったそこのあなた、もう一度最初から読み直してください。
いま需要曲線がX1からX2へと移動したとしよう。経済学者はカッコウをつけて需要曲線が下方にシフトしたなどと言うが、このとき「一般理論」は投資の変化によって所得も変化することを教えてくれる。投資の変化によって起こった所得の変化に対して資金の供給曲線はどうなるのか。Y1のままなのか、上へ移動するのか、下へ移動するのか、わからない。確かに両者は交点を持つかもしれないがそれがどこなのかはわからない、ということである。このグラフは何かを説明しているようで何も説明していない、ということなのだ。
問題は逆なのだ。今まで見てきたように流動性選好表と貨幣量から利子率は決定される。利子率が決定されると、そのときの投資量が決定されるわけだ。資金の供給は流動性選好表と貨幣量からすでに決定されている。流動性選好、利子率、貨幣量については次章で詳論される。
以下、古典派、新古典派との理論上の決定的分岐点をケインズ自らまとめている。
要するに、伝統的分析の欠陥は、体系の独立変数を正しく分離することができなかったところにある。貯蓄と投資は体系の被決定因であって、決定因ではない。貯蓄と投資は体系の決定因である消費性向、資本の限界効率表そして利子率が生んだ双子である。なるほどこれらの決定因は互いに絡み合っていて、各々は他の変化が予想されると、その影響を被りかねない。しかしそれらはその値を互いに他から推測することができないという意味で、やはり独立している。伝統的分析は貯蓄が所得に依存していることには気づいていたが、所得が投資に依存している事実には目が向かなかった。投資が変化したとき、所得は必然的に、投資の変化と同額の貯蓄の変化を生むよう変化しなければならない。このようなふうにして、所得は投資に依存するのである。
利子率を「資本の限界効率」に従属させようとする理論がうまくいったかというと、こちらもはかばかしくない。なるほど均衡状態では利子率は資本の限界効率と等しくなるであろう。なぜなら当期の投資規模を〔資本の限界効率と利子率の〕均等が達成されるまで増やす(あるいは減らす)のが有利だから。しかし、これを利子率理論としたり、ここから利子率を導出したりするのは、マーシャルがこの線に沿つて利子率を説明しようとして途中で気づいたように、循環論法である。というのは、「資本の限界効率」は部分的には当期の投資規模に依存しており、この規模の大きさを算出しうるためには、それに先立って利子率があらかじめ知られていなければならないからであ。新たな投資〔財〕の生産は資本の限界効率が利子率に等しくなるところまで推し進められるというのは重要な結論である。ただし、資本の限界効率表が教えるのは利子率がどうなるかということではない、それは、利子率が与えられたとき、新規投資〔財〕の生産がそこまで推し進められる、その限界点を教えるのである。
体系の決定因である消費性向、資本の限界効率表そして利子率は、互いに絡み合っていて、各々は他の変化が予想されると、その影響を被りかねない。しかしそれらはその値を互いに他から推測することができないという意味で、やはり独立している。重要な指摘である。重要だが経済というものがいかに複雑かということでもある。タフな思考を持っていないと放り出してしまうくらい複雑である。
では完全雇用達成のためにはどうすればいいのか?
ここで、異次元の金融緩和と緊縮財政の組み合わせは何をもたらすか考えてみよう。
緊縮財政は有効需要の創造を妨げる。その結果デフレの脱却は難しい。資本の限界効率が上昇しないときに貨幣量が増大すると、貨幣は希少性へと向かう。土地や金の価格が上がる。物価が上昇しないのに希少性を持つ(おいそれとは生産できない)資産の価格だけが上昇するのはこういう経路が存在するからである。政府・日銀が資産バブルを創り出そうとしている、と言われても仕方あるまい。
先き取りだが、公定歩合を引き下げれば貨幣量は増えるのだろうか?このあたりは、以後ケインズがみっちり解説してくれる。冒頭の問い≪なぜ価格によって資金の需給すら均衡すると考えてしまうのか≫に先回りして答えを与えると、つまらない、本当につまらないことだが、
素朴な常識に合致しているからである