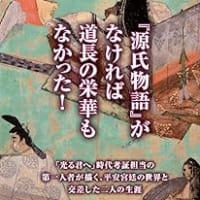毎日新聞記者で平成、令和改元時の報道に携わったのが筆者。日本における元号は大化元年に始まり、西暦701年の大宝よりは切れ目なく元号が継続している世界で唯一の国が日本である。明治維新までは天変地異や吉事、凶事などにより改元が行われたが、それ以降は天皇交代を元号改定の契機とする。昭和までは天皇制度が国体護持でもあり、天皇尊崇を国家国民の意思統一の象徴ともみなされたが、新憲法のもとでは、すべてが憲法による国民の意思の統治下に置かれることとなる。本書は、こうした歴史を振り返りながら、元号制定の意味と実際の制定に携わる学者、内閣担当者、政治家の関わりを解き明かした。
令和改元時に、安倍晋三首相がこだわったのが国書からの出典。直後の報道では、漢籍の易経からも「久化」、史記から「万和」、詩経から「万保」も提案されたというが、中国哲学者の宇野茂彦が提案したのが「英弘」「広至」。広至は出典の日本書紀の該当部分には徳、仁、という新天皇の名も入っていた。これは平成改元時に中国哲学者で茂彦の父精一が提案した「正化」にも典拠となった易経に「明」「仁」があったことと重なる。ただ、この重層的意味合いに官邸事務方や協議メンバーは気づいていなかっただろう、というのが筆者の読みだ。万葉集を典拠とする令和は万葉学者の中西進の提案であった。茂彦が元号制定の依頼を受けたのは元号担当だった官房副長官補伏屋和彦在職時の2002-2006年だったという。平成の天皇が前立腺がんの手術を受けた時期とも重なる。父の精一は1979年の元号法成立直後から考案者の一人として依頼を受けていた、というから親子が元号制定を巡って思いをつないできたと言える。実はその前の宇野哲人も中国哲学者であり元号制定には関わりがあり、平成を考案したのは山本達郎、令和は中西進ではあるが、宇野家の元号への関わりは長かった。
平成の制定時にも「生化」「修文」という案があった。最後まで絞り込まない、という方針を内閣では申し合わせていたのは、漏れても絞られていなければ、報道もされないだろう、という読みだった。漏れたときには、その案を本命としない方針もあったという。そこまで腹をくくるのなら、スクープ合戦など意味がないはずだが、記者としてはそうもいかないらしい。そもそも天皇が亡くならなければ新元号制定はないのだから、検討をしているというのは恐れ多いことでもある。しかし、一世一元を前提とし、皇位継承を改元のタイミングとする限りこのようなことは改元のたびに毎回起きることになる。平成の天皇が退位することで皇位継承が行われた令和の改元は一つの見直しの契機になる。天皇はもはや統治者ではなく象徴なのだから、改元期日も元号発表翌日ではなく、翌年1月1日と決めれば区切りも良いし、議論のための時間も取れる。官邸や事務方が事前に漏れた場合には「腹切り」覚悟の極秘検討を進める必要性はもはや薄れている、というのが筆者の主張。本書内容は以上。
1979年の元号法制定時には国会でずいぶん揉めた記憶があるが、それは推進派が日本会議や日本青年協議会であり、法律制定の裏側に戦前の天皇制復活を望む匂いが漂っていたから。現在の国民意識に元号と帝国憲法における天皇制の復活を感じる国民は少ないかもしれないが、それは戦後の昭和、平成の歴代天皇が平和主義と憲法尊重を身をもって国民の前で示し続けてきたことを、多くの国民が知っているからだろう。しかし現時点でも保守派主導の憲法改定の動きは継続している。「何が何でもGHQによる押し付け憲法は改定したい」という保守派の動きと、平和を願う国民意識との乖離は、昭和、平成の時代には大きかった。しかし令和の今、ロシアによるウクライナ侵攻を切っ掛けに、中国の動きとも連動して、憲法改定が世界の動きと繋がってきていること、強く感じてしまう昨今である。