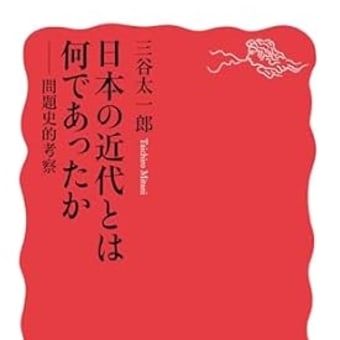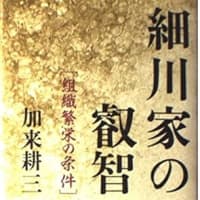タイトルの「逆襲」は特に内容を表すものではないようだ。神道についての理解を深めるための入門書である。
日本では、古来から折に触れて神様が地上の我々の周りにおいでになることがある。例えば、種まきや収穫、大晦日やお正月など。それ以外にも、「神がかり」などという言葉は、予想もしないときに神様が実在する人物の身体を借りて現実社会に作用を及ぼすことを表す。つまり、神は身の回りに始終いるわけではなく、必要な期間、来て去るまでの一定時間として人々には経験される。この神を迎えお送りする過程の形式化が祭祀であると考えられる。祭祀の固定化がお祭りであり、お祭りを通して民衆の間に神の存在が定着する。繰り返される祭祀を通して、神の経験を反省する中で神道の教説が生まれた。神道は民衆の生活その者であるのだから、教義は不要であるという考え方もある。本居宣長である。
本居宣長は、「仁義礼智信」のような体系だった教えが神道にはないのではないか、とする儒教者からの神道批判に対して、そうした理屈は理屈が必要なほどまがまがしい国だったからこそ理論的背景が必要とされたのであって、我が国のように、神の御心のままに人智によるこしらえ事がなくても道が実現できる世の中では、体系的な教えなど必要としなかったと「直毘霊(なおびのみたま)」で主張する。しかし宣長は決して神道の教義的体系を否定しているわけではない。
伊勢神宮には外宮と内宮がある。天照大御神をお祀りする内宮と豊受大御神をお祀りする度会の宮、外宮である。内宮は垂仁の皇女倭姫命が天照大御神の託宣に基づいて神霊を祀ったと日本書紀には記されている。外宮は雄略の時代に天照大御神の夢告にしたがい丹波国から迎え奉ったと古事記に記述されるが日本書紀にはその記述はない。二つの宮が象徴するのは神道の表裏、二面性を象徴しているとも言われる。日本書紀が表す天照大御神とその前の最初の神とされる国常立尊(くにのつねたちのみこと)の系列は天皇の系列であり、世界の現状を表す。古事記が記述するのは裏の神道系列であり、豊受大御神の先祖天御中主尊(あめのみなかぬしのみこと)は天照大御神を太陽とすれば月であり、表の世界の鏡である。外宮は裏、内宮は表の世界の象徴である、という世界観である。
日本は神の国である、という記述は日本書紀神功皇后の巻に表れ、鎌倉以降は各種文献にも記されている。この意味は、1.神の祭祀が優先される国 2.神が守護する国 3.神の後裔である天皇が治める国。 仏教や儒教に対応して語られるのは1,2であり、外敵に対応する場合には2,3である。蒙古襲来や太平洋戦争では2,3で使われた。「日本は神の国」という発言が問題視されるのは、太平洋戦争での2,3の使用が日本を戦争へと導いたという記憶が生々しいためであり、神道思想そのものに問題があるわけではない。
日本に古来から伝わるお伽話には5つの類型があるとしたのは柳田国男である。桃太郎、猿蟹合戦、舌切雀、花咲か爺、カチカチ山である。共通するのは「普通の人ならば格別重きを置かぬことを馬鹿正直に守っていた老翁だけが恵まれ、それに銘々の私心をさしはさんだ者は皆疎外されたということ」正直なものが福を得る、ということだ。正直が神に愛されるものの条件であり、勤勉とか忠義ではないということ。3年寝太郎や物ぐさ太郎では徹底したサボりであり、嫁を取らない若者の一人暮らしも進められた道徳的態度ではない。老母を家に残したまま亀に連れられ竜宮城に行く青年も刹那的遊び人であって、けっして万人に進められるような態度ではない。しかし正直なのだ。「正直の頭に神やどる」。子供の目は正直、という場合もある。川の上流から流れてくる桃や、捨てられていた白犬、イジメられている亀などは非日常であり、それを拾ったり助けたりすること、神を受け入れるというのは、非日常が突然現れた際にもそれを受け入れる態度として称揚されているという筆者の指摘である。
吉田神道は卜部神道、唯一神道、元本宗玄神道ともよばれ律令制度の神祇官の下級官人であった卜部氏の諸伝承を集成してできた神道の一派である。デカルトが「我思う故に我あり」、とすれば「我祭る、ゆえに我あり」というのがその思想。その理論は仏教や易をはじめ様々な思想の雑多な受容の上に成り立つものであり、世俗世界を超越した形而上学が説かれる一方、対世間的な対応では現世利益的、権力志向的な世俗性を引きずっているものではあるが神道思想の展開の足がかりを準備したことは否定できないとしている。
神儒一致の流れをくむ垂加神道は山崎闇斎から渋川春海、正親町公通、平田篤胤へと展開された。山崎闇斎によれば君臣関係は親子関係より根源的なものとされ、他の儒学者が親子関係を基本としたのと対照的である。神道の教えとは土金の伝授である、としたのは闇斎の弟子の浅見絅斎、物質的元素である土と金によって人間存在を説明、それが神代神話を主題を形成するというもの。土が締まることで万物は生じ、金で土は締まる。土が締まるとはつつしみであり、金が締まるとは金が土の中に兼ねてある、という五行思想の付会的解釈である。垂加神道では朱子学的君臣道徳に基づき封建的秩序を守ることが求められた。つまり神道とは言っても君臣、親子、夫婦、兄弟、朋友の五倫の道を守ることに尽きるのである。天照大御神はその道徳の体現者であり象徴である。
国学・復古神道の系図で言えば、荷田春満から賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤と系図は続く。思想の中には武(いづ)と和(にぎび)があり、須佐能は武を象徴し、天照大御神は和を象徴する。本居宣長の古事記解釈によれば、イザナギとイザナミによって創成されたこの世界は天照大御神、月読命、須佐之男命の三柱の神によって分掌統治された。イザナミは火の神を産んで黄泉の国に去る。顕の世界は表の世界であり、これを支えるのが天照大御神でありその子孫である天皇である。幽の世界は裏の世界であり黄泉の国、これを支えるのが神道であり大国主命である。大国主命の主宰する亡き母の世界が人間存在の地平となすというのが本居宣長の世界観であった。平田篤胤もこの神道の思想に大きな影響を受けた。
結局元の2元論に戻るようである。仏教や儒教のような仁義礼智信などの思想的価値理論というより、父母、君臣のような関係の中に尊敬の思いを抱くという感情的価値観に根源を発している気がする。戦争遂行のために利用された忠信孝悌は別にして、重要な価値観は日常生活のなかで教えられる、というのは日本人にはぴったり来る。「親は大事にしよう」「先祖は敬うべし」「嘘は泥棒の始まり」「人に迷惑をかけるな」「早起きは三文の得」などなど、いずれも日常生活の教えであり、親子、兄弟、朋友への感情を基礎としている。神様が基礎にあり、それは日本人の誰もが持つものであり、その上にホトケや儒教、人によってはキリストの教えが積み重なっているとも考えられるのではないか。神道の逆襲と言うよりも、神道は浸透済み、という感じ。