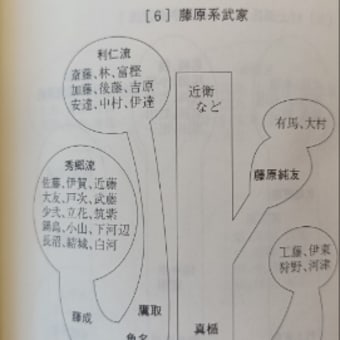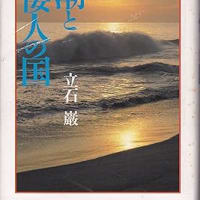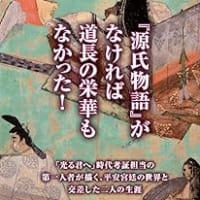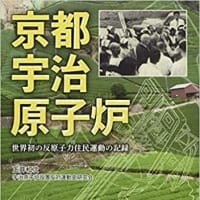人間の記憶というものはあてにならない、それも相当に他人の影響を受けることがある。アメリカで一時ブームになった幼児の虐待記憶を呼び覚まして両親を訴えるという話、カウンセラーに乗せられてカウンセラーに聞かされた話を本当に経験したと思いこんでしまい、両親を訴えてしまう話にはゾッとする。それもニセの心理療法を施されて。記憶の植え付けはこのようにしてできるという実験もあり、記憶と想像の境界線は曖昧だということが実証されている。
犯罪を犯したとされて警察に勾留されて尋問されるうちに、実際には犯してもいない犯罪の、本当に自分が犯人であると自白してしまうケースが有る。何回も同じストーリーを聞かされるうちに、この状況から逃れたいという心の弱さとともに、自分に自信が持てなくなり本当にあったことだと思いこんでしまうことはあるという。
裁判などで採用される目撃者証言にも危うさがあるという。事件の目撃者でも、実際に自分の目で見たことと、その後のニュースなどで見聞きしたことは時間とともに混じり合い、報道されたことも自分が見たことと錯覚するケースはママあるという。その結果、犯人とされた容疑者を見てもいないのに自分も実際に見たと思い込んでしまうこともある。
質問の仕方や、外からの情報で記憶は容易に書き換えられ、そのことに本人も気が付かない事が多い。情報源は信頼できるのかどうかが、記憶の確かさに関係していて、情報源を忘れてしまうと、その記憶が確かなものか曖昧なのかもわからなくことが多い。そして記憶は辻褄が合う方向に変化していくことが多い。記憶を確かなものにするためには、いつ、どこで、誰から、などという付帯情報をしっかりと記録しておくことが重要だという。
また、強烈な犯罪の目撃者の証言は、その犯罪の残虐さや凶暴度合いが高いほどあてにならないことが多いという。なぜならば、目撃者の意識がその凶暴さや残虐性に向かっていて記憶がいがんでしまうことが多いからだと。
また集団で一つのことを議論して結論を出す場合、その結論はリスキーな方向に行きやすいという。三人よれば文殊の知恵、というが、人数が多いと気が大きくなり、成功したプラス面に気が行きやすい。その結果リスクに対する慎重さが減少し冒険的な決断に走りやすいと。
どこかの国の大統領選を思い浮かべてしまうのは私だけだろうか。裁判員裁判で、市民が判断に参画するケースや証人尋問をする場合もあると思うが、こうした記憶の曖昧さに関しても十分留意することが重要。しかし、この歳になり、小中高大時代の同窓会に参加していつも思うこと、それは、忘れることは人生の幸福に大いに貢献していると、思うのだが。