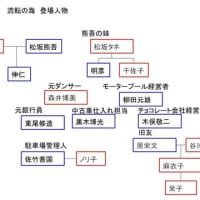人類は、地球上に誕生して以来、狩猟、農耕、産業化、文明化とその歴史上すべての局面において、生活環境から生物的、地球環境的な多様性を排除し、その結果様々な感染症や免疫異常、はたまた他の種族との戦争の頻発をも生むことになっている、という仮説。
まずは寄生虫。人類はその発生以来数百万年をかけて病気に対応する手段を身に着けてきた。それは自らの免疫力と自然界とその他の生物を利用すること。ミトコンドリアを細胞の中に取り込んだ話は有名だが、ほんの百年前まではすべての人の体の中にいた回虫、蟯虫、絛虫などの寄生虫や腸内にすみつく菌が、人類の健康維持にどのような役割を果たしてきたかの研究はまだ始まったばかり。現代の都会では、開発途上国にはない新たな病気が多数存在する。多くは自己免疫疾患とアレルギー疾患である。本書では具体的には免疫システムが自分の消化器官を攻撃するクローン病をあげている。その結果、腹痛、発疹、関節炎が引き起こされる。その治療法として本書が上げるのが回虫である。実験的に回虫を体内に取り込む治療をすると、クローン病の患者が寛解するという。寄生虫が人類の免疫機能に重要な働きをしているのではないかという。数百万年かけて人類が手に入れた健康維持の仕組みを、抗生物質や法毒液で台無しにしてはいないかという問いかけである。
寄生虫は人類が排除した自然多様性の一部、象徴的な指摘にすぎない。虫垂の役割は腸内に住む菌の一次避難場所である、というのがもう一つの説。腸内の細菌がいなくなると人は消化活動を果たせなくなる危機に陥るため、何らかの理由で腸内菌がいなくなる際には、虫垂が避難所となるというもの。腸内に多数存在する菌、生物は他の生物との相利共生状態にあり、無菌環境では多くの生命体は生きてはいけない。
牛乳を人間が飲むことは、自然ではないためもともと人類としては牛乳の成分ラクターゼを乳児期間が終わると消化できなかった。しかし、欧州人を中心として飢饉時に牛の乳を飲むことで飢餓を逃れた遺伝子が生き残り、現代では多くのヨーロッパ人、アメリカ人はラクトースによる牛乳成分分解能力を持つ。(アジア人の多くはこの能力が弱いため現代でも牛乳を飲むとお腹の具合が悪くなる人が多い)これは農業にも当てはまり、もともとは狩猟生活で定住していなかった人類が、農耕開始にともなう定住生活により、芋やキャッサバ、稲、小麦など一定の農作物を消化する能力に長けてくる。これは多様な木の実を食べる生活から僅かな種に依存することになり、一見農耕により多くの人口を養えるが、一方で、食生活が変化し消化器官疾患が増え、狩猟時代よりも短命になったという。ではなぜ狩猟生活を離れたかというと、人口が徐々に増えてくると狩猟でまかなえていた食料が不足し、一定面積あたりで獲得できるカロリー数がより多い農耕生活を選ばざるを得なかったからだという。定住生活により、同時にノミやシラミ、蝙蝠など寄生動物に悩まされるようになる。
人類が体毛を失ったのは、体毛に巣食うシラミやダニなどの寄生生物によってもたらされる感染症と体温の保持とを天秤にかけた結果であった。一定の場所で生活するとシラミなどの寄生生物に狙われる確率が高まる。そして感染症にかかる確率も高まる。体毛を失うと、紫外線に晒され肌にはメラニンが生成され、肌の色は黒くなった。しかしその結果、黒色は日光を遮り、さらに居住地域が赤道から北に移動するにつれて日光が弱くなり、結果ビタミンDが欠乏するため再度肌の色を白くした。それと同時に人類は衣服を発明した。シラミは再び衣服に住み着くようになる。第2次大戦以前の戦争で戦士した軍人は弾丸よりも感染症などの病気でより多く戦死した。感染症とは赤痢やシラミによって広がった紅斑熱である。
霊長類や人、特に人の子供は動物の中では狼、ヒョウ、トラ、熊、サメ、蛇などの捕食者から見れば獲得しやすい動物である。サバンナザルは「ヒョウ」「ワシ」「ヘビ」という3つの言葉を持っているという。人がヘビを怖がるのは人類歴史を通して最も捕食されてきた結果なのかもしれない。人類の祖先も最初の言葉はこの3つ、そして「走れ、逃げろ」だったのではないかと推察する。霊長類(人も含む)の出産が夜中に多いのは、昼間は狩りに出払っていない家族が身近にいてこうした捕食者から守られる可能性が高いからだそうだ。
外人恐怖症(Xenophobiaキセノフォビア)も他所の国の人間によりもたらされる新たな感染症を防止する本能から来ているのではないかと筆者は考える。グルーミングをする動物にはさる、牛、レイヨウ、鳩などがいるが、それば互いの体から病気の原因となる寄生生物を取り除くため。また、病気が蔓延する地域の人々ほど排他的な行動を取るのではないかとまで筆者は考える。H1N1が世界的に蔓延した時に人々は旅行を控え、握手やキスをしなくなった。病気の人の写真を見せただけで、人は体内の免疫システムであるサイトカインを多く生成するようになるという。私達の文化的行動と呼ばれるものの多くは、広い意味での免疫的行動なのではないかと。
味覚には美味しいと感じる甘さと旨味、まずいと感じる酸っぱさと苦味、そして中立なのは塩辛いである。これは人類が生き残る上で重要だったはず。また人類歴史では不足してきた脂肪分やタンパク質も多くの場合には人は欲する。排泄物の匂いは遠ざけるし果物の匂いは大好きである。甘みはサトウキビやとうもろこしからいくらでも作り出せる現代において、こうした味覚はどのように作用するのだろうか。人が自然の風景、特に青い空や海、広い草原などを見て気持ちが良くなるのは決して湿地帯や薄暗い森ではないこと、物陰からトラが飛び出てきそうな景色ではないことをよく噛みしめる必要がある。地球環境の多様性回復は、人類が生き残る上で必要なこと、これは理解しているつもりであったが、実は人は自分の周りから他生物多様性を排除してきた歴史があったこと、これには気づかなかった。今後、人類はこの矛盾とどう折り合っていけば良いのだろうか。