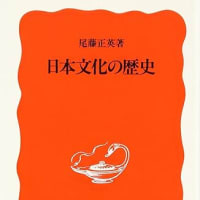筆者は日本と韓国の大学で朝鮮半島の歴史を学び、歴史民俗博物館の准教授を務める。倭国における古墳時代(三世紀後半から六世紀前半)における朝鮮半島南部の勢力と倭国勢力の関係について、朝鮮半島南部、そして日本の瀬戸内海にも点在する古墳群から分析した。
従来は、日本書紀の記述や広開土王碑の文言より、倭国ヤマト政権が朝鮮半島南部に任那と呼ばれる地域を勢力範囲に収め、百済、新羅と綱引きをしていたところに高句麗勢力に攻め込まれてきた、というような分析があったが、1970年代に資料の信頼性が見直され。大和朝廷による任那支配は存在しなかったとされている。本書では倭国でも朝鮮半島でも古墳時代には新羅、百済や大和政権の中央政権の力は限定的だったとする。倭国では吉備、北九州勢力がヤマト政権と覇を競い、朝鮮半島では半島南部の任那と考えられていた地域に大伽耶、小伽耶、阿羅伽耶、金官伽耶などの勢力と百済、新羅が勢力争いをしていた。
日本では、古墳時代の雄略7年に吉備田狭が新羅と結んで、ヤマト政権に対して起こした吉備の乱や、継体21年に朝鮮半島南部に出兵しようとするヤマト政権軍を北九州の磐井がはばみ、物部氏によって鎮圧されたとされる磐井の乱があった。これらの戦いを通して初めて、ヤマト勢力が瀬戸内海地方、そして北九州地方を支配下におさめることができたが、その間、吉備、そして磐井の勢力は朝鮮半島の新羅や百済、伽耶諸国との関係を模索していた。一方、伽耶諸国も百済や新羅に併合を迫られる中で、倭との関係をアピールすることにより、倭との関係も重視したい百済や対立する新羅とのバランスを図ったという。実際、瀬戸内地方の古墳群には朝鮮半島の百済や伽耶諸国の副葬品が多くみられ、逆に伽耶諸国にみられる古墳群には日本固有とされる前方後円墳や百済、新羅の副葬品も見られる。
結局、ヤマト政権が対外交易ルートとして朝鮮半島との関係を確固たるものにできたのは6世紀前半で、従来の説よりもずっと遅い。それまでは新羅や百済、伽耶諸国との関係をベースに北九州を支配下に置いていた磐井の乱を収めたことが政権としての基盤を確立したきっかけであった。ヤマト政権もそのころは武烈の後継を巡って北陸から継体を擁立した勢力と、奈良地方の従来の勢力がしのぎを削っていた時代であり、任那支配どころではなかった。本書内容は以上。
本書内容を的確に表す表題は「朝鮮半島南部に点在する古墳と副葬品から見た倭国との関係」ではないかと思うが、それにしても朝鮮半島に多数存在する古墳からこうした推論を組み立てた力は素晴らしいと思える。古墳時代に関する倭国側の資料は7-8世紀のヤマト政権勢力編纂による古事記、日本書紀と風土記しかないのであり、朝鮮半島の歴史にも謎が多いとすれば、こうした古墳と副葬品による分析を両国歴史家が協力して行うことは有益なはず。今後の研究継続を期待したい。