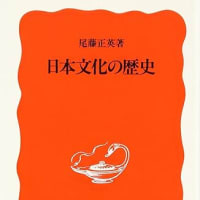戦後日本の政治対立は、主には安保と日本国憲法であった、と言える。単純化すれば、保守本流は護憲で安保推進、保守でも戦前回帰派は憲法改正して再軍備推進、左翼は護憲で安保反対である。しかしそもそも、象徴天皇とは、連合国の強硬派から天皇を守る国体護持のための方便であり、それと引きかえに、二度と戦争は引き起こしませんから、という約束を東京裁判の前に新憲法制定という形で担保しておくというのが戦争放棄の第九条だった。憲法は占領軍に押し付けられた、という見方かあるが、敗戦国として必死の交渉の結果、勝ち取れた最善の成果だったと考えられる。安保条約はサンフランシスコ講和条約とのペアであり、その大前提は現行憲法であった。
実質的にはアメリカ軍を主体とした占領軍は、軍国日本の徹底した非武装化と民主化の浸透を主眼に、マッカーサーの五大改革(労働改革、財閥解体、教育改革、農地改革、選挙改革と民主憲法制定)を占領後二年間で一気に実行した。そうした改革への評価は、1951年にマッカーサーが解任されて日本を去る際に、銀座から羽田空港迄道の両側に見送りの人垣が切れ目なく続いた、国会ではマッカーサー元帥への感謝決議が行われた、などという事実から推し量れる。更に東京湾にマッカーサーの像を建てようという提案まであったというが、マッカーサー帰国後の、「日本は十二歳レベル」発言で一気に人気は萎んだという。
憲法草案を検討する際に、人権尊重、地方分権、男女平等、労働者の権利、言論の自由などという基本的理解が当時の日本政府にはなかった。ここまでの理解不足を予測していなかったGHQは、検討指示後に毎日新聞が日本政府の憲法草案をすっぱぬいた時にはじめてこのままではまずい、と悟ったのだが、天皇を戦争犯罪人にすべきという極東委員会の発言力が強い東京裁判の前に制定というには時間がなかった。そこで九日間で作成した下書を日本側のメンバーに示して、それを日本政府の草案として発表させたのである。当時の日本政府にも強い抵抗があったが、天皇の地位を守る、ということを最優先事項と考えていた幣原内閣はこれを受け入れた。進歩、自由両党は、天皇制維持、基本的人権尊重、戦争放棄は自党案と一致すると評価、共産党以外の政党は賛成に回ったのである。
しかし、その後の世界的状勢は変化し、朝鮮戦争、中国革命、米ソ対立とアメリカにとっての日本の位置づけが変わってくる。日本の再度の軍備推進を進めたいアメリカに吉田茂は当時の社会党を使って抵抗した。経済的復興優先のため、軍事力は最低限に抑えたいと。GHQは朝鮮戦争への支援のために警察予備隊を結成させた、しかし日本の再軍備に敏感に反応するオーストラリア、ニュージーランド、フィリピンへの配慮も重要だった。アメリカはダレス国務長官が連合国を訪問してポツダム宣言をベースにしたサンフランシスコ講和条約を日米安保条約と戦争放棄条項のある日本国憲法、東京裁判の受け入れを前提にして締結することを説いて回った。
米ソ対立、共産主義への警戒感、北京政府未承認などから、サンフランシスコ講和条約には、連合国49ヶ国が参加したが、ソ連、中国、その他の東側の国は参加しなかった。講和条約締結により、日本は独立を勝ち取り、国連への加盟も認められたが、その代償は、台湾政府を中国として国交回復する、安保条約の実行のため期限の定めなく米軍に基地の提供をすること、沖縄はアメリカの施政権下におくことであった。中国とはその20年後に国交回復、沖縄も返還されたが米軍基地はたくさん残っている。
ここからが現在の問題である。基地の問題に憲法改正、などが選挙の争点になろうとしている。我々が今考えるべきなのは、こうした歴史的背景を知った上で日本の安全保障をどうするのか、そして国際社会で信頼されながら貢献できることは何かであろう。平和が第一、これに反対する人はいない。しかし、ドナルドトランプが大統領になり、尖閣諸島に人民軍が上陸してしまってから考えるのでは遅すぎるはずだ。憲法と安保、性根を据えて考え直すときが来ている。