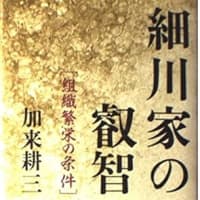古代から中世までの日本史を怨霊、祟り神などを中心とする視点から見直してみよう、という本書。荒神スサノオノミコトや牛頭天王、菅原道真、崇徳院などが有名どころだが、こうした物の怪、妖怪などの歴史視点は、人間界を俯瞰するようで大変勉強になる。歴史書は人間の視点からしか書かれていないが、その人間たちはこうした怨霊や物の怪を恐れるあまり自分の行動を大いに変更し大変な影響を受けてきたからである。
「ひとつ火」はイザナギノミコトが黄泉の国に行ってしまったイザナミノミコトを追いかけていったときに、その姿を見ようとして灯してしまった松明代わりの明かり。禁忌の光に蠢くのは観てはならない妻のケガレた姿であった。古事記であるが、日本書紀では火の神カクツチを産んだためイザナミは死んだが、カクツチは粘度の神埴山姫と結婚してワクムスビの神、つまり蚕と桑、五穀が生まれる。火は死を通して豊かに再生、火は聖なる火と不浄火の区別があるとする。ケガレた葬式、出産などの火と祭りの夜に焚かれる松明や篝火、仏壇や墓に供える蠟燭、お盆に焚く迎え火と送り火。ひとつ火は嫌われた。
目が一つの鬼は、ギリシャ神話ではキュクロープス、風、嵐、雷、蛇などを象徴する神である。破壊をもたらすが、その後には再生がある。スサノオが戦った八岐の大蛇の「8」は数多く数えられないほど多い象徴である。7までは数えられる。七代祟る、初七日、嘘八百、八百八橋、八重桜、八百屋など。三種の神器は、八咫の鏡、八尺瓊勾玉、八束の剣で、こちらは美称。八岐の大蛇は破壊と再生産を象徴していた。
書紀に記された倭迹迹日百襲姫命と大物主命の神婚説話。大物主命は夜にしか来ないので顔がわからない。顔を見たい姫は朝までいてほしいとお願いすると、大物主命は櫛笥(くしげ)の中に隠れるので、姿を見ても驚かないように諭す。翌朝、櫛笥の中にいた蛇に驚いた姫は大声で叫び、尻餅をついた拍子に女陰を箸で突いて死んでしまう。神は御諸山に雷を轟かせながら帰ってしまう。そして姫の墓は箸墓と呼ばれる古墳となる。姫は神と子も成している。類似のエピソードは「流れ矢伝説」とも重なる。蛇や雷が神の正体、というお話や、放たれた矢を拾った女性が妊娠して子をなす、神の正体を見ることで関係が断絶する物語は多い。蛇神は雷神、つまり恐れる対象であり豊穣を約束する神でもあった。祟り神は祭祀の方法を間違うと災いをもたらすが、正しくお祀りすると豊穣をもたらす。
秦氏は養蚕紡績、須恵器生産、交易、農地開発、鉱山開発などの先進技術を列島にもたらした渡来系氏族であるが、おなじような「流れ矢伝説」が伝えられる。秦氏は松尾、賀茂別雷、賀茂御祖の三明神を氏神とする伝承である。秦氏の女子が川を流れてきた矢を拾って妊娠、出産したので、両親は誰が相手だと怪しんで宴に人々を招き糺す。するとその子が矢を指差し、矢は雷神の姿に変じて昇天。秦氏も雷神の子孫、というエピソードである。僧景戒による日本霊異記にも雷神伝説があるが、景戒が尊敬した行基の後援者が秦氏、伝説は現状を人々に認識させ、リーダーへの尊敬を獲得する手段でもあった。その行基は山林修行を実践、山林修行とは仏教、道教、陰陽道、神祇信仰を習合させた呪術性の強い修験道であった。朝廷側から見れば邪教集団のリーダー的存在でもあり、秦氏としては微妙なバランスを取っていたのかもしれない。
乙巳の変で蘇我入鹿を殺害した中大兄は、蘇我馬子が物部守屋を滅ぼしたあとに建立した元興寺(法興寺)に入り、ここを砦として蘇我氏と戦う準備をした。法興寺は真神原と呼ばれ大ケヤキの立つ聖地に建てられており、蘇我氏の氏寺から天皇家の寺となる、聖地奪還の象徴でもあった。平安時代の今昔物語には本エピソードのバリエーションもあるが、仏教の力を誰が支配するか、それを政権正当性の象徴としたかった、という説話である。法興寺には大ケヤキ、化人、雷神、水神、鬼の頭髪など数多くの説話が伝えられており、こうした説話を通した恐れとご利益をペアとしたエピソードを通して信仰を政権支持に繋げようとする共通点がある。
聖武天皇が仏法による国家再編成を進めていた折、729年、長屋王は謀反の疑いをかけられ妻子ともども自害に追い込まれた。一族の遺骸は平城京の外に焼き砕かれて捨てられ、海にまで撒き散らされた。遺骸が流れ着いた土佐では疫病で多くの死者が出たため、長屋王の存在を排除しようとした藤原不比等は長屋王の怨霊に恐れを抱くことになる。その後、不比等の4人の子たちは要職を占めるようになるが、冤罪に関わった者たちを含め、太宰府から広まった疫病で次々と死んでしまう。
聖武天皇亡き後、不比等の娘光明皇后と藤原仲麻呂が実権を握る。仲麻呂の専横に反発したのが橘奈良麻呂、王臣たちを集ってクーデターを企てるがことごとく潰され、奈良麻呂をはじめ、大伴古麻呂、小野東人、道祖王、黄文王は拷問の末に命を落とす。仲麻呂は彼らの祟を恐れたので、そうした噂を流す者たちに同罪に処することとする。奈良麻呂に連座したのは443人もいたが、その後大赦により262人が赦された。怨霊への恐れは長く続いた。
神の祟りが疫病をもたらすという考えは、神武天皇の熊野神の祟り、大物主命の祟りなど古くからあった。疫病は鬼神からという考えは陰陽道、仏教の影響を受けた。陰陽道は道教、風水、呪禁(じゅごん)、密教、密教天文学などのミックスである日本独自の体系。孝謙は奈良麻呂の乱後、淳仁天皇に譲位するが、道鏡を重用して淳仁天皇を廃帝し淡路に流す。廃帝の呪いがこれ以降発生することは言わずもがな。称徳の後継の親王が次々と流罪になり、誅殺されたりし、道鏡がその地位につこうとするのを阻止したのが藤原氏が手配したとされる宇佐八幡宮の神託。この流れの中にも多くの呪詛や怨霊が飛び交う。
そして、藤原氏が道鏡を追放した称徳の遺言をでっち上げてまで即位させたのが光仁天皇、天武系から切り替わる天智天皇の孫である。光仁天皇の后は聖武天皇の娘、井上内親王、その子は他戸親王で正統性はあるが、天皇を呪詛したとされ廃帝、廃太子され毒殺される。代わって皇太子には光仁天皇と百済王の子孫高野新笠の子、山部親王、のちの桓武天皇である。こうした謀略の影には多くの怨霊と呪詛があり、陰陽道はその中で大きな役割を果たす。
怨霊は貴族社会で生まれ育った。仏教や陰陽道は権力を求める人達に利用されたのは当然とも言える。不作、不漁、疫病、不意の死などを鎮めるために、怨霊を鎮めるとされる御霊会、大祓、神宮への奉幣、護国経転読、写経などが行われる。こうした御霊会で生まれたキャラクターの一つが牛頭天王であり祇園祭、神泉苑での御霊会など。そして菅原道真、崇徳院という巨大な怨霊が誕生する。
武士の誕生のきっかけとなる保元の乱の原因の一つともされる崇徳天皇と後白河天皇の諍い。崇徳天皇の父は鳥羽天皇、しかし本当の父は鳥羽の祖父である白河院と鳥羽に嫁がせた待賢門院との間にできた子だったとされる。白河院が溺愛する崇徳に譲位させるため、鳥羽を退位させる。白河院の没後、反撃に出た鳥羽院は、藤原長実の娘の得子を入内させ、その子近衛を即位させ、崇徳を退位させる。得子は美福門院と名乗り実権を得る。こうした諍いのプロセスで藤原摂関家内部対立も激化する。近衛が眼病で没後即位したのが後白河天皇、崇徳と同母弟である。後白河即位後の保元元年1156年、鳥羽の死をきっかけに崇徳院クーデターの噂が流れ、後白河天皇の命で、源義朝が藤原頼長を襲撃、呪詛の疑いから崇徳院を排除、義朝ではなく信西入道に支持された平清盛が勢力を得る。崇徳院は讃岐に配流、8年後に亡くなる。崇徳院は舌の先を噛み切って、流れる血で五分大乗経の奥に怨念を込めた誓いの言葉を記した。保元の乱の3年後、清盛の熊野詣のすきを突いて、義朝は二条天皇、後白河院を拉致しクーデターを起こし、信西入道は自害、平治の乱である。知らせを聞いた清盛は義朝を追撃殺害、三男の頼朝を伊豆に配流する。
崇徳院の怨念の力は強かった。1176年には関係者が連続死する。鳥羽と得子の子高松院、建春門院平滋子、後白河院の孫の六条院、近衛天皇の中宮九条院呈子、みな後白河や藤原忠通の縁者だった。翌年は京が大火災、崇徳院は道真と同様の怨霊となる。
長くなるので、このへんで内容記述を止めるが、本書には古事記、日本書紀から保元物語、太平記の時代まで、600年ほどの日本史をまとめた、祟り神、怨霊などの視点から記述された日本通史とも言える内容である。筆者の意図としてはその後も戦国、江戸、近代にまで記述を進めたかったというが、建武の新政あたりまでで文章量が多くなってしまい、ここまでで一冊の本とすることにしたという。歴史を怨霊の視点から見てみる、稀有な経験である。歴史好きなら一読の価値があると思う。