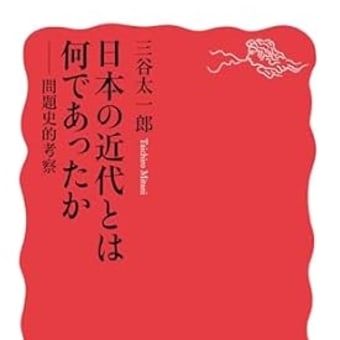古事記、日本書紀に記された事象を、単なる神話や天武持統王朝正当化の物語とせず、物語には史実があり、時代を考証しながら他の文献や手がかりとすり合わせていけば異なる真実が見えてくるはず、というのが本書のテーマ。縄文、弥生時代に大陸、半島、太平洋諸島から日本列島に流入してきた人々と、記紀記述との整合性を仮説を立てて考えてみたのが本書。
弥生時代以前、当時の日本列島には長く縄文人が住んでいて、徐々に大陸、半島、先島諸島から流入してきた弥生人たちと混血を初めていた。そうした弥生人たちの多くは戦争難民で、大陸での春秋戦国時代以降、稲作を始め、製鉄、養蚕、宝飾品加工技術などを持ち込む渡来人と呼ばれた。ジャポニカ米の遺伝子研究からは、短粒種である日本の稲作は揚子江流域の人々がもたらしたものと推測される。渡来人は戦争が激化するたびに波のように何回かの集団に分かれて日本列島に渡来してきた。漂着したのは、北九州、出雲、北陸、そして南九州と西日本の各地に上陸した。西暦で推定すると、紀元前473年の春秋戦国時代の呉滅亡、紀元前334年の越滅亡、紀元前210年ころの斉滅亡が、それぞれ北九州、出雲、南九州への渡来人漂着のきっかけになる。記紀でニニギノミコトと記述されるのはこうした中の一つであり、南九州高天原への天孫降臨物語は、こうした渡来人先祖の物語である可能性がある。魏志倭人伝に邪馬台国と記された国は、こうした集団が住み着いた地方の一つであり、倭人伝記述と流入歴史を符合させて推測すれば、日向平野宮崎あたりが邪馬台国に相当すると推察できる。
記紀に記述される神話時代のエピソードから、宮崎の集団は稲作と製鉄技術、武器を携えて、さらなる豊かな土地を目指し、瀬戸内海を東進、吉備、出雲を仲間に取り込みながら、大阪湾から大和平野に到達、大和政権の始まりとなった。これが西暦で言えば282年ころ、磐余彦改め神武となった東征エピソードとなり、纏向三代と呼ばれる崇神、垂仁、景行が西暦372年ころ、大和王朝の濫觴であると考えられる。倭の五王は413年ころから始まる王朝で、朝鮮半島進出、大土木工事による前方後円墳建設が見られたその後の応神につながる。飛鳥京遷都の允恭、万葉集の初歌とされる雄略が続き、男系が途絶えた直後の継体は西暦532年頃、そして593年の推古即位へとつながる。
筆者の仮説としては、先に編纂された古事記は日本書紀のテスト版で、乙巳の変で焼けてしまった帝紀や旧辞(くじ)の内容が誤って伝承されることを恐れた天武天皇が天皇お世話係であった稗田阿礼に覚えさせた物語が始まり。天武天皇崩御で一時中断したが、元明天皇の時代に再開、712年に大和言葉による叙事的歴史書として元明天皇に献上された。日本書紀は正式な国史として太安万侶に編纂させ、天武天皇崩御にも中断せず、国家事業として進行、古事記とは異なり、漢文表記で、720年に元正天皇に献上、第41代持統王朝までの30巻長編となった。本書内容はここまで。
多くの記述は筆者仮説に基づき、参考文献と引き合わせながら年代の整合性を取りつつ物語と歴史を紐つけているので、読んでいて不思議な納得感がある。多くん歴史謎解きでは、邪馬台国の場所、神話と歴史上の事実、卑弥呼は誰、倭の五王の正体、継体王朝の謎、などなど、謎だらけで終わるのが普通であるが、本書では大いなる仮説の上に一つの歴史として記述されているので、スーッと頭に入ってくる。権威ある歴史学者には「とんでも学説」と呼ばれているのかもしれないが、こうした仮説を考古学、生物学、DNA研究、稲作研究、民俗学など多方面から検証していけば、ただの自己主張の言い合い論争に終始しない歴史議論ができそうな気がする。