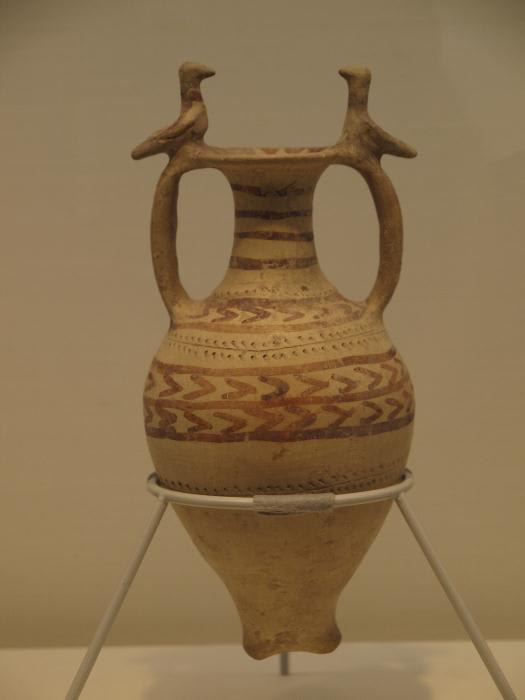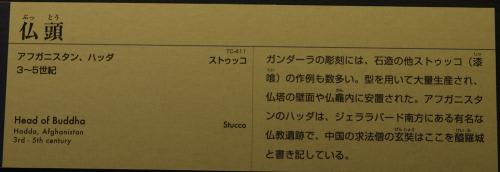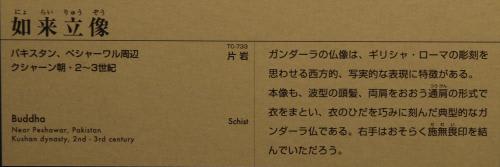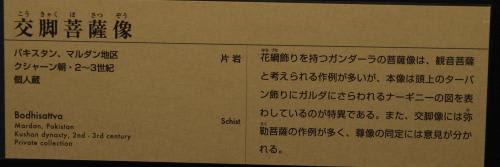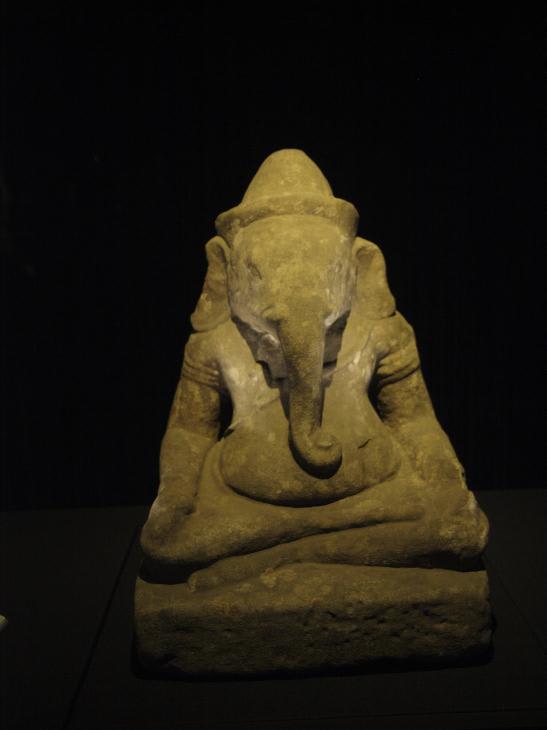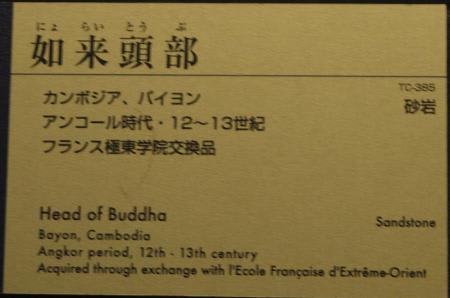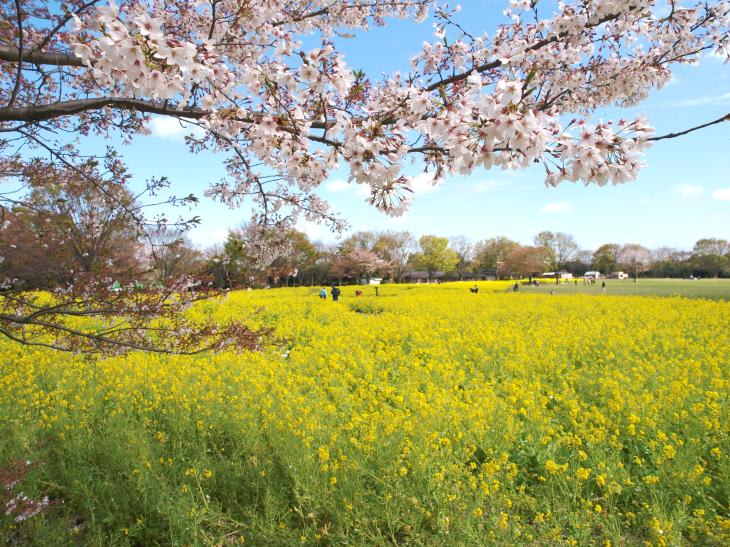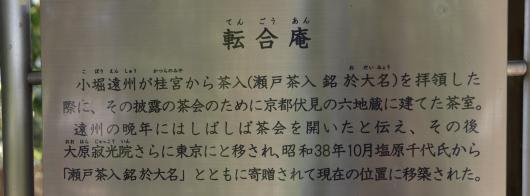アジアギャラリーも最後のエジプトです。 エジプトコーナは展示も少なく、紹介する作品も少なめです。

イニ像浮彫 エジプト独特の横向きの人面と正面を向いた身体は面白いし、表情もいきいきとしている。


婦人の頭飾り。 クレオパトラなどの映画でいろんな飾りをつけていたのを思い出します。

死者の身代わりで働く小像ウシャブティ。


婦人像となっていますが、見たときは何?と思いました。 よーく見るとモダンな髪形のデザイン性溢れる婦人像で素晴らしい。


最後にアジアギャラリーを展示している表慶館の紹介。 ドームのついた洋風の建物です。

ドームの中を下から。

入り口。

入り口から、博物館本館を見たもの。