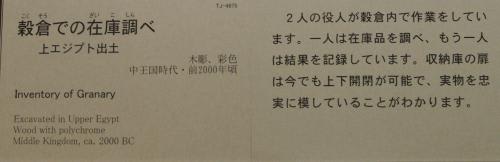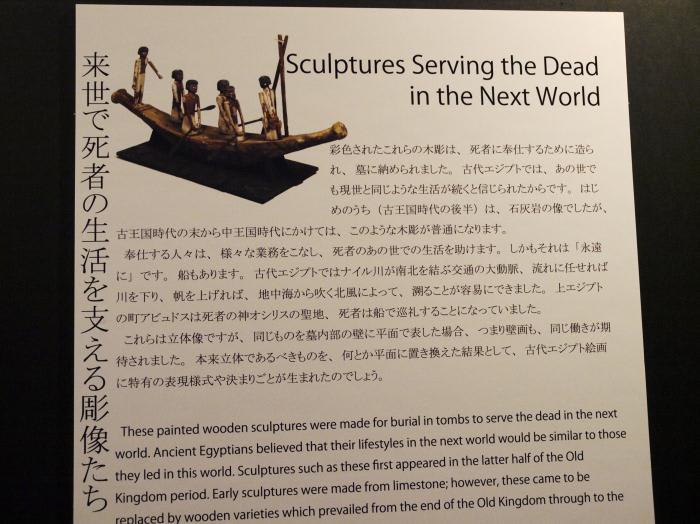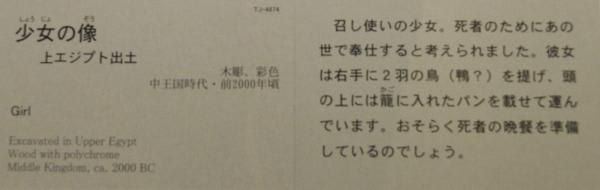久し振りにトーハクの表慶館で鑑賞。 以前、紹介していますが、いくつかは、展示品も入れ替わっているので撮ってみました。
まず、インド、東南アジアでインド文化の広がりをテーマにしたコーナ。
バイラヴァ立像 バイラヴァは恐ろしいものの意でシヴァ神の別名。 12~13世紀に南インドで造られている。 花崗岩

仏頭 アフガニスタン、ハッダ 3~5世紀 漆喰
ガンダーラの特徴が出ている。
交脚菩薩像




仏伝「初転法輪」 パキスタン、ガンダーラ 2~3世紀
釈迦が初めて仏法の教義を人々に説いた出来事をあらわしたもの。


顔の造りも東南アジアの雰囲気を感じます。


水牛の顔を見てピカソの趣を感じました。