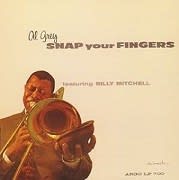ジャズ界にはソニーと名の付く人がたくさんいます。ソニー・ロリンズ、ソニー・スティット、ソニー・クラーク、ソニー・クリスあたりがパッと思い浮かぶところで、他にもソニー・レッド、ベイシー楽団のトランぺッターのソニー・コーン、ドラマーのソニー・ペインがいます。マニアックなところでは前衛系アルト奏者のソニー・シモンズ、ソウル系オルガン奏者のソニー・フィリップス、フィル・ウッズと共演したベース奏者のソニー・ダラス、70年代のマイルスのバンドにいたテナーのソニー・フォーチュンなんてのもいますね。ちなみにソニーと言うのは"坊や"を意味するニックネームで本名は全員別にあります(ロリンズはセオドア、スティットはエドワード、クラークはコンラッドetc)。
今日ご紹介する作品はその中でも"2大ソニー"と言っても良いロリンズとスティットをフィーチャーした「ソニー・サイド・アップ」です。タイトルは目玉焼きを意味するsunny side upのもじりです。サックス界を代表する巨人2人の競演と言うだけで十分豪華なのですが、リーダーは彼らではなくむしろジャケット左側にデーンと位置するディジー・ガレスピーでしょう。本作が録音された1957年12月時点で40歳。まだ長老と呼ぶような年齢ではないですが、若者が多いバップ世代の中では重鎮的存在でした。(ちなみにスティットは33歳、ロリンズは27歳)。リズムセクションは25歳のレイ・ブライアント(ピアノ)、その兄で27歳のトミー・ブライアント(ベース)、28歳のチャーリー・パーシップ(ドラム)です。

全4曲。アルバムはまずスタンダードの"On The Sunny Side Of The Street"で始まります。ソロ先発はソニー・スティット。スティットはこのアルバムではアルトではなくテナーサックスを吹いていますが、同じテナーのロリンズとはスタイルが違うので混同することはないですね。ロリンズに比べてスティットの方が明らかに音数が多く、フレージングが細かいです。スティットの後はガレスピーのミュート→ロリンズと快調にソロをリレーしますが、残り1分のところで突然ガレスピーが歌い出し、思わずズッコケそうになります。彼が時にヴォーカルを披露することは知ってはいましたが、ここで飛び出すとは・・・正直美声とも言えないし、音程も怪しい。独特のユーモラスな味わい、と言うのが最大限ひねり出した誉め言葉でしょうか?
続く"Eternal Triangle"はスティット作とありますが、どこかで聞いたことがあるようなバップナンバー。目玉は何と言ってもテナー2人の競演で、まずはロリンズ→スティットの順でソロを取り、その後は2人の熱いチェイスが9分過ぎまで続きます。その後でようやくガレスピーが登場し、ブライアントの短いソロ→ガレスピーとチャーリー・パーシップのドラムのソロ交換と続きます。なかなかド派手な演奏です。3曲目"After Hours"はブルースのスタンダード曲で、冒頭の3分間はここまで目立たなかったレイ・ブライアントの独壇場です。その後はガレスピーのミュート→ロリンズ→スティットとブルージーなソロを受け渡していきます。ラストは歌モノの"I Know That You Know"で、まずはロリンズが力強いテナーソロを聴かせた後、ガレスピー→スティットとソロを取りますが、何よりメロディを崩さずに速射砲のような勢いでアドリブを連発するスティットのソロが圧巻ですね。日本のジャズファンの間ではソニー・ロリンズは半ば神格化されていて、この作品もどちらかと言うとロリンズ目当てで聴く人が多いかもしれませんが、個人的にはスティットも互角かそれ以上の出来と思います。御大ガレスピーも歌はともかく?、プレイの方はさすがの貫録です。