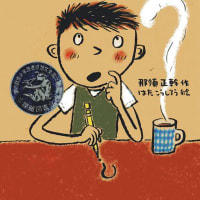三浦哲郎
三浦哲郎 新潮社文庫 400円
新潮社文庫 400円 1984年初版 1971年作品
1984年初版 1971年作品 『ユタとふしぎな仲間たち』 2007.8.7
『ユタとふしぎな仲間たち』 2007.8.7
「生きるって、生きているって、
なんて素晴らしいことなんだろう」
父を事故で亡くし、母に連れられ、東京から東北の田舎に引っ越してきた勇太。なかなか田舎の子どもたちとなじめず、退屈な生活を送っていた。ある日、水車小屋の寅吉じいさんから、銀林荘の離れにいる座敷わらしの話を聞く。満月の日にその部屋に泊まると会えるという。勇太が出会ったのは9人の座敷わらしたち。ペドロ、ダンジャ、ジュノメェ、ゴンゾ、トガサ、ジンジョ、モンゼ、ジュモンジ、ヒノデロ。離れの中央にある大黒柱がエレベーターになっていて、彼らの世界に連れていってくれる。彼ららの姿は勇太には見えるけど、他の人には見えない。
この田舎町で繰り広げられる勇太と彼ら座敷わらしたちの交友、そして勇太の成長。 大黒柱なんて残っているところは少ないだろうなあ。そんな大きな柱がある家は、きっと古い家で座敷わらしたちがいるような予感がある。生きたくても生きられなかった昔の子どもたち。そのままの姿で“今”をさまよっている。おむつのおしっこくさいにおい。きたならしいイメージだけど、見かけにこだわらない、素直につきあえる関係だからこそ仲良くなれる。いじめがおこるのは、見かけや言葉やちょっとした動作など、どうでもいいところにこだわるからだと思う。彼らと触れあいたいと思う心は、きっといじめなんてしないだろう。テレビなんかでやる座敷わらしのイメージとちがう。テレビの座敷わらしはそれなりにお上品な気がする。ものを動かしていたずらして楽しんでいる。でもペドロたちは悲しい過去と現代では決して受け入れられないような格好でイメージだ。ペドロたちが都会に来たらどんなことを思うだろうなあ。都会には都会の座敷わらしがいるのだろうか。悲しみを吹き飛ばすような座敷わらしじゃなくて、悲しみの置き所のない身動きできない幽霊になってしまうかもしれない。
大黒柱なんて残っているところは少ないだろうなあ。そんな大きな柱がある家は、きっと古い家で座敷わらしたちがいるような予感がある。生きたくても生きられなかった昔の子どもたち。そのままの姿で“今”をさまよっている。おむつのおしっこくさいにおい。きたならしいイメージだけど、見かけにこだわらない、素直につきあえる関係だからこそ仲良くなれる。いじめがおこるのは、見かけや言葉やちょっとした動作など、どうでもいいところにこだわるからだと思う。彼らと触れあいたいと思う心は、きっといじめなんてしないだろう。テレビなんかでやる座敷わらしのイメージとちがう。テレビの座敷わらしはそれなりにお上品な気がする。ものを動かしていたずらして楽しんでいる。でもペドロたちは悲しい過去と現代では決して受け入れられないような格好でイメージだ。ペドロたちが都会に来たらどんなことを思うだろうなあ。都会には都会の座敷わらしがいるのだろうか。悲しみを吹き飛ばすような座敷わらしじゃなくて、悲しみの置き所のない身動きできない幽霊になってしまうかもしれない。
音の風に乗って空を飛ぶペドロたち。帰りは歩きになることもある。田舎だからだなあ。都会の音は雑音だらけ。座敷わらしさへ居場所がない世界がさびしく感じられる。古い家がなくなった村を離れ、ペドロたちはどこにいくのだろう。解説にあったように、この続きが知りたい、読みたい、そんな気持ちにさせられる。