管首相が果敢にも消費税アップを明言したので、消費税について改めて考えてみた。
消費税=所得税+法人税
消費税と所得税・法人税はどこが違うか。前者は間接税、後者は直接税といわれ、全然違うように思われているが、よく考えてみるとそれほどでもない。
経理の実務では、消費税と法人税の扱いは実によく似ている。法人税は利益だけにかかるのに対して、消費税は利益+給与にかかるという点が主に違うだけである。ここから見ると、消費税は法人税と雇用税を合わせたようなものだ。企業から雇用税を取るのは、従業員から所得税を取るのと長期的には同じだから、消費税=所得税+法人税といってもよい。消費税をたとえば5%上げることは、法人税と所得税の両方を一律5%ずつ上げることと同じである。
ただし課税のタイミングは違う。一般に消費のほうが収入より一定しているから、消費税のほうが法人税+所得税より安定した財源になる。また一般に消費のほうが収入より地域偏在性が少ない。
消費税は資産課税
消費税には現在の金融資産を目減りさせる効果がある。稼いだときではなく使うときにかかる消費税は、まだ使っていない過去の所得・利益にも課税されるからだ。つまり、5%の消費税アップは5%の(一回限りの)資産課税でもある。
消費税は誰が負担するのか
消費税は消費者が負担するといわれるが、間違いではないだろうか。消費税は売買取引にかかる税であり、それを売り手と買い手のどちらが負担するかを論じても意味がない。
意味があるのは、せいぜい「消費税導入時に消費税分が価格転嫁される」ということだ。だから消費税の増税時にはその分だけインフレすなわち資産課税が発生することになる。
(欧米で「消費税」にあたる言葉は「付加価値税」(VAT: Value-Added Tax)だし、中国では増値税というようだ。消費者が負担するかのような名前を付けているのは日本だけなのだろうか。)
消費税の「逆進性」
所得税と違って消費税は累進課税ができない。だから消費税を上げるなら所得税の累進率を上げないと再配分の力は弱まる。再配分強化の手段として給付付き税額控除(負の所得税)はよい方策だ。
消費税の軽減税率は経済をゆがめる。たとえば食料に軽減税率が適用されれば、食料が過大に消費されて資源の無駄遣いになる。国民の行動を政府の意向で縛ることにもなり、よくない考え方の典型だ。どの品目に軽減税率を適用するかで政治的駆け引きも生じる。現在も家賃などの非課税品目があるが、これらにも軽減税率と同様に弊害がある。弱者の保護は、消費税率を複雑にするのではなく、累進課税の強化と給付付き税額控除に任せるべきである。
消費税は脱税しにくいのか
消費税は法人税よりごまかしにくいと言われるが本当だろうか。
たとえば売上100=仕入50+給与40+利益10の会社が、10の売上を申告漏れした場合、消費税10%なら減った税金は10の10%で1となり、法人税10%+所得税10%なら減った税金は法人税10×10%がゼロになるのでやはり1となる。経費の水増しでも同様の結果になるから、意外なことに、脱税への耐性は消費税でも所得税+法人税でも変わらない。
ただし、インボイス方式が導入されれば消費税はごまかしにくくなる。最終消費者に販売する事業者は依然としてごまかせるが、他の事業者に納入する事業者はごまかしにくい。いちいち紙のインボイスをやり取りするのは事業者にとって面倒だが、やはりインボイス方式はよい考えだ。ただし将来は、取引記録の電子化を進め、効率と捕捉率をさらに上げるべきだろう。
消費税はアングラ経済からも徴収できるのか
無申告の悪徳企業や暴力団は所得税・法人税を払っていないが、消費税なら(物を買ったときに)払わざるを得ない、と言われることがあるが本当だろうか。
残念ながらこれも正しくないようだ。消費税による商品の値上り分は、税金の預かり分というより、インフレと考えたほうがわかりやすい。たとえば消費税が5%上がり、すべての商品も5%上がったとする。悪徳企業の支払いは5%増えるが、売上も5%増え、利益も5%増える。ただこれはインフレ分だから、結局、悪徳企業は損得なしである。
以上、消費税について考えてみた。消費税と法人税・所得税とは意外に似ているが、消費税のほうが税収が安定すること、地域による偏在が少ないこと、資産課税効果があることを考えると、やはり上げるなら法人税・所得税より消費税だろう。相変わらず無駄の多い政府に増税させてよいかはまったく別問題であるが。
なお当然、現在の免税業者(課税売上1000万円以下)への益税はなくさねばならないし、いい加減な簡易課税制度(仕入れ比率見なし制度)もやめるべきだろう。
以上では国際取引をまったく考慮していない。次回は輸出入や法人税減税競争への影響を考えてみたい。
関連:消費税は逆進的か
消費税=所得税+法人税
消費税と所得税・法人税はどこが違うか。前者は間接税、後者は直接税といわれ、全然違うように思われているが、よく考えてみるとそれほどでもない。
経理の実務では、消費税と法人税の扱いは実によく似ている。法人税は利益だけにかかるのに対して、消費税は利益+給与にかかるという点が主に違うだけである。ここから見ると、消費税は法人税と雇用税を合わせたようなものだ。企業から雇用税を取るのは、従業員から所得税を取るのと長期的には同じだから、消費税=所得税+法人税といってもよい。消費税をたとえば5%上げることは、法人税と所得税の両方を一律5%ずつ上げることと同じである。
ただし課税のタイミングは違う。一般に消費のほうが収入より一定しているから、消費税のほうが法人税+所得税より安定した財源になる。また一般に消費のほうが収入より地域偏在性が少ない。
消費税は資産課税
消費税には現在の金融資産を目減りさせる効果がある。稼いだときではなく使うときにかかる消費税は、まだ使っていない過去の所得・利益にも課税されるからだ。つまり、5%の消費税アップは5%の(一回限りの)資産課税でもある。
消費税は誰が負担するのか
消費税は消費者が負担するといわれるが、間違いではないだろうか。消費税は売買取引にかかる税であり、それを売り手と買い手のどちらが負担するかを論じても意味がない。
意味があるのは、せいぜい「消費税導入時に消費税分が価格転嫁される」ということだ。だから消費税の増税時にはその分だけインフレすなわち資産課税が発生することになる。
(欧米で「消費税」にあたる言葉は「付加価値税」(VAT: Value-Added Tax)だし、中国では増値税というようだ。消費者が負担するかのような名前を付けているのは日本だけなのだろうか。)
消費税の「逆進性」
所得税と違って消費税は累進課税ができない。だから消費税を上げるなら所得税の累進率を上げないと再配分の力は弱まる。再配分強化の手段として給付付き税額控除(負の所得税)はよい方策だ。
消費税の軽減税率は経済をゆがめる。たとえば食料に軽減税率が適用されれば、食料が過大に消費されて資源の無駄遣いになる。国民の行動を政府の意向で縛ることにもなり、よくない考え方の典型だ。どの品目に軽減税率を適用するかで政治的駆け引きも生じる。現在も家賃などの非課税品目があるが、これらにも軽減税率と同様に弊害がある。弱者の保護は、消費税率を複雑にするのではなく、累進課税の強化と給付付き税額控除に任せるべきである。
消費税は脱税しにくいのか
消費税は法人税よりごまかしにくいと言われるが本当だろうか。
たとえば売上100=仕入50+給与40+利益10の会社が、10の売上を申告漏れした場合、消費税10%なら減った税金は10の10%で1となり、法人税10%+所得税10%なら減った税金は法人税10×10%がゼロになるのでやはり1となる。経費の水増しでも同様の結果になるから、意外なことに、脱税への耐性は消費税でも所得税+法人税でも変わらない。
ただし、インボイス方式が導入されれば消費税はごまかしにくくなる。最終消費者に販売する事業者は依然としてごまかせるが、他の事業者に納入する事業者はごまかしにくい。いちいち紙のインボイスをやり取りするのは事業者にとって面倒だが、やはりインボイス方式はよい考えだ。ただし将来は、取引記録の電子化を進め、効率と捕捉率をさらに上げるべきだろう。
消費税はアングラ経済からも徴収できるのか
無申告の悪徳企業や暴力団は所得税・法人税を払っていないが、消費税なら(物を買ったときに)払わざるを得ない、と言われることがあるが本当だろうか。
残念ながらこれも正しくないようだ。消費税による商品の値上り分は、税金の預かり分というより、インフレと考えたほうがわかりやすい。たとえば消費税が5%上がり、すべての商品も5%上がったとする。悪徳企業の支払いは5%増えるが、売上も5%増え、利益も5%増える。ただこれはインフレ分だから、結局、悪徳企業は損得なしである。
以上、消費税について考えてみた。消費税と法人税・所得税とは意外に似ているが、消費税のほうが税収が安定すること、地域による偏在が少ないこと、資産課税効果があることを考えると、やはり上げるなら法人税・所得税より消費税だろう。相変わらず無駄の多い政府に増税させてよいかはまったく別問題であるが。
なお当然、現在の免税業者(課税売上1000万円以下)への益税はなくさねばならないし、いい加減な簡易課税制度(仕入れ比率見なし制度)もやめるべきだろう。
以上では国際取引をまったく考慮していない。次回は輸出入や法人税減税競争への影響を考えてみたい。
関連:消費税は逆進的か










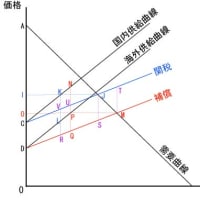
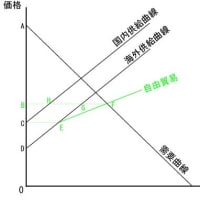
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます