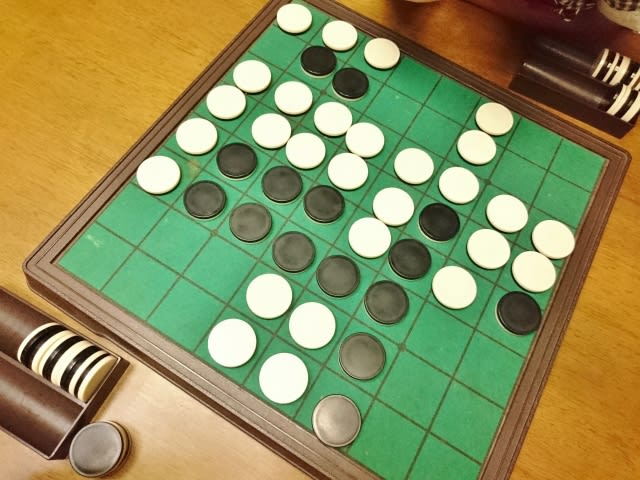皆さんこんにちは!
ようやくと言ったところか、朝でもだいぶ熱くなってきましたね!
作り置きの料理なんかも、保存が難しくなってきました。
恥ずかしながら、昨日夕飯にと思っておいて食べたカレーもなんか味が違うように感じ、
捨てる羽目になってしまいました。
皆さんも保存にはご注意くださいませ。

さて、今回は保存には欠かせないサランラップに関する雑学を紹介しておこうと思います!
サランラップと言えば食材や料理を保存するために用いられるものの商品名で、
正しい名称は「食品用ラップフィルム」と言うそうです。
厚さはわずか十数μm(マイクロメートル)でありながら耐熱性、耐水性に優れた、まさに画期的な保存用品とも言えます。
そんなサランラップですが、初めから食品の保存の為に開発されたものではなく、
最初の物は戦場で、しかも武器の弾薬などを湿気から守るために使われていたそうです。
戦争が終わり、ダウ・ケミカルのラドウィックとアイアンズという二人の技術者がピクニックに行ったとき、
妻がラップでくるんでおいたレタスがいつまでもみずみずしかったのを発見し、
食品の保湿と保管としての用途が注目され、食品用ラップが正式に販売されることとなりました。
「サランラップ」の「サラン」とは、その二人の技術者の妻の名前である「サラ」と「アン」からとったものだそうです。
「戦争中に使われていたものが改良され、日常が便利になるものとなる」と言う話はよくありますが、
サランラップも軍事用品だったんですね。カーナビやルンバもそうだったかな?
そしてそんなサランラップですが、保存以外にも掃除でも活躍するそうで、
丸めたラップに洗剤をつけてレンジの掃除に使ったり、
浴槽のカビキラーを撒いた所を密閉することで半日で黒カビが死滅したりなど、
まさにいろんな可能性が眠っていると言えます!
気になった方はぜひ試してみてください!
それでは今回はここまで!ではでは!