だがしかし、その行為の果てに密かな希望をしたためていたことは、白状せねばなるまい。
それは信次が教室に再び戻った際、自分の席に向かいながら窓際のあいつを堂々と見てしまおう、というものだった。それこそ、すけべ根性の最たるものだった。
とはいえ、誰にその魂胆を知られているわけでもない。教室内の景色を視界に入れた際、あいつがたまたま映っていればいいだけのことだった。
だから、罪悪感を持つ必要は何らないと思っていた。その作戦めいたものが失敗に終わった時にだけ、すけべ根性を恥じればいいと思っていたのだ。
用を手早く足した後、青いタイル壁に固定された鏡をちらりと見やる。トイレ内にいる他の生徒にいぶかられないよう、さりげなく前髪を整えた。
万が一、教室内で誰かと視線が合った際、冷笑されないようにと(本当のところは、あいつと目が合ったときのための、最大級の保険を掛けていたわけだが)。
トイレから教室へ戻る間、信次はリラックスしていたつもりだった。でも、廊下で歩を進めていくうちに緊張感が増していった。
いつもなら、すれ違う同級生をうつむきながらかわしていたのに、その時だけは自ら同級生の姿を認め、ひらりひらりとかわしていたように思う。
信次は急いで走った後のような息の上がりかたで、開いたままの教室後部のドアから足を踏み入れていた。
その瞬間、心のどこかで世界が真っ白になるような錯覚を期待していた。つまり、下衆な魂胆が実を結ぶことを。でも、現実の世界は色を失うことなく、そこに流れていた。
窓際の後ろの方に取り巻きの姿はなかった。もとより、あいつの姿もなかった。あいつが席を外していたのだ。
白木の机のたたずまいは、どことなく寂しさがあった。丁寧にそろえられた青と銀色のシャープペンシル。紙ケースのついた消しゴム。遠目にも、それらだけが机上で静止していた。
机の横のフックにかけられている白い紙袋は、風でかすかに揺れていた。所々、地の色が出ている鉄フレーム、それを骨格にする椅子。それはまるでもう引かれることがないかのように、机の下にきっちりと収まっていた。
それらを認めたとたん、信次の心に小さな安堵と落胆が襲ってきた。
いなくて良かった。
でも、いてほしかった。
どっちなんだ。
クラスメートが、立ち止まる信次をいぶかるようにして避けていく。おそらくその瞬間、信次ばかりが、このクラスのどの生徒よりもあいつを意識していたのだろう。
もはや、すけべ根性を恥じるどころではなかった。あまりの情けなさ、格好悪さに、自分で自分をあざけることしかできなかった。
ああ、とりあえず席に着かねば。
信次は邪心を振り払うように、小さく首を横に降った。そして、歩を進めたその直後だった。
ふっと、腰元を何かに押されたような感覚を受けていた。ただの物というよりは動体。それが、意図的な接触というよりは不意の接触で、背後を通過したような気配がしたのだ。
こくん、と揺れた上体を下半身で吸収して止める際、鈍い重力を感じたような気がしていた。
反射的に後ろを顧みる。あいつだった。並びゆく背の低いロッカーの前で、なぜか申し訳なさそうに頭を下げ、信次の背後を行くところだった。
視線が合っていたわけではない。あっ、と思う間もなかった。あいつは物静かなまま、自分の椅子を引いて席に着いていた。
信次の身に何が起こっていたのかを理解するまで、数秒の時間を要したのは言うまでもない。
ほどなくして、いつか見た景色のように取り巻きたちがあいつを囲んだ。そして、硬い表情の試験監督が教室に入ってきて休憩は終わった。
信次はいつの間にか自分の椅子に座っていて、それまでよりも多く、大胆に、あいつを盗み見ていた。その際、小さな安堵と落胆は、とうに吹き飛んでいたように思う。
惨敗だった三時限目。ノートにもプリントにも記されていなかったような内容が、問題用紙上にあふれていた。
解答用紙が前に送られ、回収されている間もずっと、きりきりするような前頭部の痛みを抱えていた。
ミシン縫いの順序、方法なんて意識したこともない。それはメーカーの機械によってまちまちであり、取り扱い説明書に従うべきである―――。そう、本気で解答しようと思っていた。
でも良心がとがめ、できなかった。
唯一、ストレスなく解答できたのは、カロリー計算の問題くらいだったと思う。あれは完全な数学の領域だったから。
とにかく、完全な油断、対象への見くびりが失敗を招いていた。その日、三つの試験科目の中で、信次への攻撃性が一番高かったのは家庭科であった。
信次が放心しながら筆記用具をペンケースにしまいだした頃、気だるい解放感が教室内に充満していた。悲喜こもごもの感想が飛び交い、誰もが半日の重しを取りはらおうとしていた。
あいつはどうだっただろう。
信次は半(なか)ばやけくそに、その方向を見やった。目が合いませんように、合ったとしてもごまかせますように。卑怯にも、そう祈っていた。
立ち動く人間たちがうごめく中で、あいつの横顔は途切れながらも見えていた。信次の視界がきれいに開いた時、前の席の女子と言葉を交わしているあいつが鮮明に映った。
もはやあいつの周囲には、熱心な取り巻きの姿はない。あいつは、ただまっすぐ目の前の女子を見つめていた。
多少の笑みを浮かべながら、首を傾げたり、口に手を当てたり。ぎくしゃくしながらも、あいつなりの人づきあいの作法を開示していた。
その雰囲気は、信次が思いこんでいたものよりも柔軟で、身軽な感じがしていた。
同じ匂いがしたなんて、都合のよい願望だったのかな。
反省にも似た一念が、信次の心をゆっくりと横断していった。緊張の初日、身構えてしまう取り巻き、急ぎ足の時間の流れ。そんなものが、あいつを一人ぼっちに仕立て上げていただけなのかな。
だとしても、信次であれば年中そんなものを背負って、それを自覚しながら一人ぼっちになっている。どれ一つとも対峙できずに。
自分の心配を棚に上げ、他人の心配をする。分かってはいたけれど、その滑稽さが浮き彫りとなっていた。あいつを見ながら、実は自分で自分を見下ろしていたのだということに、気づきかけていた。
その時、ごつん、という鈍い衝撃が信次の体を揺らした。前の席の男子が、自分の机と椅子のかたまりを無言で信次の机にぶつけてきたのだ。男子の力強い目には、早くしろ、という意思が感じ取られた。
誰の合図があったわけでもない。だが、どの列からも全ての机と椅子を押し下げる動きが始まっていた。
掃除の時間だった。帰りのホームルームがない分、直接その時間になるのだった。それと同時に、信次自身も教室の掃除当番の一人であることを急に思い出していた。
無音の圧力をかける男子に、あいつを注視していたことを悟られていたのかもしれない。信次はそんな焦りもあいまって、一目散に自分の机を下げた。
例の男子は、自分の机を持ちあげるようにして下げると、信次を一瞥することなく、鞄を手に教室を出ていった。しばらくの間、男子の心中を推測しようと躍起になる己がいたのは言うまでもない。
そんな中、あいつは律儀にも自分の椅子を机上にかぶせ、ロッカー付近まで後退していた。あいつと言葉を交わしていた前の席の女子の姿は、いつの間にか消えていた。
あいつはしきりに周囲を気にしていた。帰宅への準備は手早く済ませていたようだったのに。単純に、どうしていいかとまどっているようだった。
帰っていいと思うよ。
なぜか信次は、心であいつにささやいてしまっていた。数人のクラスメートも、不思議そうにあいつの様子をうかがっていた。だが誰も、あいつを包囲するようにして接近する、取り巻きほどの行動力は持っていなかったらしい。
後ろ髪をひかれるような感じで、一人、一人、とその場を後にしていった。
信次はあいつの存在を全身のどこかで感じながらも、とりあえず掃除に取りかかることにした。
廊下側の一番後ろにある、背の高いロッカーの扉を開ける。モップ型のほうきを手に取ろうとしたが、すでに出払っていた。
振り向けば、時間割の表記が消えかかっている黒板の前で、あるいは蛍光灯が映りこむ床板の上で、真面目に勤しむ女子班員の姿があった。
信次は仕方なく、他の男子班員と同様、人気のない雑巾がけへまわることにした。
教室の外にある鉄製の雑巾干しから乾ききった雑巾を手に取り、手洗い場で雑巾を絞り、室内に戻る。すると、黙っていても目についてしまうものがあった。
窓際の後ろで、掃除するクラスメートを見つめているあいつだ。
掃除当番の班員たちは、特にあいつを無視していたとか、あいつに気づいていなかったというわけではなかった。
ただ、あいつがあいつの意志なる下で、そこにいることを尊重していたというのが正しかったと思う。
それこそ、あいつからなにかしらの言動があることを待っていたようなふしもあった。だからなのか、信次は身勝手にもあいつに同情していた。
あいつがそこで一人にいることになってしまった、その成り行きに。何度もそんな事態に陥った自身の過去を、あいつに重ね合わせてしまっていたのだ。
信次は心苦しさを感じながらも、目を伏せていた。そして、それとなく男子班員の持ち場を確認し、それこそ空気を呼んで、雑巾で拭くものを探した。
比較的楽な窓ふきも、次第に面倒くさくなってくるクラスメートの机拭きも空きがなかった。残るは体力がものを言う、床の水拭きしか残っていなかった。
身じろぎ一つしていないあいつ。命ある静物だからこそ、その立ちつくす姿は目立ってしまう。声をかけた方がいいのだろうと思いつつ、ただ腰をかがめるしかなかった。
あいつのことを考えまいと、掃除に没頭(本当のところは現実逃避)する自分がいた。
女子班員の動きから、掃き終えた範囲を推測。控えめに床と壁面の境の汚れを確認。そして、クレームが入りそうにないことを察知すれば、あとは一気に床面を滑っていく。
線上の傷が、細いものから太いものまで走る床面。それらの一々を、誰がもたらしたものかなんて気にすることはしない。だけれど、ふと真新しかった床面の状態はどんなだったろうと想像する。
そういえば、試験週間の掃除当番って不公平ではないか。早く帰れたら、その分、遊べた、いや、試験勉強に没頭できたのに―――。
だめだった。
むりやりに雑念を湧き起こすことほど、不自然なことはなかった。ぎこちなくても自然体に戻ろう。そう決意して信次が顔を上げた、まさにその矢先だった。
あいつが動いたのは。
あいつは、女子班員の一人が床に投げだしていた塵取(ちりと)りを手にし、モップ型のほうきをくねらせるその班員の前で、 膝をついたのだった。
女子班員は驚いた表情で手を止めていた。だが、あいつの思いをすぐにくみ取り、固めて溜めておいた少量のゴミを、あいつのかまえる塵取りの中へ入れていた。
「ありがとう。あ、ゴミはね、あの赤色の蓋のダストボックスに直接入れちゃっていいから」
女子班員が優しく言うと、あいつは照れくさそうにうなずき、教壇の横に移動されていたダストボックスの中にゴミを流しこんでいた。
そして、そのまま女子班員たちにくっつき、適当な間合いでゴミを回収することをくりかえしていた。
≪つづく≫
最新の画像[もっと見る]
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.1 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.1 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.2 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.2 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.3 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.3 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.4 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.4 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.5 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.5 (10話完結)
7年前
-
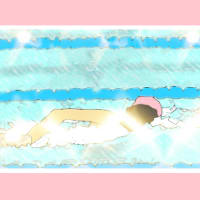 短編小説「サマーセッション」 vol.6 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.6 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.7 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.7 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.8 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.8 (10話完結)
7年前
-
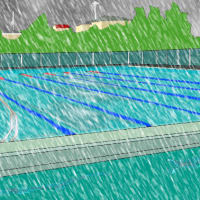 短編小説「サマーセッション」 vol.9 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.9 (10話完結)
7年前
-
 短編小説「サマーセッション」 vol.10 (10話完結)
7年前
短編小説「サマーセッション」 vol.10 (10話完結)
7年前









