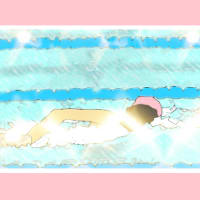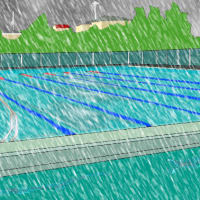西野「ああ、ちょっと待って。きれいに入らない!」
茶色のマントに包まれた細い体は、ビニール袋の中身をがさごそと探り、一人苛立っていた。
安藤「そういうことか。お前がしたかったことは……。万引きだな」
黒いテンガロンハットを深くかぶり、低い声でつぶやく仲間の一人。西野の隣にいれば、その頭の高さが二つ、三つ抜きん出ているのがよく分かる。身長は百九十センチを優に超えているだろう。
西野「ちがう! 袋に入れられた物を、さらに別の袋に入れたいだけなんだから」
安藤「その色つきの袋に入れる必要があるのか? やけに用意周到じゃないか」
西野「うるさいなあ! ねえ、ちょっとあんた。さっきから異様に近いんだけど! 隣に立つの、やめてくれる?」
西野は憤慨して、長い髪を大きく揺らしていた。怒るのは無理もない。隣のカウボーイスタイルの男は、西野の左半身にぴったりと寄り添っているのだから。
この男、つい先ほどまでは過度に集中して漫画雑誌を立ち読みしていたのだ。確かに、西野が買物をしていたかどうかは知るところではないのだろう。
しかし、安易に彼女を万引き犯に仕立て上げる思考というのは短絡的であるし、無理がある。趣味の悪い冗談にもなっていない。
西野が露骨に嫌な顔を見せているのに、安藤は平然とした様子で、西野の手元を凝視していく。彼女の我慢の限界は、近いうちにやって来るだろう。
安藤「袋の中に袋だと? 自分で言っていて苦しい言い訳だと思わんか? 実に滑稽(こっけい)だ。ふふっ、ふふふっ」
西野「その気味悪い笑い方、やめろ」
安藤「これか? ふふっ、ふふふっ」
西野「人の話、聞いてる?」
安藤は西野のきつい指摘にもへこたれず、その笑い方を何度か繰り返していた。西野が無言で安藤の横っ腹に拳を打ち込むと、男はもろくもその場にうずくまってしまった。
安藤「ぐうっ……。痛いじゃないか。暴力反対だと、あれほど言っておいたのに……。だいたい、お前の野良犬拳法は美しくない。堂々としていない」
西野「堂々としてなくて悪かったね。これならいいのかなっ?」
安藤「いーちちちちちちちち! いひゃい! いひゃいって! はなひて、悪かった! 悪かったって!」
安藤は西野に顎(あご)をつかまれると、そのまま立ち上がらされていた。そして思い切り頬(ほほ)をつねられてしまったのだ。大男が涙目になる様は、見るからに情けなかった。
安藤「はあ、はあ、はあ……。なあおい、後戻りするなら今だぞ。店主も大目に見てくれるかもしれない。私も適当に口添えしてやる。な?」
安藤は帽子を目深にかぶり直し、なおも食い下がっていく。本人は優しく忠告したつもりらしいが、彼(か)の女にとっては、つくづく余計な進言となったようだ。
西野「しつこいんだよ、お前! 変質者呼ばわりされたくなかったら黙ってろ!」
周囲に容易に響く西野の声量。店内に居合わせた客からの視線が二人に集まってくる。カウボーイ男は、自らが釈明する側に転じなければならなくなり、慌てていた。
安藤「そ、そんなに言うのなら、見せてみろ。何を盗った、何を」
西野「ちょ、ちょっと! 返して! 返しなさいって! 返せ、このバカ!」
安藤は苦しまぎれに西野の持つ袋の中身を強引に確認しようとした。しかし、西野に突き離されてしまい、真実は解明できなかったようだ。
西野「なにムキになってんの? ガキなの? こっちが恥ずかしい!」
安藤「無念……」
西野は初めからこうすべきだった、と独り言を発すると、安藤の隣を素早く離れていく。店内奥にある製氷機の前に移動すると、やるせないため息を漏らしていった。
孤立した安藤には、近づく一つの影があった。眼鏡をかけ、ノーネームの灰色のレーシングスーツを身につける、細面の男だ。彼はカウボーイ男の肩に優しく手をかけていた。
細面の男「ただでさえ、西野は気が強い。それに加え、あの目力(めぢから)だ。マスカラまつ毛が異様に長いのは伊達(だて)じゃないよ。あれは完全武装の仕様なんだ。彼女への立ち入り方というものがある」
安藤「森下……。しかし、人としてやってはいけないことがあるんだぞ? あいつをこのまま犯罪人にしておくことなど、私にはできない」
細面の男(森下)「まあ、そう熱くなるな。あいつが犯罪をやらかした事実はないんだから」
安藤「どうしてそう言い切れる? あいつは、袋の中身をかたくなになってでも見せようとしない。仲間としては放っておけないだろう?」
安藤の激しくなるばかりの様子に、森下は一瞬たじろいだかのように見えた。しかし、店内を一度冷静に見渡すと、安藤の背中に腕を回していく。さらに、彼の黒いジーンズのポケットに手を忍ばせると、そこから窮屈そうにあるモノを取り出していた。
森下「これは何だ?」
森下が安藤の目の前で慎重に見せつけたもの。それは掌(てのひら)に収まる大きさの、土色のキーホルダーのようだった。いや、土色に見えたものは、実は細部まで精巧に造り込まれた紐(ひも)付きの恐竜フィギュアだった。
安藤「そう、そうなんだ。最近、息子がこういうのを欲しがっているんだ。これはトリケラトプス。小さいがよく出来ているだろう?」
安藤がわざとらしく笑みを浮かべる。しかし、森下は誤魔化されないぞと言わんばかりに、安藤に詰め寄っていく。
森下「どこで手に入れた?」
安藤「なぜそんなことを聞くんだ? どこで手に入れようと私の勝手じゃないか」
安藤はにわかに焦燥の色を隠せないでいる。恐竜フィギュアの存在を探り当てられたことに動揺している。それは明白だった。森下は一ミリも表情を崩さずに、安藤を見据えていく。
森下「ならば、質問を変えるよ。これをどこで買った?」
安藤「本質的に質問が変わっていないじゃないか……」
安藤の全身が硬直したように動きを止めた。そして、安藤の革製のテンガロンハットは、もはや所有者の人相を隠し通せるものではなくなっていた。
どんなにそれを目深にかぶろうが、安藤を見上げる人間がいる限り、その表情は衆目を集めるものだ。
不意に、店内に響く音声が二人の耳に入ってきた。入ってきたというよりも、二人が黙ってしまったことによって、それが際立っただけのことだろう。
もともと、店内には切れ目のない音が流れつづけている。今でさえ、解散発表が話題になっている、女性アイドルグループのラストシングルが聞こえている。
新旧の人の出入りによって鳴らされる、入口のチャイム。買物の有無に限らず、客へのあいさつとお礼を欠かさない店員の声。
靴の種類によって異なるいくつかの足音。煩雑に開け閉めされる、保冷ケースの扉のきしみ。おそらくは西野の、携帯電話の画面をタップする雑な指癖。
無数とはいかないまでも、許容される有限の雑音があった。
かすかに香る、チキンの唐揚げの匂いも忘れてはいけない。
そんな店内で、森下は無言で安藤の反応を待っている。当の安藤は山の高い帽子の頂点を右手でしっかりと抑えていた。さらに目深にするつもりなのか、帽子のつばの高さは涙袋よりも下にある。
何かを観念したようにも見えるその所作。安藤は静かに口を開いていた。
安藤「お前が何を言いたいのかは知らないが……、別に隠すことでもない。その恐竜はこの店のレジの横にある棚から購入した」
森下「いつ?」
安藤「確か四、五日前だ」
森下「証人はいるか?」
安藤「証人なんているわけないだろう。む、待てよ。今日のレジの店員は……、いや、ちがう、初見の人間だ。残念だったな」
森下「レシートは?」
安藤「私がもらうような人間に見えるか? もらうわけないだろう。だいたい、店員だってその辺は見極めている。レシートを欲している客かどうか瞬時に判断しているのだぞ。お前はその陰の努力も知らないで、軽々しくレシート、レシートと連呼しないほうがいい」
森下「しかしレシートは領収書であり、購入者の行動を辿れる重要な物証。軽視できるものではない」
安藤「そうかい。ならば身の潔白を証明するものは無いな。残念だったな」
手負いの状態にもかかわらず、素知らぬ顔でいる安藤。強引に話を切り上げようとしていた。森下の手からフィギュアを奪い取るようにつかむと、ポケットの中にねじこんでいく。森下は空になった掌をしばらく見つめ、その腕を力なく下げていった。
森下「レシートの有用性を知らないようだな」
安藤「どういうことだ?」
森下はいぶかしがる安藤を右手で制し、ちょっと待っていろとつぶやく。そして足早に店内奥に移動すると、先程から一人で待機している西野と合流。西野と粘り強く交渉した結果、彼女の持っていた二重のビニール袋の中から、とあるモノを取り出していた。
モノが具体的に何なのか、数がいくつあるのか、帽子を目深にかぶることを信条とする安藤には見当がつけられない。
森下はそのままレジへ行き、対応した男の店員と二言三言、言葉を交わした。店員は森下から一枚の紙切れとモノを受け取ると、慣れた様子でバーコードを読む機械にモノを当てた。そして、レジカウンターの跳ね扉を揺らして店内の通路に出てきたのだ。
≪つづく≫
茶色のマントに包まれた細い体は、ビニール袋の中身をがさごそと探り、一人苛立っていた。
安藤「そういうことか。お前がしたかったことは……。万引きだな」
黒いテンガロンハットを深くかぶり、低い声でつぶやく仲間の一人。西野の隣にいれば、その頭の高さが二つ、三つ抜きん出ているのがよく分かる。身長は百九十センチを優に超えているだろう。
西野「ちがう! 袋に入れられた物を、さらに別の袋に入れたいだけなんだから」
安藤「その色つきの袋に入れる必要があるのか? やけに用意周到じゃないか」
西野「うるさいなあ! ねえ、ちょっとあんた。さっきから異様に近いんだけど! 隣に立つの、やめてくれる?」
西野は憤慨して、長い髪を大きく揺らしていた。怒るのは無理もない。隣のカウボーイスタイルの男は、西野の左半身にぴったりと寄り添っているのだから。
この男、つい先ほどまでは過度に集中して漫画雑誌を立ち読みしていたのだ。確かに、西野が買物をしていたかどうかは知るところではないのだろう。
しかし、安易に彼女を万引き犯に仕立て上げる思考というのは短絡的であるし、無理がある。趣味の悪い冗談にもなっていない。
西野が露骨に嫌な顔を見せているのに、安藤は平然とした様子で、西野の手元を凝視していく。彼女の我慢の限界は、近いうちにやって来るだろう。
安藤「袋の中に袋だと? 自分で言っていて苦しい言い訳だと思わんか? 実に滑稽(こっけい)だ。ふふっ、ふふふっ」
西野「その気味悪い笑い方、やめろ」
安藤「これか? ふふっ、ふふふっ」
西野「人の話、聞いてる?」
安藤は西野のきつい指摘にもへこたれず、その笑い方を何度か繰り返していた。西野が無言で安藤の横っ腹に拳を打ち込むと、男はもろくもその場にうずくまってしまった。
安藤「ぐうっ……。痛いじゃないか。暴力反対だと、あれほど言っておいたのに……。だいたい、お前の野良犬拳法は美しくない。堂々としていない」
西野「堂々としてなくて悪かったね。これならいいのかなっ?」
安藤「いーちちちちちちちち! いひゃい! いひゃいって! はなひて、悪かった! 悪かったって!」
安藤は西野に顎(あご)をつかまれると、そのまま立ち上がらされていた。そして思い切り頬(ほほ)をつねられてしまったのだ。大男が涙目になる様は、見るからに情けなかった。
安藤「はあ、はあ、はあ……。なあおい、後戻りするなら今だぞ。店主も大目に見てくれるかもしれない。私も適当に口添えしてやる。な?」
安藤は帽子を目深にかぶり直し、なおも食い下がっていく。本人は優しく忠告したつもりらしいが、彼(か)の女にとっては、つくづく余計な進言となったようだ。
西野「しつこいんだよ、お前! 変質者呼ばわりされたくなかったら黙ってろ!」
周囲に容易に響く西野の声量。店内に居合わせた客からの視線が二人に集まってくる。カウボーイ男は、自らが釈明する側に転じなければならなくなり、慌てていた。
安藤「そ、そんなに言うのなら、見せてみろ。何を盗った、何を」
西野「ちょ、ちょっと! 返して! 返しなさいって! 返せ、このバカ!」
安藤は苦しまぎれに西野の持つ袋の中身を強引に確認しようとした。しかし、西野に突き離されてしまい、真実は解明できなかったようだ。
西野「なにムキになってんの? ガキなの? こっちが恥ずかしい!」
安藤「無念……」
西野は初めからこうすべきだった、と独り言を発すると、安藤の隣を素早く離れていく。店内奥にある製氷機の前に移動すると、やるせないため息を漏らしていった。
孤立した安藤には、近づく一つの影があった。眼鏡をかけ、ノーネームの灰色のレーシングスーツを身につける、細面の男だ。彼はカウボーイ男の肩に優しく手をかけていた。
細面の男「ただでさえ、西野は気が強い。それに加え、あの目力(めぢから)だ。マスカラまつ毛が異様に長いのは伊達(だて)じゃないよ。あれは完全武装の仕様なんだ。彼女への立ち入り方というものがある」
安藤「森下……。しかし、人としてやってはいけないことがあるんだぞ? あいつをこのまま犯罪人にしておくことなど、私にはできない」
細面の男(森下)「まあ、そう熱くなるな。あいつが犯罪をやらかした事実はないんだから」
安藤「どうしてそう言い切れる? あいつは、袋の中身をかたくなになってでも見せようとしない。仲間としては放っておけないだろう?」
安藤の激しくなるばかりの様子に、森下は一瞬たじろいだかのように見えた。しかし、店内を一度冷静に見渡すと、安藤の背中に腕を回していく。さらに、彼の黒いジーンズのポケットに手を忍ばせると、そこから窮屈そうにあるモノを取り出していた。
森下「これは何だ?」
森下が安藤の目の前で慎重に見せつけたもの。それは掌(てのひら)に収まる大きさの、土色のキーホルダーのようだった。いや、土色に見えたものは、実は細部まで精巧に造り込まれた紐(ひも)付きの恐竜フィギュアだった。
安藤「そう、そうなんだ。最近、息子がこういうのを欲しがっているんだ。これはトリケラトプス。小さいがよく出来ているだろう?」
安藤がわざとらしく笑みを浮かべる。しかし、森下は誤魔化されないぞと言わんばかりに、安藤に詰め寄っていく。
森下「どこで手に入れた?」
安藤「なぜそんなことを聞くんだ? どこで手に入れようと私の勝手じゃないか」
安藤はにわかに焦燥の色を隠せないでいる。恐竜フィギュアの存在を探り当てられたことに動揺している。それは明白だった。森下は一ミリも表情を崩さずに、安藤を見据えていく。
森下「ならば、質問を変えるよ。これをどこで買った?」
安藤「本質的に質問が変わっていないじゃないか……」
安藤の全身が硬直したように動きを止めた。そして、安藤の革製のテンガロンハットは、もはや所有者の人相を隠し通せるものではなくなっていた。
どんなにそれを目深にかぶろうが、安藤を見上げる人間がいる限り、その表情は衆目を集めるものだ。
不意に、店内に響く音声が二人の耳に入ってきた。入ってきたというよりも、二人が黙ってしまったことによって、それが際立っただけのことだろう。
もともと、店内には切れ目のない音が流れつづけている。今でさえ、解散発表が話題になっている、女性アイドルグループのラストシングルが聞こえている。
新旧の人の出入りによって鳴らされる、入口のチャイム。買物の有無に限らず、客へのあいさつとお礼を欠かさない店員の声。
靴の種類によって異なるいくつかの足音。煩雑に開け閉めされる、保冷ケースの扉のきしみ。おそらくは西野の、携帯電話の画面をタップする雑な指癖。
無数とはいかないまでも、許容される有限の雑音があった。
かすかに香る、チキンの唐揚げの匂いも忘れてはいけない。
そんな店内で、森下は無言で安藤の反応を待っている。当の安藤は山の高い帽子の頂点を右手でしっかりと抑えていた。さらに目深にするつもりなのか、帽子のつばの高さは涙袋よりも下にある。
何かを観念したようにも見えるその所作。安藤は静かに口を開いていた。
安藤「お前が何を言いたいのかは知らないが……、別に隠すことでもない。その恐竜はこの店のレジの横にある棚から購入した」
森下「いつ?」
安藤「確か四、五日前だ」
森下「証人はいるか?」
安藤「証人なんているわけないだろう。む、待てよ。今日のレジの店員は……、いや、ちがう、初見の人間だ。残念だったな」
森下「レシートは?」
安藤「私がもらうような人間に見えるか? もらうわけないだろう。だいたい、店員だってその辺は見極めている。レシートを欲している客かどうか瞬時に判断しているのだぞ。お前はその陰の努力も知らないで、軽々しくレシート、レシートと連呼しないほうがいい」
森下「しかしレシートは領収書であり、購入者の行動を辿れる重要な物証。軽視できるものではない」
安藤「そうかい。ならば身の潔白を証明するものは無いな。残念だったな」
手負いの状態にもかかわらず、素知らぬ顔でいる安藤。強引に話を切り上げようとしていた。森下の手からフィギュアを奪い取るようにつかむと、ポケットの中にねじこんでいく。森下は空になった掌をしばらく見つめ、その腕を力なく下げていった。
森下「レシートの有用性を知らないようだな」
安藤「どういうことだ?」
森下はいぶかしがる安藤を右手で制し、ちょっと待っていろとつぶやく。そして足早に店内奥に移動すると、先程から一人で待機している西野と合流。西野と粘り強く交渉した結果、彼女の持っていた二重のビニール袋の中から、とあるモノを取り出していた。
モノが具体的に何なのか、数がいくつあるのか、帽子を目深にかぶることを信条とする安藤には見当がつけられない。
森下はそのままレジへ行き、対応した男の店員と二言三言、言葉を交わした。店員は森下から一枚の紙切れとモノを受け取ると、慣れた様子でバーコードを読む機械にモノを当てた。そして、レジカウンターの跳ね扉を揺らして店内の通路に出てきたのだ。
≪つづく≫