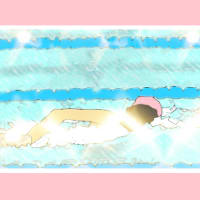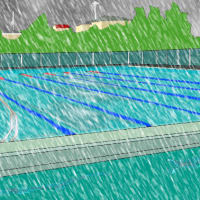ほどなくして、信次の背中に細い棒状のものが食いこむように衝突してきた。あまりの衝撃の大きさに我に返り、後ろ向きの歩行をやめた。
前に向き直って認めたものは、バス停の黄色いポールと、そのポール越しにバスを待っていた、あいつだった。
一瞬何が起こったのか分からなかった。確かなことは、歩道上の屋根の無いバス停留所に、バスを待つあいつがいたということだけ。
あいつは朝、教室に入ってきた時と同じ格好、同じ姿勢で直立していた。驚いた顔で、信次を見つめてもいた。
なぜここにいるんだ。
しかもバスに乗ろうとしているのか。
どこへ行こうとしている。
事態をうまく飲み込めなかった。他人から見れば、奇行とも取れる信次の後進。それを目撃されていたことは、ひとまず考えないようにした。
掃除の時間に嫌というほどみじめな思いをしていたし、放っておいてもじきにいつもの心模様になると思ったからだ。
それよりも何よりも、信次の胸中にうずまく疑念の方を払拭したかった。
停留所の行き先の表示は、最寄りのJRの駅名を示していた。信次の通う中学校の生徒は皆、徒歩通学。むろん、定められた学区内に住む家がなければ通学できない決まりだった。
聞きたいことが山のようにあふれ、でも何一つ口にすることができなかった。中途半端に相手を見知っていればこそ、ぎくしゃくした雰囲気が生まれるもの。信次はその空間にはまっていた。
そんな中、意外にも先に口を開いたのは、あいつの方からだった。
「さっきはどうも」
「え?」
「教室で掃除していた時に……」
「あ、ああ。そうだね。どうも」
スカートの前で両手を結び、そこから白い紙袋を下げ、首だけを横に向けていたあいつ。信次が頭をかきながら会釈すると、あいつは恥ずかしそうにうつむいた。
良くも悪くも、信次はあいつに記憶されていたということだ。信次があいつのことを記憶していたのと同様に。
でも両者で決定的に異なるのは、互いの記憶の時間の長さであろう。信次は朝からあいつを意識していた。一方のあいつは、いつから信次を意識していただろうか。
あいつの言葉を鵜呑みにすれば、それは掃除時間の間だけ、ということになる。三時限目の前のあのニアミスなど、もとから頭になかったということだろう。
それならば、あの短い間の中で信次という人間を知ったというのならば、それは誤解が多い。あれが信次のすべてではない。信次はあいつにそう言いたかった。
とはいえ、信次だってあいつの何を知っていたというのだろう。盗み見ていただけのやじ馬でしかなかった。直接言葉を交わしてもいないのに、相手を知ったような気でいた。
結局、心の中で右往左往し、いいように見られたいという願望に行き着いていく。信次はいつもの悪あがきをしているに過ぎなかった。
あいつは特段、掃除時間の信次について言及するわけでもなく、半日の感想を述べるでもなかった。ただただ、押し黙ったままだった。
バス停に他に人はおらず、国道の遠くを見やってもバスの来る気配はなかった。じりじりと進む車列から、アイドリングストップ機構を作動させる音だけが、勃発的に響いていた。
「あの……」
あいつのひかえめな声がかすかに聞こえた。信次はのどに異物がひっかかったようになって返答できず、首を傾げただけで終わっていた。
ためらうような表情をみせるあいつ。嫌な印象を与えてしまっただろうか。信次はすぐに不安に駆られた。
でもそれは杞憂に終わっていた。
あいつは一度、何でもないというように首を振り、そこから思い切ったように白い紙袋の中へ手を入れていた。そして、折り畳まれた一枚のプリント用紙を取りだしたのだ。
あいつは紙袋を地面に下ろすと、信次にもよく見えるよう、青白い紙を広げた。見覚えのある名前の羅列、なじみのある数字の順番。それはクラスの出席簿のようなものだった。
「あの、名前を……」
あいつは信次に紙を差し出すようにして言った。信次の名前がどこにあるか、指し示してほしいということだった。
直接名前を聞くこともできただろうに、一枚の紙を介して確認しようとする姿勢。あいつなりに、恥ずかしさをふりはらって、意を決した思いが伝わってきた。何だかあいつらしい。信次はそう、勝手に思っていた。
信次は右の人差し指で、自分の名前をなぞり、あいつに教えた。
「……かさき、信次君、あ、信次さん」
「ていねいに言わなくてもいいよ。名字でも下でも、呼び捨てでもかまわないし」
「そうですか……」
信次の名前を丁寧に言い換えたあいつは、初めて慌てた様子を見せていた。小さな感情の現れだったが、あいつの人間らしさを垣間見た思いで少し安心した。
「わたし引っ込み思案で、最初のほうがいつも慣れなくて。ごめんなさい」
「え……? ああ、いいよ、それくらい。謝るようなことじゃないよ」
信次は驚いていた。あいつが自分で自分の弱点を認めていたことに。それは、信次にはなかなかできないことだった。
引っ込み思案、という表現。
信次の場合、それが事実でも自分を貶(おとしめ)るようで言えなかったと思うのだ。一発で見抜かれるもろい部分を、わざわざ念押しすることはない。同情が働いたところで、相手が己の性格を瞬時に変えてくれるわけでもない。
事実を認めたくないからこそ、放っておいてほしい部類のものだった。
それなのに、あいつは堂々と人に伝えることができていた。信次と同様にやっかいなことだと俎上(そじょう)に乗せても、そこから逃れられないことを認めているようだった。
だからなのだろう。あいつのことを裏表がない人間なのだと思ってしまったのは。その証拠に、あいつに対して、笑ったり(愛想笑いだけれど)、なんとか言葉を繰り出したりする信次がいた。
近しく付き合っていけるような相手でないと、そうはならないのではないか。
だいたい、初対面ってどういう意味だっけ。
誰かに問いたい気分だった。警戒心が薄らいでいた。それだけは確かなようだった。
話はそれ以上弾まず、どうしても間が空いてしまう。あいつは手にしていた紙の、信次の名前の付近をずっと見つめていた。今度は信次が声をかける番だと、思い切った。
「バス、乗るんだ」
「はい?」
「うちの中学でバス乗る人、珍しいから」
「あ、そうなんですか。バスは、その……」
口ごもってしまったあいつ。聞いてほしくない質問だったことは、それで明白だった。いつものように墓穴を掘った信次。幻想の中では、うまくいく結果だけを想像していた。
現実には結果の前に過程がある。過程をおろそかにしてしまえば、望む結果も生まれない。
相手のことを聞く前に、自分のことをさらけ出すのが道理だった。信次は火の出る勢いの表情で謝るしかなかった。
「ごめん、いきなり変なこと聞いて。俺はもうこの辺に、すぐ近くに住んでる。ここから、ほんの十分くらいのとこ」
「え? ああ、そうなんですか……」
ますます戸惑うあいつ。信次は欲する解答が得られないまま、自分の発言が見当ちがいであったことにようやく気づいていた。でも、取りつくろい方を知らなかった。
にわかに渋滞の流れが速くなっていく。いらだつような排気音が、そこらじゅうで収束しつつあった。
あいつは紙を手にしたまま、前髪を何度も整えていた。鞄を持つ右腕が棒のようになっていたのは信次。左手に持ち変えようとしたが、それすらもはばかられる空気がそこには流れていた。どうしたものか、困り果てていた。
そんな時、あいつは一つの咳払(せきばら)いをはさんだ。そして、リュック型の鞄を揺さぶるように背負い直し、焦点を定めないようにして前へ向き直った。
「今回こそは、と思うんだけど、だめで。また、ここでも耐えられなくなるかもしれない」
あいつは急に、一節一節を丁寧に、しかも思いを込めて話しはじめた。
「え?」
「居場所が作れないかもしれない」
「居場所?」
「どこにあるんだろうって、いつも思ってたの。でも、そんなのどこにもなかった。自分で作るしかないって分かってたけど、できなかった」
独白のようなあいつの発言に、信次は圧倒される思いだった。同い年の女性の意志の強さを、こんなにも間近で感じたことはなかった。信次の右腕は音を上げ、鞄をアスファルトに落としていた。
「せめて、皆と同じことを一緒にやってみようって努力したの。みんなの輪の中にいれば、連帯感が生まれて、認めてもらえることができると思ったから。だけど、失敗したり、ぶざまな姿を見せるのが苦しくなって、気づいたらついていけなくなってた」
あいつはそこまでで、本当に苦しそうに悲しそうに、気持ちを告げてくれていた。信次ならば、自分と向き合う時にだけ、吐露しているような内容だった。
とてもじゃないが、他人に打ち明けられる種類のものではなかった。
「だから、バスに乗っているんだと思う」
あいつは再び信次の方へ顔を向けた。
何かに負けまいと必死に抗するまなざしで、信次を見ていた。
「答えになっていないかな?」
それに対して、信次は力なく首を横に振っていた。
答えになっていようがいまいが、どうでもいい。
信次の胸は、針で何度も突き刺されたみたいに痛かった。
保身のために毎日を生き、自分が傷つかないことを最優先にしていた己を恥じた。少なくとも、あいつは信次と同類項ではなかった。
挑み、傷つき、また挑み。それを繰りかえしていたのだから。
転校してきた理由だとか、時期だとか、蠅のように群がって知ることではなかったのだ。明らかになった真実めいたものに、信次は呆然とするしかなかった。自分の鞄の端を踏んでいたのにも、しばらく気づけなかったほどだ。
「でもね、掃除時間の時に」
あいつはそう言って、もったいぶるように発言を区切った。信次は必死の思いで、二度うなずいていた。一言も聞き漏らすまい。そう感じさせるものが、あいつの発する言葉にはあったのだ。
≪つづく≫
前に向き直って認めたものは、バス停の黄色いポールと、そのポール越しにバスを待っていた、あいつだった。
一瞬何が起こったのか分からなかった。確かなことは、歩道上の屋根の無いバス停留所に、バスを待つあいつがいたということだけ。
あいつは朝、教室に入ってきた時と同じ格好、同じ姿勢で直立していた。驚いた顔で、信次を見つめてもいた。
なぜここにいるんだ。
しかもバスに乗ろうとしているのか。
どこへ行こうとしている。
事態をうまく飲み込めなかった。他人から見れば、奇行とも取れる信次の後進。それを目撃されていたことは、ひとまず考えないようにした。
掃除の時間に嫌というほどみじめな思いをしていたし、放っておいてもじきにいつもの心模様になると思ったからだ。
それよりも何よりも、信次の胸中にうずまく疑念の方を払拭したかった。
停留所の行き先の表示は、最寄りのJRの駅名を示していた。信次の通う中学校の生徒は皆、徒歩通学。むろん、定められた学区内に住む家がなければ通学できない決まりだった。
聞きたいことが山のようにあふれ、でも何一つ口にすることができなかった。中途半端に相手を見知っていればこそ、ぎくしゃくした雰囲気が生まれるもの。信次はその空間にはまっていた。
そんな中、意外にも先に口を開いたのは、あいつの方からだった。
「さっきはどうも」
「え?」
「教室で掃除していた時に……」
「あ、ああ。そうだね。どうも」
スカートの前で両手を結び、そこから白い紙袋を下げ、首だけを横に向けていたあいつ。信次が頭をかきながら会釈すると、あいつは恥ずかしそうにうつむいた。
良くも悪くも、信次はあいつに記憶されていたということだ。信次があいつのことを記憶していたのと同様に。
でも両者で決定的に異なるのは、互いの記憶の時間の長さであろう。信次は朝からあいつを意識していた。一方のあいつは、いつから信次を意識していただろうか。
あいつの言葉を鵜呑みにすれば、それは掃除時間の間だけ、ということになる。三時限目の前のあのニアミスなど、もとから頭になかったということだろう。
それならば、あの短い間の中で信次という人間を知ったというのならば、それは誤解が多い。あれが信次のすべてではない。信次はあいつにそう言いたかった。
とはいえ、信次だってあいつの何を知っていたというのだろう。盗み見ていただけのやじ馬でしかなかった。直接言葉を交わしてもいないのに、相手を知ったような気でいた。
結局、心の中で右往左往し、いいように見られたいという願望に行き着いていく。信次はいつもの悪あがきをしているに過ぎなかった。
あいつは特段、掃除時間の信次について言及するわけでもなく、半日の感想を述べるでもなかった。ただただ、押し黙ったままだった。
バス停に他に人はおらず、国道の遠くを見やってもバスの来る気配はなかった。じりじりと進む車列から、アイドリングストップ機構を作動させる音だけが、勃発的に響いていた。
「あの……」
あいつのひかえめな声がかすかに聞こえた。信次はのどに異物がひっかかったようになって返答できず、首を傾げただけで終わっていた。
ためらうような表情をみせるあいつ。嫌な印象を与えてしまっただろうか。信次はすぐに不安に駆られた。
でもそれは杞憂に終わっていた。
あいつは一度、何でもないというように首を振り、そこから思い切ったように白い紙袋の中へ手を入れていた。そして、折り畳まれた一枚のプリント用紙を取りだしたのだ。
あいつは紙袋を地面に下ろすと、信次にもよく見えるよう、青白い紙を広げた。見覚えのある名前の羅列、なじみのある数字の順番。それはクラスの出席簿のようなものだった。
「あの、名前を……」
あいつは信次に紙を差し出すようにして言った。信次の名前がどこにあるか、指し示してほしいということだった。
直接名前を聞くこともできただろうに、一枚の紙を介して確認しようとする姿勢。あいつなりに、恥ずかしさをふりはらって、意を決した思いが伝わってきた。何だかあいつらしい。信次はそう、勝手に思っていた。
信次は右の人差し指で、自分の名前をなぞり、あいつに教えた。
「……かさき、信次君、あ、信次さん」
「ていねいに言わなくてもいいよ。名字でも下でも、呼び捨てでもかまわないし」
「そうですか……」
信次の名前を丁寧に言い換えたあいつは、初めて慌てた様子を見せていた。小さな感情の現れだったが、あいつの人間らしさを垣間見た思いで少し安心した。
「わたし引っ込み思案で、最初のほうがいつも慣れなくて。ごめんなさい」
「え……? ああ、いいよ、それくらい。謝るようなことじゃないよ」
信次は驚いていた。あいつが自分で自分の弱点を認めていたことに。それは、信次にはなかなかできないことだった。
引っ込み思案、という表現。
信次の場合、それが事実でも自分を貶(おとしめ)るようで言えなかったと思うのだ。一発で見抜かれるもろい部分を、わざわざ念押しすることはない。同情が働いたところで、相手が己の性格を瞬時に変えてくれるわけでもない。
事実を認めたくないからこそ、放っておいてほしい部類のものだった。
それなのに、あいつは堂々と人に伝えることができていた。信次と同様にやっかいなことだと俎上(そじょう)に乗せても、そこから逃れられないことを認めているようだった。
だからなのだろう。あいつのことを裏表がない人間なのだと思ってしまったのは。その証拠に、あいつに対して、笑ったり(愛想笑いだけれど)、なんとか言葉を繰り出したりする信次がいた。
近しく付き合っていけるような相手でないと、そうはならないのではないか。
だいたい、初対面ってどういう意味だっけ。
誰かに問いたい気分だった。警戒心が薄らいでいた。それだけは確かなようだった。
話はそれ以上弾まず、どうしても間が空いてしまう。あいつは手にしていた紙の、信次の名前の付近をずっと見つめていた。今度は信次が声をかける番だと、思い切った。
「バス、乗るんだ」
「はい?」
「うちの中学でバス乗る人、珍しいから」
「あ、そうなんですか。バスは、その……」
口ごもってしまったあいつ。聞いてほしくない質問だったことは、それで明白だった。いつものように墓穴を掘った信次。幻想の中では、うまくいく結果だけを想像していた。
現実には結果の前に過程がある。過程をおろそかにしてしまえば、望む結果も生まれない。
相手のことを聞く前に、自分のことをさらけ出すのが道理だった。信次は火の出る勢いの表情で謝るしかなかった。
「ごめん、いきなり変なこと聞いて。俺はもうこの辺に、すぐ近くに住んでる。ここから、ほんの十分くらいのとこ」
「え? ああ、そうなんですか……」
ますます戸惑うあいつ。信次は欲する解答が得られないまま、自分の発言が見当ちがいであったことにようやく気づいていた。でも、取りつくろい方を知らなかった。
にわかに渋滞の流れが速くなっていく。いらだつような排気音が、そこらじゅうで収束しつつあった。
あいつは紙を手にしたまま、前髪を何度も整えていた。鞄を持つ右腕が棒のようになっていたのは信次。左手に持ち変えようとしたが、それすらもはばかられる空気がそこには流れていた。どうしたものか、困り果てていた。
そんな時、あいつは一つの咳払(せきばら)いをはさんだ。そして、リュック型の鞄を揺さぶるように背負い直し、焦点を定めないようにして前へ向き直った。
「今回こそは、と思うんだけど、だめで。また、ここでも耐えられなくなるかもしれない」
あいつは急に、一節一節を丁寧に、しかも思いを込めて話しはじめた。
「え?」
「居場所が作れないかもしれない」
「居場所?」
「どこにあるんだろうって、いつも思ってたの。でも、そんなのどこにもなかった。自分で作るしかないって分かってたけど、できなかった」
独白のようなあいつの発言に、信次は圧倒される思いだった。同い年の女性の意志の強さを、こんなにも間近で感じたことはなかった。信次の右腕は音を上げ、鞄をアスファルトに落としていた。
「せめて、皆と同じことを一緒にやってみようって努力したの。みんなの輪の中にいれば、連帯感が生まれて、認めてもらえることができると思ったから。だけど、失敗したり、ぶざまな姿を見せるのが苦しくなって、気づいたらついていけなくなってた」
あいつはそこまでで、本当に苦しそうに悲しそうに、気持ちを告げてくれていた。信次ならば、自分と向き合う時にだけ、吐露しているような内容だった。
とてもじゃないが、他人に打ち明けられる種類のものではなかった。
「だから、バスに乗っているんだと思う」
あいつは再び信次の方へ顔を向けた。
何かに負けまいと必死に抗するまなざしで、信次を見ていた。
「答えになっていないかな?」
それに対して、信次は力なく首を横に振っていた。
答えになっていようがいまいが、どうでもいい。
信次の胸は、針で何度も突き刺されたみたいに痛かった。
保身のために毎日を生き、自分が傷つかないことを最優先にしていた己を恥じた。少なくとも、あいつは信次と同類項ではなかった。
挑み、傷つき、また挑み。それを繰りかえしていたのだから。
転校してきた理由だとか、時期だとか、蠅のように群がって知ることではなかったのだ。明らかになった真実めいたものに、信次は呆然とするしかなかった。自分の鞄の端を踏んでいたのにも、しばらく気づけなかったほどだ。
「でもね、掃除時間の時に」
あいつはそう言って、もったいぶるように発言を区切った。信次は必死の思いで、二度うなずいていた。一言も聞き漏らすまい。そう感じさせるものが、あいつの発する言葉にはあったのだ。
≪つづく≫