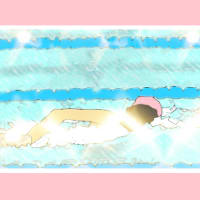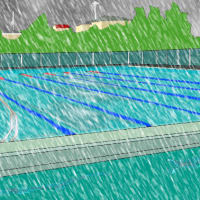スマートフォンの画面に目線を落とす。現在地の詳細が知りたかった。
地図アプリを起動する。GPSの測定から、三ノ輪駅近くの十字路の交差点付近にいるのが分かった。
しかし、ここはいわゆる464号線上の交差点ではないらしい。
正面には、JR常磐線が北東から西に向かって横切っているらしかった。
その方向を見やるも、街灯に照らされた小中のビル群が見えるだけ。それらの頂点部分は、闇色の空と同化するように霞(かす)んで見える。
その下を、休まずに動く交通の流れがある。それを制御するのは、寸分狂わぬタイミングで点灯する複数の信号機。
どこの街でも見かける状況なのに、慣れることができない。初めて訪れる夜の街で、心細さを感じていた。
その時、スマートフォンから着信音が鳴った。通話の着信だ。しかしそれは、非通知番号からの発信だった。
なぜ、非通知? いや、しかし。このタイミングであれば、かの子からの可能性が高い。事情があって非通知なのかもしれない。
迷いに迷ったあげく、恐る恐る、通話開始のボタンを押す。第一声がちゃんと出るのか、自分でも自信がなかった。
「もしもし」
第一声は出てくれた。しかし、相手のそれは返ってこない。
「……」
「もしもし、どちら様ですか?」
「……、あ、かの子です」
「かの子? かの子なのか?」
「はい」
確かに電話口の相手の声質は、かの子そのものだった。ほっとした。しかし、なぜ非通知なのだ?
「どうしたっていうんだ? 電話番号、非通知設定にしたのか?」
「ごめんね。もう終わりにしよう? 嘘だったの。でたらめだったの。ピッ。私、そこにはいないから。東京どころか、初めから日本になんかいないから」
「え? ええ? ど、どういうこと? 日本にいない……?」
信じられないような展開に、全身に電気的な衝撃が走っていた。
右肩が、ビル一階の店舗のシャッターに激しく当たっていく。動揺していた。
「ごめんね。悪いけど、会えない。会えないの」
かの子の声は、申し訳なさそうに、消え入りそうになって届いてくる。返す言葉が思いつかなかった。
必然、無音状態になる。すると、なぜか、ちっという舌打ちが聞こえてきたのだ。こちらの気のせいだろうか。
とにもかくにも、かの子を近くに置いておかねばならない。この日までの二人の親交を無にできるはずがない。
必死になって声を大きくしていた。
「う、嘘だよな? 日本にいないって? だってかの子、お前、神奈川にいるって言ったよな?」
「そんなこと、言ったかな」
「言った! 言っただろう? おい! ちょっと、いったん、ちゃんとしっかりしてみようよ! なんか、おかしいよ!」
「私、何をしている人だと思った?」
「え? 何って……。かの子はそこで、神奈川の逗子で、土産物屋さんで働いているって言ったじゃないか! 地元で会うのが嫌だから、東京の泪橋っていう場所があるから、そこがいいって。ちがうのか?」
「そうだと思った」
「な、なに、さっきからワケわかんないことばっかり言っているんだよ!」
そこで、相手方からの通信音がひどく乱れ、耳に痛い奇妙な電子音が発されていた。
さらには、「学習機能により、該当トラックを再生し終わりました」、という女声のアナウンスが聞こえてきた。
それらが静まった後だ。明らかに男の、男の咳ばらいが聞こえてきたのは。
「はい、はい、お兄さん。もう、充分だろう。東京見物できて良かったな。じゃあな」
がらの悪そうな男の声が一方的に聞こえ、通話も一方的に切られた。
我が身に何が起こっていたのか。それを判断しようにも、思考することすらできなかった。
かの子は確かに電話口に出て、通話が途切れては復活、その繰り返しを行い、互いの所在を確認し合っていた。
それがどうなった?
よく思い出せない。
いや、思い出せないのではない。排除したい記憶があまりにも劇的なものだったため、思い出す前に、意識がおじけついてしまうのだ。
耳に当てていたスマートフォンを見つめる。リダイヤルをしようと思ったが、もはや指が動いてくれない。
手の力が抜け、筺体はそのままするりと地面に落下した。乾いた音は聞こえなかった。
雨上がりのむっとする湿気が、この身にまとわりつく。じっとしていればこそ、それは逃れようがなくなる。
掌には汗がにじみ、大気がそれに触れ、熱を奪って気化していく。それでも掌は湿っていた。
土地勘などまるで無い場所で、このまま焦燥しきってしまうのか。
群がってきた小さな虫を追い払うこともできない。それらは発光体のようになって、残像を残して消えていった。
いくつかの角を曲がり、あるいは直線を行き、視界が開けたところで、筺体を持つ手を振りかざす。それだけのことだった。
自分は、かの子を探していたはずなのだ。
≪おわり≫