(1)第72代白河天皇
父「後三条天皇」が、藤原摂関家より嫌がらせを受ける不遇の東宮時代、
その子である「貞仁(さだひと)親王こと白河天皇」もまた、不遇の時代を送っており、
父同様の、打倒藤原摂関家の意志を強く引き継いでいた。
母は藤原系で、藤原公成の娘、藤原道長の孫娘の「藤原茂子」。
1068年、20歳で父帝より譲位、白河天皇として即位。
1073年、父帝後三条上皇、病死。
1081年、神社参りに、武士の護衛をつける
1083年、「後三年の役」始まる
1084年、中宮「賢子」死去
1085年、東宮で弟の「実仁親王(さねひと)」病死。
1086年、9歳の息子「堀川天皇」を立太子と同時に譲位、自身は院となり、院政を執る。
1087年、「後三年の役」終わる
1096年、溺愛の娘が病死、出家して「融観、白河法皇」として院制を続ける。
1097年、源義家の昇殿
1099年、堀川天皇時世の関白「藤原師通(もろみち)」病死。
1107年、堀川天皇29歳で病死、孫の「鳥羽天皇」が5歳で即位。
1108年、平正盛が、源義親を討伐/延暦寺の強訴を源平両氏で防ぐ
1113年、平忠盛、夏焼大夫の討伐で出世
1115年、待賢門院が、天皇の中宮になる
1119年、平正盛、賊平真澄の追討で出世
1123年、ひ孫の「崇徳天皇」即位
1129年、白河法王、77歳で崩御
(2)白河天皇まとめ
①院制をはじめる
②堀川天皇、鳥羽天皇、崇徳天皇の3代天皇で院制をとる。
③武士の起用---源氏(源義家)、平氏(平正盛)を側近とする
④鳥羽離宮を造営
⑤六勝寺の初めを作り、熊野詣など、仏教を信仰する
⑥南都、北嶺などの強訴多発
(3)院制
【父帝後三条天皇の土台】
藤原摂関家の権力を失墜させた後三条天皇は、僅か4年の在位で「白河天皇」に譲位する。
摂関政治が、天皇の母方尊属(外戚)による統治であったのに対して、
院政は、天皇の父方尊属にあたる、上皇(院)が統治した。
院は、天皇より強き存在として、「治天の君」とよばれ、
天皇はまるで東宮のごとき扱いであった。
父「後三条」からの早すぎる譲位は、、藤原摂関家の復権を阻止する為、
先帝が次の天皇の後見人として政治を執る、父方尊属の制度を敷いたものだとも考えられている。
白河天皇の後を、村上源氏系の母を持つ白河天皇の異母弟で2歳の「実仁親王」を東宮にすえ、
脱藤原外戚天皇の路線形成を図ったが、早くに病死する。
【白河上皇の院制】
1086年、わずか9歳の子を73代「堀川天皇」として譲位し、自身は院から政治の実権を握る。
堀川天皇の死後、その子で孫の74代「鳥羽天皇」の時も、院から政治を握り、
ひ孫の75代「崇徳天皇」までの3代天皇、43年間院制を執り続けた。
天皇即位争いを起こさせない為、東宮以外の兄弟は早くに出家させている。
白河上皇の43年間の院制に続き、
鳥羽上皇、後白河上皇と、院制は100年余り続くこととなる。
天皇、内裏、朝廷、宣旨よりも、上皇、院庁、院宣、院庁下文の方が
権力と効力を持つよりになり、朝廷政治に大きな影響を与えていくようになる。
(4)僧兵と、天下三不如意
平安時代も寺社の勢力、権力が強く、かつ各寺院には屈強な僧兵を囲い、
僧兵による強訴が度々あり、白河上皇を悩ませた。
特に 「山法師」とよばれる、比叡山延暦寺の僧兵は、勝手な理由に
かこつけては日吉山王社の神輿を担いで都に乗り込み、強訴を繰り返した。
『平家物語の源平盛衰記』に、白河上皇が
「鴨川の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」
と嘆いたという逸話がある。
これは、『天下三不如意』とよばれ、京都市内を流れる賀茂川の氾濫、すごろくの目と、
山法師=比叡山延暦寺の僧兵の3つは、自分の意図に従わないもの、
という意味。上皇の権力の大きさと、山法師への苦慮がうかがい知れる。
(5)『中右記』にみる白河上皇
『中右記(ちゅうゆうき) 』とは、平安時代の右大臣「藤原宗忠」が、1087年~1138年に
書いた50巻から成る日記で、院制時代を詳しく伝えている。
白河上皇には反発的だが、堀川上皇には手厚くしてもらい、恩義を感じているらしい。
「白河法皇は、後三条院崩御後、天下の政をとること五十七年〈在位十四年、位を避りて後四十三年〉、
意にまかせ、法にこだわらず、除目・叙位を行い給ふ。
古今未だあらず。
威四海に満ち天下帰伏す。幼主三代の政をとり、斎王六人の親となる。
桓武より以来絶えて例なし。
聖明の君、長久の主というべきなり。
但し理非決断、賞罰分明、愛悪を掲焉とし、貧富顕然なり。
男女の殊寵多く、すでに天下の品秩破るなり」
白河上皇が、いかに型破りな人物であったかが、うかがい知れる。
(6)白河院と最愛の中宮、賢子
賢子(たかこ)は、源顕房の娘で、左大臣「藤原師実(もろざね)」の養女である。
白河天皇とは非常に仲睦まじく、深い寵愛を受けて、
2人の皇子と、3人の内親王に恵まれた。
しかし、賢子が28歳の時に流行していたはしかに感染し、病死する。
通常、病気になった中宮は、実家に引き取られるのが慣例だが、
白河天皇はそれを許さず、傍で病気の治癒を祈り、息をひきとる時も
賢子の手を握って見送り、その亡骸を3日3晩離すことはなかったという。
白河天皇は、悲観のあまり、政治や公式行事に出ることもなく、
法勝寺に阿弥陀仏と常行堂を建立し、ひたすら賢子の供養に勤めていた。
(7)息子への譲位にこだわる白河天皇
中宮賢子の死の翌年、弟で皇太子の「実仁(さねひと)親王」が病死すると、
白河天皇は、精力的に動き出した。
父帝「後三条天皇」の遺言では、天皇譲位は兄弟の順に継ぐよう言い渡されてあり、
皇太子は、弟の「実仁親王」が父帝によって立てられていた。
その皇太子が亡くなった場合、本来はその下の弟である「輔仁親王」を皇太子とする
はずであったが、白河天皇は先帝との約束を破棄してそれを許さず、
8歳の息子の「善仁(よしひと)親王」を、立太子と同時に、堀川天皇として譲位した。
堀川天皇は、中宮賢子の子である。
(8)側近を固める
白河上皇は、堀川天皇の後見人として、院から政治を執る仕組みを作った。
当時の摂政は、中宮賢子の養父「藤原師実」であったが、養父は外戚に当たらないとして、
摂政藤原家を軽んじた。
院庁別当には、左大臣:大江匡房
大納言:白河上皇の母方の叔父、藤原実季(さねすえ)など、
上皇の近親者や、乳母の近親者5人を含んだ。
さらに、近臣として、乳母の関係者を取り立てたり、
親衛隊として、「北面の武士」を組織して、身辺警護にあたらせた。
こうした、身分の階級に拘らず、白河上皇の気持ち1つで動く院の政治に
対して、人々は敏感に反応し、我先にと白河上皇に贈り物(賄賂)を贈った。
平正盛も、うまく白河上皇にとりいった一人である。
(9)鳥羽離宮
白河上皇は、陸路と水路の交わる、朱雀大路の真南の位置に、
新しい都を作って、移り住んだ。その地を「鳥羽離宮」と言う。
(10)女堤子内親王と祇園女御
白河上皇は、中宮賢子の忘れ形見として、第一皇「女堤子ていし(やすこ)内親王」を、
他の皇子、皇女とは別として深く寵愛し、郁芳門院(ゆうほうもんいん)の称号を与えた。
しかし、1096年、京都中が田楽に狂っている最中、田楽が大好きだった女堤子内親王
が急死した。白河上皇の落胆は激しく、剃髪出家するほどであった。
出家後の白河法王は、放蕩三昧に明け暮れ、人妻であった「祇園女御」を寵愛するように
なり、妃や中宮にも劣らぬ権威を振るうようになる。
(11)待賢門院璋子
祇園女御を寵愛していた白河法王は、「藤原公実」に美しい娘が生まれたと知り、
祇園女御の養女として貰い受けた。
しかし、法王はその幼女である「待賢門院璋子」を懐に入れて寝る程の寵愛ぶりで、
後に、白河法皇と待賢門院璋子の関係は、公然たる秘密となっていく。
のちに璋子を、孫の「鳥羽天皇」の妻として入内させるが、入内後も法王との
関係は続いたとみられ、璋子の産んだ「顕仁親王、のちの崇徳天皇」のことを、
夫の鳥羽天皇は「叔父子(おじこ)」と呼んで嫌い、のちの天皇系統に影響を及ぼしていく。
父「後三条天皇」が、藤原摂関家より嫌がらせを受ける不遇の東宮時代、
その子である「貞仁(さだひと)親王こと白河天皇」もまた、不遇の時代を送っており、
父同様の、打倒藤原摂関家の意志を強く引き継いでいた。
母は藤原系で、藤原公成の娘、藤原道長の孫娘の「藤原茂子」。
1068年、20歳で父帝より譲位、白河天皇として即位。
1073年、父帝後三条上皇、病死。
1081年、神社参りに、武士の護衛をつける
1083年、「後三年の役」始まる
1084年、中宮「賢子」死去
1085年、東宮で弟の「実仁親王(さねひと)」病死。
1086年、9歳の息子「堀川天皇」を立太子と同時に譲位、自身は院となり、院政を執る。
1087年、「後三年の役」終わる
1096年、溺愛の娘が病死、出家して「融観、白河法皇」として院制を続ける。
1097年、源義家の昇殿
1099年、堀川天皇時世の関白「藤原師通(もろみち)」病死。
1107年、堀川天皇29歳で病死、孫の「鳥羽天皇」が5歳で即位。
1108年、平正盛が、源義親を討伐/延暦寺の強訴を源平両氏で防ぐ
1113年、平忠盛、夏焼大夫の討伐で出世
1115年、待賢門院が、天皇の中宮になる
1119年、平正盛、賊平真澄の追討で出世
1123年、ひ孫の「崇徳天皇」即位
1129年、白河法王、77歳で崩御
(2)白河天皇まとめ
①院制をはじめる
②堀川天皇、鳥羽天皇、崇徳天皇の3代天皇で院制をとる。
③武士の起用---源氏(源義家)、平氏(平正盛)を側近とする
④鳥羽離宮を造営
⑤六勝寺の初めを作り、熊野詣など、仏教を信仰する
⑥南都、北嶺などの強訴多発
(3)院制
【父帝後三条天皇の土台】
藤原摂関家の権力を失墜させた後三条天皇は、僅か4年の在位で「白河天皇」に譲位する。
摂関政治が、天皇の母方尊属(外戚)による統治であったのに対して、
院政は、天皇の父方尊属にあたる、上皇(院)が統治した。
院は、天皇より強き存在として、「治天の君」とよばれ、
天皇はまるで東宮のごとき扱いであった。
父「後三条」からの早すぎる譲位は、、藤原摂関家の復権を阻止する為、
先帝が次の天皇の後見人として政治を執る、父方尊属の制度を敷いたものだとも考えられている。
白河天皇の後を、村上源氏系の母を持つ白河天皇の異母弟で2歳の「実仁親王」を東宮にすえ、
脱藤原外戚天皇の路線形成を図ったが、早くに病死する。
【白河上皇の院制】
1086年、わずか9歳の子を73代「堀川天皇」として譲位し、自身は院から政治の実権を握る。
堀川天皇の死後、その子で孫の74代「鳥羽天皇」の時も、院から政治を握り、
ひ孫の75代「崇徳天皇」までの3代天皇、43年間院制を執り続けた。
天皇即位争いを起こさせない為、東宮以外の兄弟は早くに出家させている。
白河上皇の43年間の院制に続き、
鳥羽上皇、後白河上皇と、院制は100年余り続くこととなる。
天皇、内裏、朝廷、宣旨よりも、上皇、院庁、院宣、院庁下文の方が
権力と効力を持つよりになり、朝廷政治に大きな影響を与えていくようになる。
(4)僧兵と、天下三不如意
平安時代も寺社の勢力、権力が強く、かつ各寺院には屈強な僧兵を囲い、
僧兵による強訴が度々あり、白河上皇を悩ませた。
特に 「山法師」とよばれる、比叡山延暦寺の僧兵は、勝手な理由に
かこつけては日吉山王社の神輿を担いで都に乗り込み、強訴を繰り返した。
『平家物語の源平盛衰記』に、白河上皇が
「鴨川の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」
と嘆いたという逸話がある。
これは、『天下三不如意』とよばれ、京都市内を流れる賀茂川の氾濫、すごろくの目と、
山法師=比叡山延暦寺の僧兵の3つは、自分の意図に従わないもの、
という意味。上皇の権力の大きさと、山法師への苦慮がうかがい知れる。
(5)『中右記』にみる白河上皇
『中右記(ちゅうゆうき) 』とは、平安時代の右大臣「藤原宗忠」が、1087年~1138年に
書いた50巻から成る日記で、院制時代を詳しく伝えている。
白河上皇には反発的だが、堀川上皇には手厚くしてもらい、恩義を感じているらしい。
「白河法皇は、後三条院崩御後、天下の政をとること五十七年〈在位十四年、位を避りて後四十三年〉、
意にまかせ、法にこだわらず、除目・叙位を行い給ふ。
古今未だあらず。
威四海に満ち天下帰伏す。幼主三代の政をとり、斎王六人の親となる。
桓武より以来絶えて例なし。
聖明の君、長久の主というべきなり。
但し理非決断、賞罰分明、愛悪を掲焉とし、貧富顕然なり。
男女の殊寵多く、すでに天下の品秩破るなり」
白河上皇が、いかに型破りな人物であったかが、うかがい知れる。
(6)白河院と最愛の中宮、賢子
賢子(たかこ)は、源顕房の娘で、左大臣「藤原師実(もろざね)」の養女である。
白河天皇とは非常に仲睦まじく、深い寵愛を受けて、
2人の皇子と、3人の内親王に恵まれた。
しかし、賢子が28歳の時に流行していたはしかに感染し、病死する。
通常、病気になった中宮は、実家に引き取られるのが慣例だが、
白河天皇はそれを許さず、傍で病気の治癒を祈り、息をひきとる時も
賢子の手を握って見送り、その亡骸を3日3晩離すことはなかったという。
白河天皇は、悲観のあまり、政治や公式行事に出ることもなく、
法勝寺に阿弥陀仏と常行堂を建立し、ひたすら賢子の供養に勤めていた。
(7)息子への譲位にこだわる白河天皇
中宮賢子の死の翌年、弟で皇太子の「実仁(さねひと)親王」が病死すると、
白河天皇は、精力的に動き出した。
父帝「後三条天皇」の遺言では、天皇譲位は兄弟の順に継ぐよう言い渡されてあり、
皇太子は、弟の「実仁親王」が父帝によって立てられていた。
その皇太子が亡くなった場合、本来はその下の弟である「輔仁親王」を皇太子とする
はずであったが、白河天皇は先帝との約束を破棄してそれを許さず、
8歳の息子の「善仁(よしひと)親王」を、立太子と同時に、堀川天皇として譲位した。
堀川天皇は、中宮賢子の子である。
(8)側近を固める
白河上皇は、堀川天皇の後見人として、院から政治を執る仕組みを作った。
当時の摂政は、中宮賢子の養父「藤原師実」であったが、養父は外戚に当たらないとして、
摂政藤原家を軽んじた。
院庁別当には、左大臣:大江匡房
大納言:白河上皇の母方の叔父、藤原実季(さねすえ)など、
上皇の近親者や、乳母の近親者5人を含んだ。
さらに、近臣として、乳母の関係者を取り立てたり、
親衛隊として、「北面の武士」を組織して、身辺警護にあたらせた。
こうした、身分の階級に拘らず、白河上皇の気持ち1つで動く院の政治に
対して、人々は敏感に反応し、我先にと白河上皇に贈り物(賄賂)を贈った。
平正盛も、うまく白河上皇にとりいった一人である。
(9)鳥羽離宮
白河上皇は、陸路と水路の交わる、朱雀大路の真南の位置に、
新しい都を作って、移り住んだ。その地を「鳥羽離宮」と言う。
(10)女堤子内親王と祇園女御
白河上皇は、中宮賢子の忘れ形見として、第一皇「女堤子ていし(やすこ)内親王」を、
他の皇子、皇女とは別として深く寵愛し、郁芳門院(ゆうほうもんいん)の称号を与えた。
しかし、1096年、京都中が田楽に狂っている最中、田楽が大好きだった女堤子内親王
が急死した。白河上皇の落胆は激しく、剃髪出家するほどであった。
出家後の白河法王は、放蕩三昧に明け暮れ、人妻であった「祇園女御」を寵愛するように
なり、妃や中宮にも劣らぬ権威を振るうようになる。
(11)待賢門院璋子
祇園女御を寵愛していた白河法王は、「藤原公実」に美しい娘が生まれたと知り、
祇園女御の養女として貰い受けた。
しかし、法王はその幼女である「待賢門院璋子」を懐に入れて寝る程の寵愛ぶりで、
後に、白河法皇と待賢門院璋子の関係は、公然たる秘密となっていく。
のちに璋子を、孫の「鳥羽天皇」の妻として入内させるが、入内後も法王との
関係は続いたとみられ、璋子の産んだ「顕仁親王、のちの崇徳天皇」のことを、
夫の鳥羽天皇は「叔父子(おじこ)」と呼んで嫌い、のちの天皇系統に影響を及ぼしていく。










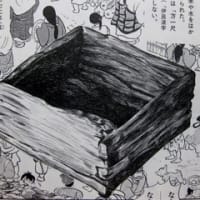









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます