(1)欠史八代とは
「古事記」「日本書記」に登場する天皇のうち、初代神武天皇を除く2代~8代までは、
史実上実在していないと考えられている。(初代もだけど)
(2)初代:神武天皇
神武天皇とは、死後に贈られる漢語風の名で、生存時は和名を複数持っている。
神武天皇の代表的な名は「神日本磐余彦天皇・かむやまといわれびこすめらのみこと」と、
「始くに天下之天皇・はつくにしらす」で、ある。
磐余(いわれ)とは、奈良県桜井市~橿原市一帯の地名で、神武の即位地とされ、
現在は「橿原神宮」が置かれてある。
即位は紀元前660年2月11日と推定されているが、紀元前に大和政権があったとは
考えにくい。
神話によると、天孫族の末裔の父と、竜宮族の娘「玉依姫」との間に生まれ、
当初は九州の日向国を治めていたが、葦原中国の統治をめざして、熊野から大和を
めざし、天照大神の神剣や、高木神の使いの八咫烏の助けを受け手、大和の荒ぶる
神を鎮め、畝傍の橿原で即位した、とある。
母親は、大阪の摂津と関係深く、皇后の父は「古事記」では三輪大社の大物主神、
「日本書記」では葛城山の事代主命であることから、摂津と大和の勢力が、大和政権
の設立に関わったと考えらる。
(2)2代:綏靖天皇(すいぜい)
神武天皇の第3子で、兄達を殺して王位に就いている。
初期の大和の豪勢である葛城族のシンボルである、事代主神(ことしろぬしのかみ)
の娘を皇后とし、葛城高丘宮(奈良県御所市)に皇居を定めた、とされる。
人肉を食う習性があり、朝夕7人の人間を食べ、幽閉されたと伝わる。
(3)3代:安寧天皇(あんねい)
事代主神の娘を母とし、事代主神のひ孫を皇后にしており、葛城一族の勢力がうかがえる。
(4)4代:いとく天王
姪を皇后としており、以前葛城氏、特に鴨(賀茂)氏とのつながりが深い。
(5)5代:孝昭天皇(こうしょう)
天皇自身は、葛城一族だがその后が、愛知県に勢力を持ち、「火明命・ほあかりのみこと」
を祖神とする大豪族の尾張一族の娘となっている。
葛城族と、尾張族の同盟関係の可能性がある。
(6)6代:孝安天皇(こうあん)
同母兄に、「天足彦国押彦国押人命」がおり、この人物が、奈良県添上郡を
本拠地とした「和邇わに氏」の遠祖とそれている。
その家系から、春日臣、大阪臣、大宅臣、小野臣、柿本臣など、古代朝廷の
重鎮一族が枝分かれしている。
(7)7代:孝霊天皇(こうれい)
息子の「彦五十狭芹彦命・ひこいさせりひこのみこと・吉備津彦命」は、
弟の「稚武彦命・わかたけひこのみこと」と、犬飼部、猿飼部、鳥飼部らを
お供にして、吉備などの西海道を平定した。
この息子が、後に桃太郎のモデルとなる。
「日本書記」には、崇神天皇が地方支配の為に『四道将軍』を各地に派遣した
旨の記載があるが、この息子はその四道将軍のうちの一人である。
弟は、後の「吉備臣」の祖となったと伝えられている。
(8)8代:孝元天皇(こうげん)
実在説がある。
埼玉県の稲荷山古墳から出た鉄剣に、孝元天皇の長男「オオヒコ」の名が出てくる。
「オオヒコ」は、北陸担当の四道将軍として、崇神紀に登場する。
また、オオヒコの娘の「御間城姫命」は、事実上の初代天皇の崇神天皇の妻である。
(9)9代:開化天皇(かいか)
物部氏の祖である「大へそ杵命」の娘を皇后に迎えている。
息子は、四道将軍の、丹波担当。
「古事記」「日本書記」に登場する天皇のうち、初代神武天皇を除く2代~8代までは、
史実上実在していないと考えられている。(初代もだけど)
(2)初代:神武天皇
神武天皇とは、死後に贈られる漢語風の名で、生存時は和名を複数持っている。
神武天皇の代表的な名は「神日本磐余彦天皇・かむやまといわれびこすめらのみこと」と、
「始くに天下之天皇・はつくにしらす」で、ある。
磐余(いわれ)とは、奈良県桜井市~橿原市一帯の地名で、神武の即位地とされ、
現在は「橿原神宮」が置かれてある。
即位は紀元前660年2月11日と推定されているが、紀元前に大和政権があったとは
考えにくい。
神話によると、天孫族の末裔の父と、竜宮族の娘「玉依姫」との間に生まれ、
当初は九州の日向国を治めていたが、葦原中国の統治をめざして、熊野から大和を
めざし、天照大神の神剣や、高木神の使いの八咫烏の助けを受け手、大和の荒ぶる
神を鎮め、畝傍の橿原で即位した、とある。
母親は、大阪の摂津と関係深く、皇后の父は「古事記」では三輪大社の大物主神、
「日本書記」では葛城山の事代主命であることから、摂津と大和の勢力が、大和政権
の設立に関わったと考えらる。
(2)2代:綏靖天皇(すいぜい)
神武天皇の第3子で、兄達を殺して王位に就いている。
初期の大和の豪勢である葛城族のシンボルである、事代主神(ことしろぬしのかみ)
の娘を皇后とし、葛城高丘宮(奈良県御所市)に皇居を定めた、とされる。
人肉を食う習性があり、朝夕7人の人間を食べ、幽閉されたと伝わる。
(3)3代:安寧天皇(あんねい)
事代主神の娘を母とし、事代主神のひ孫を皇后にしており、葛城一族の勢力がうかがえる。
(4)4代:いとく天王
姪を皇后としており、以前葛城氏、特に鴨(賀茂)氏とのつながりが深い。
(5)5代:孝昭天皇(こうしょう)
天皇自身は、葛城一族だがその后が、愛知県に勢力を持ち、「火明命・ほあかりのみこと」
を祖神とする大豪族の尾張一族の娘となっている。
葛城族と、尾張族の同盟関係の可能性がある。
(6)6代:孝安天皇(こうあん)
同母兄に、「天足彦国押彦国押人命」がおり、この人物が、奈良県添上郡を
本拠地とした「和邇わに氏」の遠祖とそれている。
その家系から、春日臣、大阪臣、大宅臣、小野臣、柿本臣など、古代朝廷の
重鎮一族が枝分かれしている。
(7)7代:孝霊天皇(こうれい)
息子の「彦五十狭芹彦命・ひこいさせりひこのみこと・吉備津彦命」は、
弟の「稚武彦命・わかたけひこのみこと」と、犬飼部、猿飼部、鳥飼部らを
お供にして、吉備などの西海道を平定した。
この息子が、後に桃太郎のモデルとなる。
「日本書記」には、崇神天皇が地方支配の為に『四道将軍』を各地に派遣した
旨の記載があるが、この息子はその四道将軍のうちの一人である。
弟は、後の「吉備臣」の祖となったと伝えられている。
(8)8代:孝元天皇(こうげん)
実在説がある。
埼玉県の稲荷山古墳から出た鉄剣に、孝元天皇の長男「オオヒコ」の名が出てくる。
「オオヒコ」は、北陸担当の四道将軍として、崇神紀に登場する。
また、オオヒコの娘の「御間城姫命」は、事実上の初代天皇の崇神天皇の妻である。
(9)9代:開化天皇(かいか)
物部氏の祖である「大へそ杵命」の娘を皇后に迎えている。
息子は、四道将軍の、丹波担当。










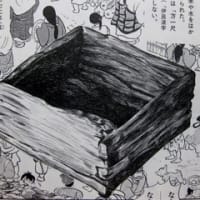









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます