(1)宇多天皇時代の菅原道真
菅原家は、代々学者の家で、「文章道」を教える文章博士の家であった。
845年に、菅原家に生まれた「阿古(あこ)」こと、「菅原道真」はめきめきと頭角をあらわし、
33歳で文章博士となり、讃岐の国司として、地方政治にもかかわった。
887年、京で政治の停滞を起こす[阿衡の紛議]が起きた時、讃岐国司だった菅原道真は、
太政大臣「藤原基経」に、怒りを鎮めて政治に戻るよう手紙をだし、宇多天皇を助けている。
「菅原道真」は、「源能有」と並んで、宇多天皇の寵愛をうけ、めざましい出世を続けていく。
宇多天皇時世の『寛平の治』とよばれる政治改革や、894年の『遣唐使の廃止』など。

その、目覚ましい出世の影で、妬み恨みを買っていくことにもなる。
896年、菅原道真の長女「衍子(ていし)」が、「斉世親王」女御として入内する。
(「斉世親王」は、次天皇「醍醐天皇」の弟で、この結婚をいいがかりとして、大宰府へとばされる。)
897年、宇多天皇は、藤原北家の譲位介入の対策として、まだ若い間に
子の醍醐天皇に譲位することを、北家の藤原時平に相談せず、菅原道真にだけ相談して決めた。
(2)遣唐使の廃止
894年、久しぶりの大事業である[遣唐使]の代表に任命された菅原道真であったが、
この頃の中国、朝鮮半島の荒れた情勢の中で交流するのは危険であること、また
中国から学ぶより、国内内政の充実を図ることを進言し、道真の提案で、遣唐使が廃止
されることとなった。

菅原道真が、日本の国風文化の充実を促したこととなる。
実際、中国も、朝鮮半島も8世紀中頃から乱れており、907年に唐が滅亡している。
唐滅亡後の中国は5代10国時代となり、朝鮮では新羅が滅び、高麗の支配となる。
さらに、926年に親交のあった「渤海国」も滅んでおり、激動の時代であった。
(3)醍醐天皇時代の菅原道真
譲位にあたり、宇多天皇は『除目』によって、最高位大納言「藤原時平」と大納言「菅原道真」の
2人に政治を任せる[内覧(ないらん) 」とするよう、公言する。しかし、これは他の官職達には
大変不評であったが、宇多上皇が不満を一蹴するなど、宇多上皇が醍醐天皇の後見人として、
政治に口出ししていた為、宇多による道真びいきは続いていた。

(4)昌泰の変
899年、宇多上皇が仁和寺で落飾、東大寺で受戒して、出家した。
そのとき、「藤原時平」は左大臣、「菅原道真」はそれに次ぐ右大臣にまで昇りつめていたが、
ここで、菅原道真は宇多上皇という強力な後ろ立てをなくすこととなる。
道真の存在が邪魔であった、諸官僚と藤原時平が、道真失墜に動き出す。
宇多上皇出家の翌年900年、「三善清行(みよしきよゆき)」から道真に、
突然の辞職勧告が送りつけられる。

「三善清行」は、父が承和の変に名を連ねたことから不遇の人生で、
苦労の中で勉学に励んだ53歳であった。
一説には、35歳で文章道の受験をしたときの試験官が若い道真で、
不合格にされた恨みが残っている、とも言われるが、『意見封事』での意見などを
見ると、冷静に、時の情勢と正しい政治を見ていた人なのかもしれない。
901年、醍醐天皇の元に、菅原道真が醍醐天皇を降ろして、娘婿の「斉世親王」を
次の天皇に就ける謀反を企てているとの密告が入り、九州大宰府の権帥へ引き摺り下ろされた。
この事は宇多法皇にも寝耳に水で、驚いた宇多法皇は、醍醐天皇に直談判する為に
裸足で駆けつけたが、上皇であれど、天皇の許可なく内裏に入るべからずとの
自分で作った法によって、門前払いされ、宇多法皇は、門の前で一日中立ち尽くしていたという。

この時蔵人頭として、宇多法王を足止めした藤原菅根は後に落雷で死亡する。
道長の子供達も、妻と幼児を除いて地方へとばされる。
京の屋敷を出るときに詠んだ歌が、有名である。
「こちふかば にほひをこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな」

意味:梅の花よ 来年の冬の終わりを告げる東の風がふいたなら、
その花を咲かせておくれ。この家に主人が居なくとも、春を忘れたりせずに。
九州大宰府では、今にも倒れそうなボロ屋に閉じこもり、悲しい歌ばかりを
詠んでいたが、2年後の903年に寂しく亡くなった。
(5)菅原道真の呪い
・903年、菅原道真が大宰府で死去。
・道真の怨霊は没後すぐに、比叡山に現れたと『北野天神縁起』には記されている。
座主が差し出したザクロを食べて、口から出した種が燃えたという。

・906年、道真を大宰府に飛ばした当時藤原時平派であった「中納言定国」は40歳で死亡。
・908年、当時の蔵人頭で、宇多法王を門前払いにした「藤原菅根」は、落雷で死亡。

・909年、藤原時平が39歳で病死。

時平の元に蛇に化身した怨霊が現れ、時平を苦しめつつ殺した、という。
時平の子供達も、次男の「顕忠(あきただ)を除いて全員が相次いで病死。
・910年、京都を暴風雨が襲う。

・911年、大安寺、消失
・913年、道真を飛ばした一人「源光(みなもとのひかる)」は狩りの最中に泥沼に
はまり、その遺体が出てくる事はなかった。

・藤原時平の死後は、弟の「藤原忠平」が醍醐天皇の側近となるが、
伝染病の流行と、天候不順が続き、914年の班田収受の年は対応に苦慮した。

・918年、東寺の金堂が落雷で焼失。
淀川が氾濫して、死者多数でる。
・923年、醍醐天皇と藤原時平の妹の子で、皇太子の「保明親王」が21歳で病死。
『日本書記』によると、この事で道真公の怨霊への恐れは都中で爆発した。
天下庶民、悲泣しない者はない。世をあげて言う、菅帥の怨霊のなすことである、と。

・925年、保明親王の子で、次の皇太子「慶頼王」も、わずか5歳で死亡。

・決定的だったのは、930年、突然愛宕山より沸き立った黒雲から、落雷が
清涼殿に落ち、清涼殿に詰めていた官職が2人焼死、多数負傷している。

・落雷事件以来、醍醐天皇は床に伏し、同年死去。
残された8歳の「寛明皇太子」が「朱雀天皇」として即位する。
・931年、宇多法王、没
・徹底して祟られた藤原時平一族の中で、唯一たたりから免れたのは、弟「藤原忠平」であった。
忠平は当時参議を辞退し、[昌泰の変]に関与しておらず、また宇多法皇との関係もよく、
大宰府の菅原道真に、時折手紙を出していた為、祟りから逃れた、と言われた。
道真の怨霊は、天台宗の密教によって増幅され、全国に広められた。
また、東国の平将門の乱では、将門は反乱を正当化する為「道真の霊魂」を
振りかざして戦ったという。
こうした不吉な出来事と、落雷が菅原道真を「雷神」へと仕立てていった。

836年、天神地祇が北野に祭られた。
959年、右大臣「藤原師輔」によって、神殿増築、
987年、官幣社となる。
993年、道真に左大臣と、太政大臣の位が贈られた。
平安時代、怨霊として恐れられていた荒神が、
鎌倉時代には、冤罪を救う神となり次第に信仰の対象への変化し、
現在では、その賢さにちなんで、「学問の神」として親しまれている。
菅原家は、代々学者の家で、「文章道」を教える文章博士の家であった。
845年に、菅原家に生まれた「阿古(あこ)」こと、「菅原道真」はめきめきと頭角をあらわし、
33歳で文章博士となり、讃岐の国司として、地方政治にもかかわった。
887年、京で政治の停滞を起こす[阿衡の紛議]が起きた時、讃岐国司だった菅原道真は、
太政大臣「藤原基経」に、怒りを鎮めて政治に戻るよう手紙をだし、宇多天皇を助けている。
「菅原道真」は、「源能有」と並んで、宇多天皇の寵愛をうけ、めざましい出世を続けていく。
宇多天皇時世の『寛平の治』とよばれる政治改革や、894年の『遣唐使の廃止』など。

その、目覚ましい出世の影で、妬み恨みを買っていくことにもなる。
896年、菅原道真の長女「衍子(ていし)」が、「斉世親王」女御として入内する。
(「斉世親王」は、次天皇「醍醐天皇」の弟で、この結婚をいいがかりとして、大宰府へとばされる。)
897年、宇多天皇は、藤原北家の譲位介入の対策として、まだ若い間に
子の醍醐天皇に譲位することを、北家の藤原時平に相談せず、菅原道真にだけ相談して決めた。
(2)遣唐使の廃止
894年、久しぶりの大事業である[遣唐使]の代表に任命された菅原道真であったが、
この頃の中国、朝鮮半島の荒れた情勢の中で交流するのは危険であること、また
中国から学ぶより、国内内政の充実を図ることを進言し、道真の提案で、遣唐使が廃止
されることとなった。

菅原道真が、日本の国風文化の充実を促したこととなる。
実際、中国も、朝鮮半島も8世紀中頃から乱れており、907年に唐が滅亡している。
唐滅亡後の中国は5代10国時代となり、朝鮮では新羅が滅び、高麗の支配となる。
さらに、926年に親交のあった「渤海国」も滅んでおり、激動の時代であった。
(3)醍醐天皇時代の菅原道真
譲位にあたり、宇多天皇は『除目』によって、最高位大納言「藤原時平」と大納言「菅原道真」の
2人に政治を任せる[内覧(ないらん) 」とするよう、公言する。しかし、これは他の官職達には
大変不評であったが、宇多上皇が不満を一蹴するなど、宇多上皇が醍醐天皇の後見人として、
政治に口出ししていた為、宇多による道真びいきは続いていた。

(4)昌泰の変
899年、宇多上皇が仁和寺で落飾、東大寺で受戒して、出家した。
そのとき、「藤原時平」は左大臣、「菅原道真」はそれに次ぐ右大臣にまで昇りつめていたが、
ここで、菅原道真は宇多上皇という強力な後ろ立てをなくすこととなる。
道真の存在が邪魔であった、諸官僚と藤原時平が、道真失墜に動き出す。
宇多上皇出家の翌年900年、「三善清行(みよしきよゆき)」から道真に、
突然の辞職勧告が送りつけられる。

「三善清行」は、父が承和の変に名を連ねたことから不遇の人生で、
苦労の中で勉学に励んだ53歳であった。
一説には、35歳で文章道の受験をしたときの試験官が若い道真で、
不合格にされた恨みが残っている、とも言われるが、『意見封事』での意見などを
見ると、冷静に、時の情勢と正しい政治を見ていた人なのかもしれない。
901年、醍醐天皇の元に、菅原道真が醍醐天皇を降ろして、娘婿の「斉世親王」を
次の天皇に就ける謀反を企てているとの密告が入り、九州大宰府の権帥へ引き摺り下ろされた。
この事は宇多法皇にも寝耳に水で、驚いた宇多法皇は、醍醐天皇に直談判する為に
裸足で駆けつけたが、上皇であれど、天皇の許可なく内裏に入るべからずとの
自分で作った法によって、門前払いされ、宇多法皇は、門の前で一日中立ち尽くしていたという。

この時蔵人頭として、宇多法王を足止めした藤原菅根は後に落雷で死亡する。
道長の子供達も、妻と幼児を除いて地方へとばされる。
京の屋敷を出るときに詠んだ歌が、有名である。
「こちふかば にほひをこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな」

意味:梅の花よ 来年の冬の終わりを告げる東の風がふいたなら、
その花を咲かせておくれ。この家に主人が居なくとも、春を忘れたりせずに。
九州大宰府では、今にも倒れそうなボロ屋に閉じこもり、悲しい歌ばかりを
詠んでいたが、2年後の903年に寂しく亡くなった。
(5)菅原道真の呪い
・903年、菅原道真が大宰府で死去。
・道真の怨霊は没後すぐに、比叡山に現れたと『北野天神縁起』には記されている。
座主が差し出したザクロを食べて、口から出した種が燃えたという。

・906年、道真を大宰府に飛ばした当時藤原時平派であった「中納言定国」は40歳で死亡。
・908年、当時の蔵人頭で、宇多法王を門前払いにした「藤原菅根」は、落雷で死亡。

・909年、藤原時平が39歳で病死。

時平の元に蛇に化身した怨霊が現れ、時平を苦しめつつ殺した、という。
時平の子供達も、次男の「顕忠(あきただ)を除いて全員が相次いで病死。
・910年、京都を暴風雨が襲う。

・911年、大安寺、消失
・913年、道真を飛ばした一人「源光(みなもとのひかる)」は狩りの最中に泥沼に
はまり、その遺体が出てくる事はなかった。

・藤原時平の死後は、弟の「藤原忠平」が醍醐天皇の側近となるが、
伝染病の流行と、天候不順が続き、914年の班田収受の年は対応に苦慮した。

・918年、東寺の金堂が落雷で焼失。
淀川が氾濫して、死者多数でる。
・923年、醍醐天皇と藤原時平の妹の子で、皇太子の「保明親王」が21歳で病死。
『日本書記』によると、この事で道真公の怨霊への恐れは都中で爆発した。
天下庶民、悲泣しない者はない。世をあげて言う、菅帥の怨霊のなすことである、と。

・925年、保明親王の子で、次の皇太子「慶頼王」も、わずか5歳で死亡。

・決定的だったのは、930年、突然愛宕山より沸き立った黒雲から、落雷が
清涼殿に落ち、清涼殿に詰めていた官職が2人焼死、多数負傷している。

・落雷事件以来、醍醐天皇は床に伏し、同年死去。
残された8歳の「寛明皇太子」が「朱雀天皇」として即位する。
・931年、宇多法王、没
・徹底して祟られた藤原時平一族の中で、唯一たたりから免れたのは、弟「藤原忠平」であった。
忠平は当時参議を辞退し、[昌泰の変]に関与しておらず、また宇多法皇との関係もよく、
大宰府の菅原道真に、時折手紙を出していた為、祟りから逃れた、と言われた。
道真の怨霊は、天台宗の密教によって増幅され、全国に広められた。
また、東国の平将門の乱では、将門は反乱を正当化する為「道真の霊魂」を
振りかざして戦ったという。
こうした不吉な出来事と、落雷が菅原道真を「雷神」へと仕立てていった。

836年、天神地祇が北野に祭られた。
959年、右大臣「藤原師輔」によって、神殿増築、
987年、官幣社となる。
993年、道真に左大臣と、太政大臣の位が贈られた。
平安時代、怨霊として恐れられていた荒神が、
鎌倉時代には、冤罪を救う神となり次第に信仰の対象への変化し、
現在では、その賢さにちなんで、「学問の神」として親しまれている。










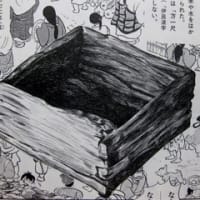









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます