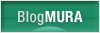昨日のお話のつづきで、いろんな資料を読んでました。
去年、厚生労働省が発表した「2006年賃金構造基本統計調査結果」によると、医師の所定内給与(月額)は76万1000円(平均41.2歳)だそうです。労働時間は週に70時間くらいだと書かれてました。
でも、医師会が発表した報告(pdf)はちょっと泣けます。
実は、勤務医はもっと給料が安いし、もっと働いています。時給に計算すると、2000円にもならなくて、「派遣社員の彼女の方が時給が高い」なんて先生もいました(笑)
あとは、お医者さんは、激務なわりに、労働基準法の保護から抜け落ちがち。
ご自身も闘病中の先生に病院でばったり会ったら、真っ青なお顔だったので、「どうしたんですか!?」と聞いたら、夜の1時に、患者さんのご家族が話をしたいと呼ばれて、朝までずっと話をしてたとか。それでも、「監視又は断続的労働に従事する者」という扱いで、労働基準法の除外項目(第41条第3号)扱いにされたりするそうな。だから、翌日に代休なんて保護はありません(泣)
たとえば、心療内科がカウンセリングと連携するみたいに、連携できる医療情報アドバイザーや相談窓口が増えたら、ちょっとはお医者さんの負担も軽くなって、診察の時間や質もあがるんじゃないかなぁ。
苦労して受験して、苦労して研修して、それでも患者さんに「どうしてですか!?」と詰め寄られたり、裁判になったり…。
問題のある先生もいるし、お医者さんの肩を持つわけではないけれど、「病気の人を救いたい!」という気持ちだけでは、つづかない、たいへんなお仕事だなと思います。
統計上、40代のお医者さんがどんどん、患者数の少ない小さなクリニックに移っていっている傾向にあるし、もう何とかしないといけない状況になっているような気が…。
頼りになるお医者さんたちが足りなくなったら、困るなぁ。
※後日、「救命医宿直7割『違法』」と題するこんな記事を発見。地元の労働基準監督署が改善指導するみたいです。うまく改善されるといいですね。
 ←参加中!ポチッで応援ありがとうございます♪
←参加中!ポチッで応援ありがとうございます♪
去年、厚生労働省が発表した「2006年賃金構造基本統計調査結果」によると、医師の所定内給与(月額)は76万1000円(平均41.2歳)だそうです。労働時間は週に70時間くらいだと書かれてました。
でも、医師会が発表した報告(pdf)はちょっと泣けます。
実は、勤務医はもっと給料が安いし、もっと働いています。時給に計算すると、2000円にもならなくて、「派遣社員の彼女の方が時給が高い」なんて先生もいました(笑)
あとは、お医者さんは、激務なわりに、労働基準法の保護から抜け落ちがち。
ご自身も闘病中の先生に病院でばったり会ったら、真っ青なお顔だったので、「どうしたんですか!?」と聞いたら、夜の1時に、患者さんのご家族が話をしたいと呼ばれて、朝までずっと話をしてたとか。それでも、「監視又は断続的労働に従事する者」という扱いで、労働基準法の除外項目(第41条第3号)扱いにされたりするそうな。だから、翌日に代休なんて保護はありません(泣)
たとえば、心療内科がカウンセリングと連携するみたいに、連携できる医療情報アドバイザーや相談窓口が増えたら、ちょっとはお医者さんの負担も軽くなって、診察の時間や質もあがるんじゃないかなぁ。
苦労して受験して、苦労して研修して、それでも患者さんに「どうしてですか!?」と詰め寄られたり、裁判になったり…。
問題のある先生もいるし、お医者さんの肩を持つわけではないけれど、「病気の人を救いたい!」という気持ちだけでは、つづかない、たいへんなお仕事だなと思います。
統計上、40代のお医者さんがどんどん、患者数の少ない小さなクリニックに移っていっている傾向にあるし、もう何とかしないといけない状況になっているような気が…。
頼りになるお医者さんたちが足りなくなったら、困るなぁ。
※後日、「救命医宿直7割『違法』」と題するこんな記事を発見。地元の労働基準監督署が改善指導するみたいです。うまく改善されるといいですね。