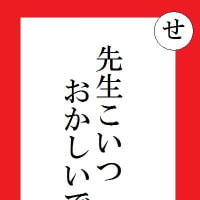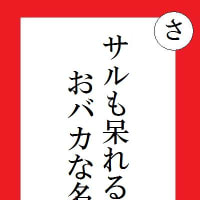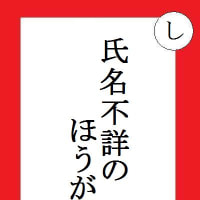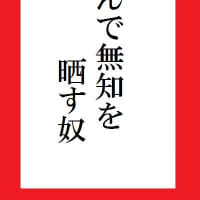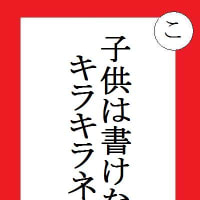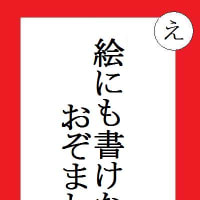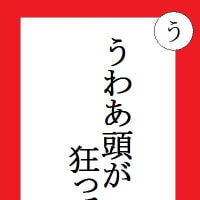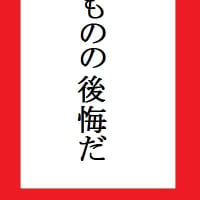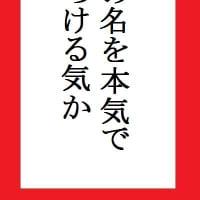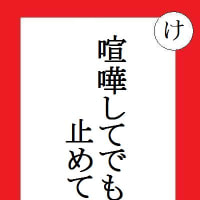2.ハイ・レベル対話の活性化
2008年下半期以降の国際金融危機の発生や地球環境問題の深刻化、北朝鮮の核開発によ
り表面化した大量破壊兵器(WMD)の開発と拡散、そして東アジアの共生のための地域
秩序の構築といった課題は、グローバル国家として成長した日本と韓国に、より能動的な
共同対応を求めている。
日韓両国の間では、首脳によるシャトル外交をはじめ、外交、国防、経済、環境など領
域ごとの閣僚会議が定期的に実施されてきた。近年では、日韓間にとどまらず、日韓中三
国間でも首脳会談や領域別の閣僚会議、外務次官級戦略対話などが定例的に開催されるよ
うになっている。日韓中首脳会談が2008年から毎年開催されるようになったことは記憶に
新しい。
新時代の日韓関係は、このような領域ごとの協力を、政治・安全保障・経済・文化・情
報知識・科学技術・環境生態など領域横断的な協調と協力の緊密なネットワークへと深化
させていくべきである。複数の領域にわたる包括的イシューに共同対処していくために、
両国首脳や関連閣僚、主要政治家などが参加するハイ・レベル対話を必要に応じていつで
も開催することは、複合ネットワークの構築にとって不可欠の要請である。
このようなハイ・レベル対話の活性化により、日韓両国は、多様なイシューに対する協
力の推進状況を点検するとともに、協力を進めていくなかで明らかになった問題点を修正、
補完していくことができる。また、日韓協力の課題を持続的に発掘していくことも可能と
なる。日韓新時代のハイ・レベル対話は、二国間の争点のみならず、東アジアおよびグロ
ーバルな領域の協力分野にわたる争点を広範囲に議論する場になることを期待する。
11
3.交流ネットワークの多層化
日韓間の対話チャンネルは重層化され、すそ野はより一層拡大されることが望ましい。
そのためには、各界の老・壮・青の広い世代がバランスよく参加できる配慮が必要である。
まず、政治分野のネットワーク構築のためには、超党派若手議員の定期交流、日韓首脳
のシャトル外交をフォローアップする民間主導の有識者(研究者、経済人、官界出身者等)
会議の設置などが考えられる。
地方自治体間の協力ネットワーク構築も重要である。すでに100を超える姉妹都市協定や
友好提携が結ばれているが、2006年に設立された「福岡−釜山フォーラム」のように、経済
的効果を期待する越境型の地域連携(地域FTAを含む)が促進されてもよい。また、両
国間で歴史認識問題や領土問題により政治・外交面が緊張したとしても、地方自治体主導
の交流行事等は、中止・延期・規模縮小に追い込まれるべきではない。
これまで、日韓両国の官と民、中央と地方が協力する文化交流行事の存在は、実質的に
も象徴的にも大きな意義を持ってきた。今後は、イベント型だけでなく、相手国の文化等
を知ろうとする活動があってもよい。
一方、草の根交流は基本的には民間主導により発展していくものである。但し、双方を
結びつけるチャンス、人材や言葉の壁をケアするお手伝い、的確な情報提供、誤解の生じ
やすい場面での調整、経済的助成など、政府、地方自治体、公的団体からの一定の支援は
依然として有効である。とりわけ、青少年交流は効果をあげており、若者が相手国を大量
に訪問できるプログラムをさらに充実させることが望ましい。急速に少子・高齢化社会に
なりつつある両国にとって、青少年交流ばかりでなく、両国の中高年交流、シルバー交流
に支援策や激励策があってもよい。
これまでも、少子・高齢化、年金、医療・介護、雇用、環境、ジェンダー、教育、障害
者、生涯教育など共通課題をテーマにした両国間の草の根交流が各地で行われてきた。類
似した社会構造の日韓間で議論することで、こうした課題への解決策が提示されることも
十分ありうる。今後も、このような共通課題を扱う学術共同研究や共同シンポジウム開催
を奨励していくべきである。
12
2008年下半期以降の国際金融危機の発生や地球環境問題の深刻化、北朝鮮の核開発によ
り表面化した大量破壊兵器(WMD)の開発と拡散、そして東アジアの共生のための地域
秩序の構築といった課題は、グローバル国家として成長した日本と韓国に、より能動的な
共同対応を求めている。
日韓両国の間では、首脳によるシャトル外交をはじめ、外交、国防、経済、環境など領
域ごとの閣僚会議が定期的に実施されてきた。近年では、日韓間にとどまらず、日韓中三
国間でも首脳会談や領域別の閣僚会議、外務次官級戦略対話などが定例的に開催されるよ
うになっている。日韓中首脳会談が2008年から毎年開催されるようになったことは記憶に
新しい。
新時代の日韓関係は、このような領域ごとの協力を、政治・安全保障・経済・文化・情
報知識・科学技術・環境生態など領域横断的な協調と協力の緊密なネットワークへと深化
させていくべきである。複数の領域にわたる包括的イシューに共同対処していくために、
両国首脳や関連閣僚、主要政治家などが参加するハイ・レベル対話を必要に応じていつで
も開催することは、複合ネットワークの構築にとって不可欠の要請である。
このようなハイ・レベル対話の活性化により、日韓両国は、多様なイシューに対する協
力の推進状況を点検するとともに、協力を進めていくなかで明らかになった問題点を修正、
補完していくことができる。また、日韓協力の課題を持続的に発掘していくことも可能と
なる。日韓新時代のハイ・レベル対話は、二国間の争点のみならず、東アジアおよびグロ
ーバルな領域の協力分野にわたる争点を広範囲に議論する場になることを期待する。
11
3.交流ネットワークの多層化
日韓間の対話チャンネルは重層化され、すそ野はより一層拡大されることが望ましい。
そのためには、各界の老・壮・青の広い世代がバランスよく参加できる配慮が必要である。
まず、政治分野のネットワーク構築のためには、超党派若手議員の定期交流、日韓首脳
のシャトル外交をフォローアップする民間主導の有識者(研究者、経済人、官界出身者等)
会議の設置などが考えられる。
地方自治体間の協力ネットワーク構築も重要である。すでに100を超える姉妹都市協定や
友好提携が結ばれているが、2006年に設立された「福岡−釜山フォーラム」のように、経済
的効果を期待する越境型の地域連携(地域FTAを含む)が促進されてもよい。また、両
国間で歴史認識問題や領土問題により政治・外交面が緊張したとしても、地方自治体主導
の交流行事等は、中止・延期・規模縮小に追い込まれるべきではない。
これまで、日韓両国の官と民、中央と地方が協力する文化交流行事の存在は、実質的に
も象徴的にも大きな意義を持ってきた。今後は、イベント型だけでなく、相手国の文化等
を知ろうとする活動があってもよい。
一方、草の根交流は基本的には民間主導により発展していくものである。但し、双方を
結びつけるチャンス、人材や言葉の壁をケアするお手伝い、的確な情報提供、誤解の生じ
やすい場面での調整、経済的助成など、政府、地方自治体、公的団体からの一定の支援は
依然として有効である。とりわけ、青少年交流は効果をあげており、若者が相手国を大量
に訪問できるプログラムをさらに充実させることが望ましい。急速に少子・高齢化社会に
なりつつある両国にとって、青少年交流ばかりでなく、両国の中高年交流、シルバー交流
に支援策や激励策があってもよい。
これまでも、少子・高齢化、年金、医療・介護、雇用、環境、ジェンダー、教育、障害
者、生涯教育など共通課題をテーマにした両国間の草の根交流が各地で行われてきた。類
似した社会構造の日韓間で議論することで、こうした課題への解決策が提示されることも
十分ありうる。今後も、このような共通課題を扱う学術共同研究や共同シンポジウム開催
を奨励していくべきである。
12