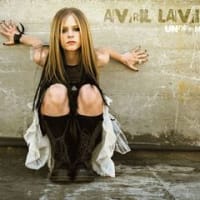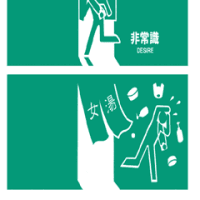昨日読んでいた梶井基次郎の「筧の話」を、
ぼくなりに現代文に近づけてみました。
風景描写が繊細で、
あらすじとして紹介するのは勿体無いので、
ところどころ倒置してみたり、
切り取ったり、
表現を変えてみたりしました。
「筧」と言うのは、
水を送り流す管のことなのですが、
そこからは水の流れを見ることができず、
はたしてこの水音はどこから聴こえてくるのだろう、
ということがこの話の内容で、
けっきょく男は水音を目で見ることはできません。
現れては消える水音の閃光と、
あとに残る暗闇、
男が生きる現実の世界を、
この水音探しにたとえているのですが、
読んでみると、
重要なことは結末だけではなく、
山道の美しさも、
男が常々抱えている不安も、
重要だということが読み取れます。
しかし、
読みにくい。
まず始めの街道と山道の話。
街道の話がいつか出てくるかもしれない、
とあたまの片隅に置いていると、
山道の風景描写が始まって、
ああこれは山道の話か、
と思っていると、
長々と続く山道の風景描写は、
本筋とあまり関係のないところに位置しています。
そのふらふらした状態で筧の話に入ると、
話の筋はおおよそ見当がつくけれど、
どうも本質を捉えていないような、
消化不良の状態になります。
そこから青い花の暗喩に入り、
次に閃光と暗闇の暗喩。
最後に生の幻影と絶望の暗喩で締められているから、
ぼーっと読んでいると、
本筋すら意味が分からなくなってしまいます。
これは、近代小説だから、
ということではなく、
現代を生きていくなかで、
少しずつ感性が失われているのでは?
という懸念があります。
音にしてみても、
車の音、
工事の音、
昭和はじめごろになかった様々な音によって、
思考はかく乱されてしまいます。
見るにしても、
テレビのチャンネル、
スーパーの食品、
人ごみで会う様々な人たちによって、
思考はかく乱させられてしまいます。
本来ならこのように簡約せず、
原文のもつ文字の世界に浸っていたいのですが、
現代を生きているぼくには難しいです。