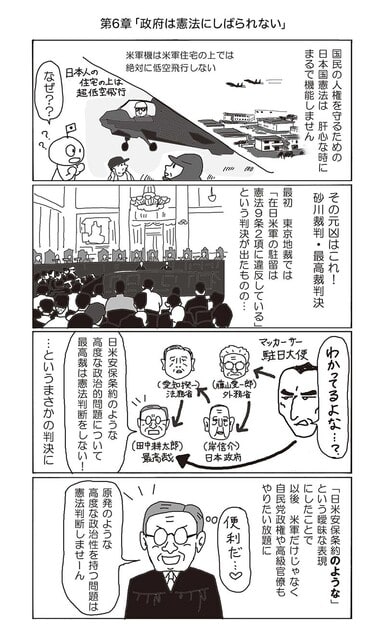孫崎享氏の『 戦後史の正体 1945-2012 』を読みました。
以前読んだのですが、どうしても読み返してみたいと思った本です。
やはり、読み返すと新しい発見が多くありました。
忘れたくないところに貼る付箋も、ずいぶん違う場所に貼り替えたりしました。
内容は・・・
はじめに
序 章 なぜ「高校生でも読める」戦後史の本を書くのか
第一章 「終戦」から占領へ
第二章 冷戦の始まり
第三章 講和条約と日米安保条約
第四章 保守合同と安保改定
第五章 自民党と経済成長の時代
第六章 冷戦終結と米国の変容
第七章 9.11とイラク戦争後の世界
あとがき
資料① ポツダム宣言
資料② 降伏文書
資料③ 年表
ベストセラーになっただけの充実した内容の本です。
戦後の日米関係を、米国の圧力を軸に「高校生にも読める本」を意識し記されたものです。
ネットのレビューに『高校の教科書にすべき』などと書いた人がいましたが、本当にそう思わせるものです。
内向きになりがちで、自分の考えに近い意見の中だけで生活している若い世代の人には、この本に触れて「視野」を広げ、表面化しない見えにくいところに視線を向けることが、より良い未来の選択に繋がる気がします。
本当に読み返して良かった。
戦後日本を支えてきた高齢世代も、読んで気づくことはとても楽しいことだと思うのです。