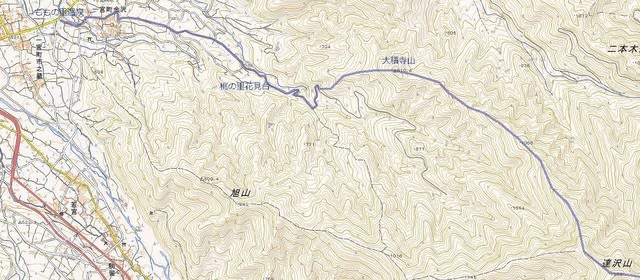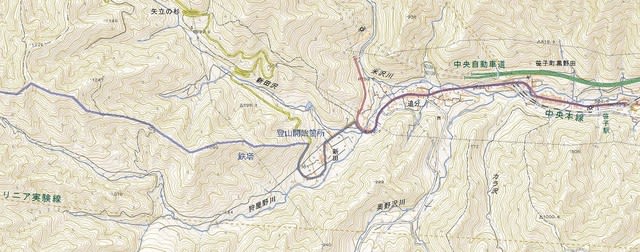2018年5月2日(水)
今回は連休に帰省して実家近くの山での山菜取り。
子供の頃からトド山と言っていたが、正式名称は知らない。
地図にも記載がなかったのでとりあえず自分で書き込んでみた。
◎ 地図
登山のコンパスより(山名は追記)

◎ 山菜取り
かつては外部からの山菜取りの人も排除していなかったが、農道に車を止めて山に入る迷惑な人が出てきて
農作業の支障となっていた。そのため最近は農道入口にチェーンをして外部者の山菜取り禁止の看板が出ている。

・フキノトウ,ツクシ
これは大抵の人がわかると思う。
今年は雪溶けが早かったので、フキノトウは成長しすぎて、ちょうどいいのはほとんどなし。
フキノトウはテンプラ・フキ味噌などで食す。ツクシはおひたしくらいだが、手間がかかる割に
食べ応えがないのでパス。



・ウド
山のウドは緑が濃くにおいも強い。あまり大きくならないものの根元を少し掘り込み、カマ
などで切断。”ウドの大木”と言うように、大きくなり過ぎたものは固くなって食えない。
採りたてなら皮をむいて味噌付けて食べてもよし。酢味噌和えでもよし、いためてもよし、
テンプラにしてもよし、用途の広い山菜である。


・ワラビ
雪溶けが早かったため、ワラビが最盛期。あちこちに食べごろワラビが顔を出してる。葉先
があまり広がっていない状態のものが柔らかい。指先でひねって折れるところから採取する。
重曹(3g/ℓ)か灰であく抜きをする。今回は藁灰を使用。ワラビに灰を振りかけて、全体が
浸る量のお湯を注ぐ。そのまま一晩放置。翌朝水洗いすれば、おひたしなどで食べられる。
ワラビは煮込むと溶けるのでご注意を。


・キノメ
わが田舎ではミツバアケビの新芽を”キノメ”と称して食用にする。指先でひねって折れる
所から採取する。時期が良ければ結構いたるところに出ているので、太いものを選んで採る。
ゆでるだけで食べられてほろ苦い。個人的には卵(黄身のみ)醤油で食べるのがうまい。



・タラノメ
早すぎたり遅すぎたりでちょうどいいサイズが見つけられず。枝のトゲが目印


・ゼンマイ
先っぽがくるくる巻いて綿がかぶっていたりもする。まとまって生えている中に何本か
葉っぱ部分が丸くなっているものが混じっていることがある。地元ではこれをその形から、
”きんた〇ゼンマイ”と呼んで採らずに残す。この球形の部分は胞子葉であり、ゼンマイ
が繁殖するための胞子を持っている。
通常はゆでて天日干しにしながらもんで乾燥ゼンマイにし、それを水でもどして食す。
重曹であく抜きして食べられるとのことでやり始めたが、時間切れで今回は食すにいたらず。


・コゴミ
ゆでるだけで食べられるくせのない山菜。からし醤油でもマヨネーズでもうまい。雪が
溶けてすぐの湿地に出るものが太くておいしい。成長するとシダのように広がる。



◎ 春山の注意
※ 雪渓
豪雪地帯は連休でも日陰では結構雪が残っている。山菜取りで移動している時に、雪渓を
歩きたくなることがあるが、やめておいたほうがいい。雪の下が空洞で川が隠れていることが
よくある。


※ ヘビ
春になるとヘビも動き出す。山菜取りで藪の中を歩いたり、不用意に藪に手を突っ込むと
へびにかまれることがある。マムシは頭が三角形ですぐわかると思うが、ヤマカガシは一見
毒蛇には見えない。ヤマカガシは臆病なヘビですぐ逃げるので、わざわざ捕まえていじらな
ければ大丈夫だとは思うが、その毒性はマムシの3倍といわれる。
”やぶへび”という言葉があるが、ヘビを見つけてもそっとしておくように。

※ クマ
わが故郷でクマを見たことはないが、近くの山で山菜取りの人がクマに襲われたという話
を聞いた。
今回、一人で山菜取りをしていたら、山の畑のはじを横切る黒い影発見!ドキドキしながら
見ていると、相手も立ち止まってじっとこちらを見ている。よくよく見るとカモシカのようで
ゆっくり近づいたが逃げるでもなく平然としていた。